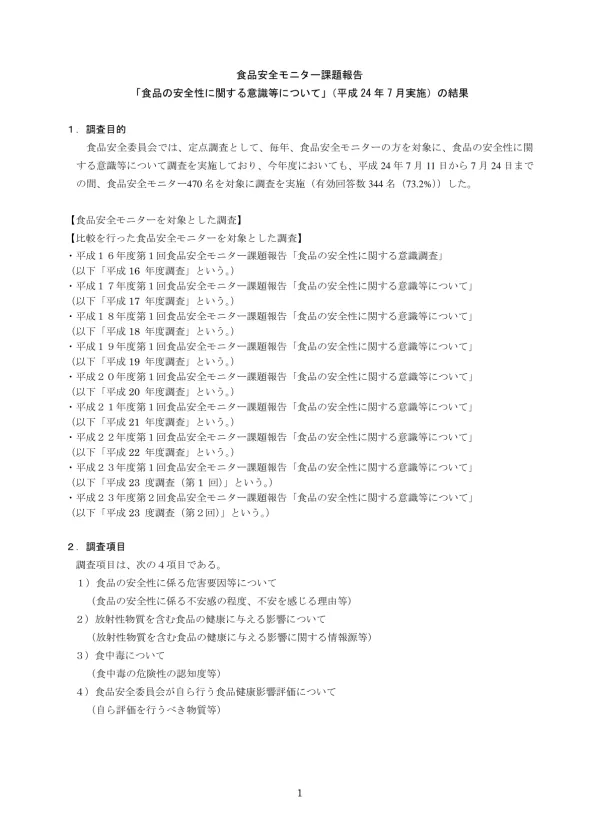
食品安全モニター調査:2012年度結果報告
文書情報
| 著者 | 食品安全委員会 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.92 MB |
概要
I.食品の安全性に関する不安 福島原発事故後の状況
平成24年度調査では、食品の安全性に関する不安は、自然災害や環境問題に比べ低いものの、依然として高い水準にあることが判明しました。特に、放射性物質を含む食品(74.2%)に対する不安が大きく、有害微生物(79.0%)による食中毒、汚染物質(カドミウム・メチル水銀等、64.5%)への懸念も根強いことが示されました。 福島原発事故後、食品からの放射性物質摂取量は東京で約0.002ミリシーベルト、福島・宮城で約0.02ミリシーベルトと推計されていますが、この数値に対する理解度は低く、不安の大きな要因となっています。不安の理由は「過去に経験したことがない事態」、「科学者の見解の相違」、「政府の情報公開の不十分さ」などに集約されます。情報源としては「新聞・インターネット」、「テレビ」、「食品安全委員会」が主要な役割を果たしています。
1. 食品安全に関する全体的な不安レベル
平成24年度の調査では、食品の安全性について「とても不安」「ある程度不安」と回答した割合は64.8%でした。これは平成21年度調査以降、最も低い数値ではありますが、依然として高い水準にあります。他の分野と比較すると、自然災害(89.6%)、環境問題(83.5%)、重症感染症(67.4%)よりは低いものの、交通事故(64.3%)、犯罪(62.5%)と同程度であり、国民の不安が大きいことが示唆されます。特に、平成23年度調査と比較すると、食品添加物や健康食品、放射性物質を含む食品を除くすべての項目で不安を示す回答割合が増加しており、国民の食品安全への意識の高まりがうかがえます。最も増加したのは器具・容器包装からの溶出化学物質で、5.0%増加(50.6%→55.6%)しています。
2. 上位3つの食品安全に関する不安事項
「非常に不安である」「ある程度不安である」の合計回答割合の上位3項目は、有害微生物(細菌・ウイルス)による食中毒等(79.0%)、放射性物質を含む食品(74.2%)、汚染物質(カドミウム・メチル水銀等)(64.5%)でした。これは平成23年度調査の上位3項目と同じですが、有害微生物と放射性物質を含む食品の順位が入れ替わっています。この結果は、福島原発事故以降、放射性物質への不安が依然として高いものの、食中毒への懸念も依然として強いことを示しています。 また、漠然とした不安が高い項目としては、体細胞クローン家畜由来食品、器具・容器包装からの溶出化学物質、遺伝子組換え食品などが挙げられ、これらの食品に対する情報提供の充実が求められます。行政による規制が不十分とされている項目は、健康食品、BSE、遺伝子組換え食品などが多く、事業者の法令遵守や衛生が不十分とされている項目は、有害微生物による食中毒、器具・容器包装からの溶出化学物質などが挙げられています。
3. 放射性物質に関する不安と情報源
放射性物質を含む食品に対する不安は、依然として非常に高いレベルにあります。回答者の不安の理由は、「過去に経験したことがない事態のため(63.5%)」、「放射線の健康影響について科学者の見解が様々であるため(59.2%)」、「政府の情報公開が不十分(47.5%)」が上位3つを占めており、情報不足や情報の信頼性に対する不安が強いことがわかります。情報源としては、「新聞(インターネットのニュースサイトを含む)」(84.9%)、「テレビ」(75.9%)、「食品安全委員会」(64.8%)が上位を占めており、特にテレビは第1位の情報源として回答者の44.2%から挙げられています。このことは、国民がこれらの情報源に大きく依存し、不安を解消するために正確で信頼できる情報提供が不可欠であることを示唆しています。また、厚生労働省が推計した、原発事故以降の食品からの放射性物質摂取量(東京:0.002ミリシーベルト~福島・宮城:0.02ミリシーベルト)に関する認識度は低く、多くの国民がその情報を知らないか、曖昧にしか理解していないことが明らかになりました。
II.不安の具体的な理由と情報源
調査では、放射性物質を含む食品への不安に関して、具体的な理由として「過去に経験したことのない事態(63.5%)」、「放射線の健康影響に関する科学者の見解の相違(59.2%)」、「政府の情報公開の不十分さ(47.5%)」が上位を占めました。また、情報源としては、「新聞(インターネットを含む)」、「テレビ」、「食品安全委員会」が主要な情報源として挙げられています。特に、テレビは回答者の44.2%が最も重要な情報源と考えていることが分かりました。
1. 放射性物質に関する不安の具体的な理由
放射性物質を含む食品に関する不安の理由として、回答者の上位3つの理由は、「過去に経験したことがない事態のため(63.5%)」、「放射線の健康影響について科学者の見解が様々であるため(59.2%)」、「政府の情報公開が不十分(47.5%)」でした。これは、福島原発事故という未曽有の事態に対する不安、科学的な知見の不足や食い違い、そして政府の情報発信に対する不信感が強く影響していることを示しています。 これらの不安は、単に数値的な情報だけでは解消されず、透明性のある情報公開と科学的な根拠に基づいた説明が求められていることを示唆しています。 その他、「安全性についての科学的根拠が納得できない」、「食品の検査体制に不安を感じる」、「自分の被ばく量がどの程度か解らないため」、「新しい規制値では納得できない」、「周囲が心配しているので自分も心配になる」といった意見も挙げられており、不安の複雑さを示しています。
2. 情報源としてのメディアと政府機関の役割
食品の安全性に関する情報源として、新聞(インターネットを含む)、テレビ、食品安全委員会が上位を占めており、特にテレビが最も重要な情報源として認識されています。回答者の44.2%がテレビを第一の情報源と回答しており、メディアの情報発信が国民の不安に大きな影響を与えていることが分かります。一方、食品安全委員会も重要な情報源として認識されており、64.8%が上位5位以内に選んでいますが、テレビや新聞に比べると影響力は劣るという結果となっています。 このことから、国民への情報伝達において、メディアによる正確かつ分かりやすい情報発信の重要性、そして食品安全委員会等の政府機関による信頼できる情報提供の必要性が改めて浮き彫りになっています。厚生労働省の情報提供についても、国民の理解度を高めるための工夫が求められます。
3. その他の食品に関する不安と情報源
放射性物質以外にも、有害微生物、汚染物質、食品添加物、遺伝子組換え食品、BSEなど、様々な食品に関する不安が示されています。これらの不安の背景には、「行政による規制が不十分」、「事業者の法令遵守や衛生が不十分」、「消費者の理解が不十分」といった要因が挙げられており、それぞれの分野において、より厳格な規制、事業者の責任ある行動、そして消費者のための分かりやすい情報提供が求められています。 特に、健康食品に関しては、「行政による規制が不十分」とする回答割合が20.9%と高く、この分野における安全性の確保が喫緊の課題となっています。 情報源としては、それぞれの分野における専門機関やメディアからの情報が重要となるでしょう。消費者が自ら判断するための情報リテラシーの向上も課題と言えるでしょう。
III.不安の地域差と時間経過による変化
不安の程度は地域差も示しました。東北・関東地域では東日本大震災前後で大きな変化は見られませんでしたが、それ以外の地域では、「東日本大震災の前後で変化はない」とする回答割合が減少傾向にあり、「東日本大震災の直後は変化したが、現在は以前と同じに戻った」とする回答割合が増加傾向にあることが分かりました。また、性差においては、女性の方が男性に比べ、震災以降の不安の継続を強く感じている傾向が見られました。厚生労働省による推計値(東京:0.002ミリシーベルト、福島・宮城:0.02ミリシーベルト)についても、認知度が低いことが判明しました。
1. 地域差による不安の程度
食品の安全性に関する不安の程度は、地域によって差が見られました。具体的には、東北・関東地域では東日本大震災の前後で大きな変化は見られませんでしたが、東北・関東以外の地域では、「東日本大震災の前後で変化はない」とする回答割合が減少傾向を示しました。一方、「東日本大震災の直後は変化したが、現在は以前と同じに戻った」とする回答割合は増加傾向にあり、時間経過とともに不安の感じ方が変化している可能性が示唆されています。これは、震災直後の強い不安が、時間の経過とともに、ある程度は落ち着いてきたものの、依然として不安を抱えている人が多いことを意味していると考えられます。 特に、「放射線の健康影響について科学者の見解が様々であるため」という不安要因は、平成23年度調査では東北・関東以外で高く、今回調査では同程度となっています。これは、情報拡散や政府対策の影響が、地域によって異なるスピードで進んでいる可能性を示唆しています。
2. 性別による不安の差異
性差による不安の程度にも注目すべき点があります。男性の回答では「東日本大震災の前後で変化はない」とする割合が40.4%と最も高かった一方、女性では「東日本大震災以降で変化し、現在も続いている」とする割合が51.8%と最も高くなっています。この結果は、女性の方が男性よりも、震災以降の食品の安全性に対する不安をより強く、そして長期的に感じている可能性を示唆しています。この性差の原因については、更なる調査が必要となりますが、情報へのアクセスやリスクに対する認識の差などが考えられます。 食品安全に関する情報発信においては、このような性差を考慮したアプローチが必要となるでしょう。 例えば、女性特有の生活様式や情報収集方法などを考慮した情報提供方法の検討が求められます。
3. 放射性物質摂取量に関する認識の低さ
厚生労働省が推計した、原発事故以降の食品からの放射性物質摂取量(東京:0.002ミリシーベルト~福島・宮城:0.02ミリシーベルト)に関する認識度が低いことも重要な点です。 調査では、「まったく知らない」または「何となく聞いたことがあるが、はっきりとは知らない」と回答した割合が50.0%と半数を超えており、国民の多くが、この重要な情報を正確に把握していないことが明らかになりました。この情報への理解度が低いことが、食品の安全性に対する不安の要因の一つとなっている可能性が高いです。 この結果を受けて、政府や関係機関は、国民への情報伝達方法の改善、分かりやすい情報提供の強化が急務であると言えるでしょう。 数値データだけでなく、具体的な影響や対策などを分かりやすく説明する努力が求められます。
IV.食品安全委員会による評価の必要性
調査では、食品安全委員会による迅速な評価が必要とされる物質として、バナジウム、食品添加物(特にカルシウム塩)、調理器具・容器からの溶出化学物質などが挙げられました。これらの物質に関する具体的な不安の理由や、危害要因に関する情報、国内外の評価状況などが示されています。特に、バナジウムについては、天然水やホヤへの高濃度蓄積が懸念されており、その影響の検討が求められています。
1. 食品安全委員会による迅速な評価が必要とされる物質
調査結果において、食品安全委員会が迅速に評価を進めるべきと考える物質として、いくつかの物質が挙げられています。具体的には、バナジウム、食品添加物(特にカルシウム塩)、そして調理器具・容器からの溶出化学物質などが挙げられています。これらの物質に関しては、国民の間に漠然とした不安ではなく、科学的知見に基づいた具体的な懸念が存在しており、食品安全委員会による専門的な評価が求められていることを示唆しています。 バナジウムに関しては、ラットの母体毒性に関するデータや、バナジウムを濃縮する性質を持つホヤの摂取習慣などから、その影響の検討が必要とされています。また、食品添加物のカルシウム塩については、厚生労働省が上限量設定を削除した理由が提示され、その科学的根拠の再検証の必要性が示唆されています。調理器具・容器からの溶出化学物質に関しては、多様な材質が存在する中で、ガラス質のホウロウなどの安全性評価が求められています。
2. 各物質に対する懸念の理由と背景
各物質に対する懸念の理由は、それぞれ異なっています。バナジウムについては、日本国内で基準値を超えるバナジウム含有の天然水が販売されていること、富士山麓の住民の飲料水にも基準値を超えるものがある可能性、そしてホヤの摂取習慣を考慮した影響の検討が必要であることが挙げられています。カルシウム塩については、厚生労働省が上限量設定を削除した理由として、石灰類の混入状況の想定難しさ、カルシウム摂取量の少なさなどが挙げられていますが、この判断の妥当性について更なる科学的根拠が求められています。調理器具・容器からの溶出化学物質については、多様な材質の中で、食品の素材を痛めにくいガラス質のホウロウなどの、健康被害防止効果の高い器具の科学的な評価を求める声が上がっています。これらの懸念は、科学的な裏付けに基づいた評価と情報提供が重要であることを示しています。
3. 食品安全委員会の役割と今後の課題
調査結果からは、食品安全委員会による科学的な評価の重要性と、国民への情報発信の必要性が改めて浮き彫りになっています。 国民の不安を解消するためには、食品安全委員会がこれらの物質について、科学的根拠に基づいた評価を行い、その結果を分かりやすく国民に伝えることが重要です。 また、今回の調査では、食品安全委員会から定期的に情報提供を受けている食品安全モニターが回答者であることに留意する必要があるとされています。これは、モニター層の意見が必ずしも一般国民全体を代表するものではない可能性を示唆しており、より広範な層への調査が必要となるでしょう。食品安全委員会は、専門家としての知見を活かし、国民の不安に応えるための積極的な情報発信と、科学的な評価体制の強化に取り組む必要があります。
V.その他の食品安全に関する懸念事項
調査では、食品添加物、遺伝子組換え食品、健康食品、BSEなどについても、不安や懸念が示されています。これらの食品に対する不安の根拠として、「行政による規制の不十分さ」、「事業者の法令遵守や衛生の不十分さ」、「消費者の理解不足」などが指摘されています。特に、健康食品については、「行政による規制が不十分」とする回答割合が最も高く(20.9%)、安全性の確保が重要な課題となっています。
1. 食品添加物 遺伝子組換え食品 健康食品に関する不安
調査では、放射性物質以外にも、食品添加物、遺伝子組換え食品、健康食品などに対する不安が示されています。これらの食品に対する不安の背景には、行政による規制の不十分さ、事業者の法令遵守や衛生管理の不十分さ、そして消費者の理解不足などが挙げられています。具体的には、健康食品については、「行政による規制が不十分」と回答した割合が20.9%と最も高く、国民の間に強い懸念があることがわかります。 遺伝子組換え食品についても、「行政による規制が不十分」と回答した割合が12.4%、「事業者の法令遵守や衛生が不十分」と回答した割合が11.5%と高く、安全性の確保と情報開示の透明性が求められています。食品添加物についても、CODEXで基準が設定されていないものがあるなど、科学的な裏付けに基づいた規制と情報提供が重要視されています。これらの不安要素は、行政、事業者、消費者の三者による連携と透明性の高い情報公開によって解消していく必要があります。
2. BSE 牛海綿状脳症 とその他の食品安全に関する懸念
BSE(牛海綿状脳症)についても、国民の間に不安が存在しています。「行政による規制が不十分」と回答した割合は13.9%に上り、適正な管理体制の構築と情報公開が求められています。 不安の理由は、治療方法がないこと、発症者の存在が恐怖心を煽ること、そして適正な管理が行われているかどうかの不安などが挙げられています。 その他、器具・容器包装からの溶出化学物質、家畜用抗生物質、肥料・飼料などについても、不安や懸念が示されています。「事業者の法令遵守や衛生が不十分」と回答した割合が、有害微生物による食中毒等(20.8%)、器具・容器包装からの溶出化学物質(16.0%)、家畜用抗生物質(11.5%)で高く、これらの分野における衛生管理の徹底と情報公開が重要となります。輸入食品の包装についても懸念の声が上がっており、安全な流通システムの構築が求められています。
3. 不安を感じていない理由と今後の課題
一方、汚染物質(カドミウム、メチル水銀等)について、不安を感じていないと回答した人(2名)は、自然界における微量汚染であり、個体差による摂食方法が正しければ問題ないと考えていると回答しています。しかし、これはあくまで個人の見解であり、一般化できるものではありません。 食品安全に関する不安の解消には、科学的根拠に基づいた情報提供に加え、消費者の理解促進も不可欠です。 そのためには、専門機関による分かりやすい情報発信、教育啓発活動の充実、そして事業者による積極的な情報開示が求められます。 また、今回の調査では、食品安全に関する不安は、個人の知識や情報へのアクセス、そしてリスクに対する認識によって大きく異なることも示唆されています。今後、より多角的な視点から、国民全体の食品安全に関する理解を深めていくための取り組みが必要となります。
