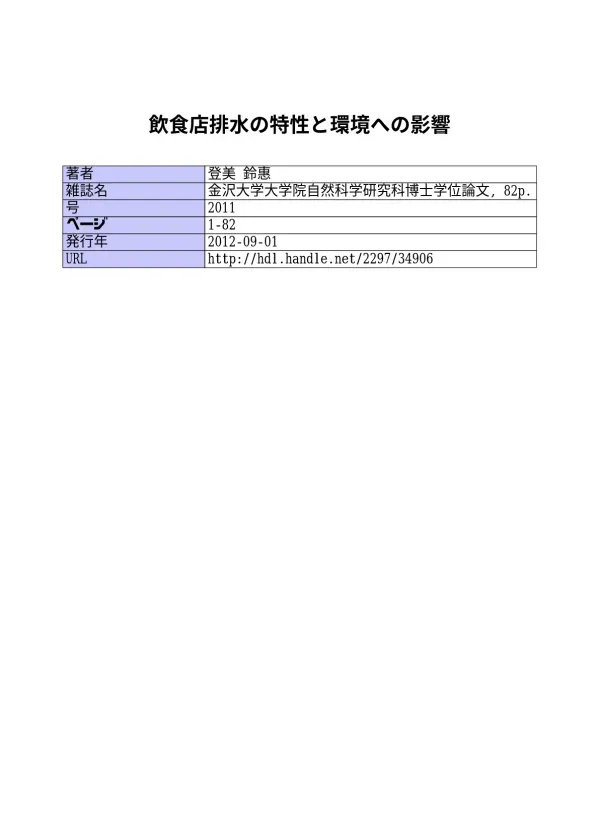
飲食店排水:環境影響と対策
文書情報
| 著者 | 登美 鈴惠 |
| 学校 | 金沢大学大学院自然科学研究科 |
| 専攻 | 環境科学専攻 環境計画講座 |
| 文書タイプ | 博士論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.49 MB |
概要
I.飲食店排水の実態とグリストラップの課題
本研究は、日本の公共用水域における水質汚濁、特にBODとCODの環境基準達成率の低さを背景に、小規模事業場からの排水、中でも飲食店排水に焦点を当てています。多くの飲食店は、1日当たり排水量50m³未満で水質汚濁防止法の規制対象外であり、グリストラップを経由して直接公共用水域または下水道に排水されています。特に油分を多く含む飲食店排水は、景観悪化や水生生物への影響、下水道管の詰まり、合流式下水道区域での雨天時流出による水質汚濁を引き起こす懸念があります。研究では、金沢市と小松市の飲食店を対象に、グリストラップの管理状況や排水特性を調査しました。
1. 公共用水域の水質汚濁と小規模事業場の排水問題
日本の公共用水域では、BOD(生物化学的酸素要求量)とCOD(化学的酸素要求量)の環境基準達成率が低い状況が続いています。水質環境基準は、人の健康保護と生活環境保全の2つに大別され、前者はカドミウムなど28項目(平成24年6月現在)、後者は水素イオン濃度など10項目が基準として設定されています。公共用水域の水質改善のためには、小規模事業場からの排水対策が急務とされており、その中でも特に排水量50m³/日未満の小規模事業場は、水質汚濁防止法の規制対象外であるため、深刻な問題となっています。平成22年度のデータによると、届出が必要な特定事業場267,499件のうち、89%にあたる237,027件が規制の適用外の小規模事業場であり、その多くは飲食店や食品加工場です。本研究では、これらの小規模事業場の中でも、特に飲食店からの排水に焦点を当て、その特性や環境への影響を調査することを目的としています。飲食店は、その規模が小さく、特定施設の条件を満たすものは極めて少ないのが現状です。
2. 飲食店排水の特徴と既存研究の現状
飲食店排水は、生活雑排水と比較して汚濁物質濃度が高い傾向にあります。既存研究では、小規模飲食店排水の汚濁負荷量に関する調査が報告されており、BODやCOD削減には油分除去装置の設置が必須にもかかわらず、未処理で排出する店舗が過半数を占め、特に小規模な店舗ほどその割合が高いという結果が示されています。また、調理器具や容器に付着した食用油、調味料、原材料の残渣などが排水されるため、COD、油分、SS(懸濁物質)などが多くなり、対策が求められています。しかしながら、飲食店排水の実態調査や研究事例は全体的に少ないのが現状です。既存の技術開発事例としては、厨房排水から排出される高濃度の油分を除去するための技術開発が中心であり、「グリストラップにおける水と油脂分の分離機能向上」、「油脂分解菌と微生物付着担体の相乗効果」、「高濃度ノルマルヘキサン抽出物質と有機物(BOD)の除去技術」、「SSと油脂類の部分的な除去」などの技術開発が行われています。近年では、グリストラップの管理を容易にするために、油吸着材や微生物製剤、界面活性剤などの投入、ばっ気などの様々な方法が考案されていますが、その効果には不明な点が多く、界面活性剤やばっ気によって油分が分散され、本来の機能を損なう可能性も指摘されています。
3. 研究の目的と対象範囲
本研究の目的は、飲食店からの排水、特にグリストラップを通じた油分含有排水が公共用水域や下水道に及ぼす影響を明らかにすることです。多くの飲食店は、水質汚濁防止法の適用を受けない排水量50m³/日未満の小規模事業場に該当し、グリストラップを経由して直接公共用水域または下水道に排水されています。この高濃度の油分を含む排水は、公共用水域では油膜による景観悪化や生物への影響、下水道では排水管の詰まりや処理場の処理機能への影響、合流式下水道区域では雨天時のオイルボールによる水質汚濁を引き起こす可能性があります。本研究では、まず厨房排水の水質調査を行い、その特性を明らかにし、グリストラップにおける油分とSSの除去率を求めます。次に、合流式下水道区域を有する金沢市と小松市の飲食店を対象に、グリストラップに関するアンケート調査を行い、厨房排水量を試算し、グリストラップの管理状況と問題点を明らかにします。さらに、グリストラップの管理に関する規制はなく、適切な管理が行われていないケースも多く、長期間貯留された油脂の腐敗による悪臭などの問題も発生しています。これらの問題点について、実態を調査し、改善策を検討することを目的としています。
II.厨房排水の水質調査とグリストラップの油分 SS除去率
金沢大学学生食堂2ヶ所での水質調査では、排水中の油分濃度、SS(懸濁物質)、TOC(全有機性炭素)などを測定しました。排水は、特に昼時に油分とSS濃度が高く、食器洗浄機の使用による高水温・高pH環境が、グリストラップ内での油分の分離を阻害していることが示唆されました。グリストラップにおける油分とSSの除去率は非常に低く、4~15%と10~37%でした。これは、グリストラップの設計や管理に課題があることを示唆しています。
1. 金沢大学学生食堂における厨房排水の水質調査
本研究では、金沢大学角間キャンパスの学生食堂2ヶ所を対象に、厨房排水の水質調査を実施しました。調査期間は2008年11月から2011年7月までの計7回で、日変動調査と週変動調査を行いました。日変動調査では、食堂の営業形態に合わせてほぼ2時間おきにグリストラップの流入水と流出水を採取し、その場で流量、水温、pHを測定しました。採取した排水は実験室に持ち帰り、油分濃度、SS(浮遊物質)、TOC(全有機性炭素)、DOC(溶存態炭素)、TN(全窒素)濃度(一部実験のみ)を測定しました。週変動調査では、日変動調査の実施日を含む1週間、油分濃度のピークが認められる12時30分に同様の採水を行いました。これらの調査により、時間帯や曜日による排水水質の変化を詳細に分析しました。分析項目には、油分濃度、SS、TOC、DOC、TNに加え、水温とpHも含まれ、特に油分濃度とSS濃度は12時30分頃にピークを示す傾向が見られました。
2. グリストラップにおける油分とSSの除去率
学生食堂のグリストラップにおける油分とSSの除去率を算出するため、毎日グリストラップのメンテナンスに合わせ、浮上した油分とバスケットに堆積した固形物を全て回収しました。回収した油分は乾燥後、重量を測定し、油分濃度計用溶媒を用いて油分抽出を行い、回収油分量を求めました。固形物についても同様に乾燥重量を測定後、ミキサーで破砕・均質化し、油分抽出を行いました。これらの結果から、グリストラップにおける油分と固形物の回収量、ひいては除去率を算出しました。実験結果では、油分の回収率は4~15%、固形物の回収率は10~37%と非常に低い値を示しました。これは、グリストラップ内の水温が30℃を超えることが多く、pHも9以上のアルカリ性を示すことが多かったため、食器洗浄機用強アルカリ性洗剤の使用が油分の分散状態を生じさせ、グリストラップ内での浮上分離を妨げている可能性が示唆されました。日変動調査の結果、油分濃度は時間帯によって大きく変動し、ピーク時には高い値を示す一方、グリストラップの前後で油分濃度が低下する時間帯と増加する時間帯が存在し、流出濃度が流入濃度の変化を完全に反映していないことが分かりました。
III.飲食店におけるグリストラップ管理の実態調査
金沢市と小松市の飲食店を対象としたアンケート調査(回収率25.7%、239店舗)の結果、床面積100m²以下の小規模店舗が72%を占めていました。グリストラップの清掃頻度は、毎日清掃を行う店舗は少なく、月1回以上の清掃を行う店舗は約50%でした。専門業者による清掃も十分とは言えず、グリストラップからの悪臭や汚泥堆積の問題が多くの店舗で発生していました。バイオ製剤や酵素剤、ばっ気などの改善策も導入され始めていますが、その効果は不明な点が多く、さらなる検証が必要です。食器洗浄機の普及率は62.5%で、排水量の増加とアルカリ性洗剤の影響が懸念されます。
1. アンケート調査の概要と対象地域
本研究では、合流式下水道区域を有する金沢市と小松市の飲食店を対象に、グリストラップに関するアンケート調査を実施しました。調査対象は、金沢市と小松市の飲食店で、業種別の割合を考慮して店舗を抽出し、アンケートを送付しました。回収率は25.7%で、金沢・小松の全飲食店の約7.8%にあたる239店舗から回答を得ることができました。業種別では、金沢市と小松市で、その他の食堂・レストランを除き、ほぼ同様の傾向を示しました。ただし、喫茶店やその他の一般飲食店は抽出率が低く、これは喫茶店では食事を提供していない店舗も多いことを考慮したためです。後述の喫茶店の集計は「その他の一般飲食店」に含めています。店舗規模については、金沢市と小松市ともに事業所統計を用いて分析を行いました。アンケート回答では、従業員数のデータが少なく、床面積と客席数のデータが豊富だったため、両者の相関関係を分析した結果、高い相関(R²=0.91)が確認されました。客席数のみが記載された店舗については、客席数から床面積を算出して分析に用いました。
2. 飲食店の規模とグリストラップの管理状況
床面積データが得られた210店舗について、規模別の割合を分析した結果、床面積100m²(30坪)以下の店舗が72%を占めていました。これは、本調査でも小規模な事業所を多く抽出していることを示しています。床面積40m²以下の極めて小規模な店舗でも30%、従業員数4人以下の小規模な店舗でも約半数がグリストラップを利用していました。食器洗浄機の普及率は62.5%で、規模の大きい店舗ほど食器洗浄機を設置している傾向が見られました。食器洗浄機の普及は、高水温と高pH環境をもたらし、金沢大学食堂の排水と同様に、油分の分離を妨げていると推定されます。一般家庭の食器洗浄機普及率との比較も示唆されており、飲食店における食器洗浄機の普及が排水処理に及ぼす影響が示唆されています。グリストラップの容量算定の根拠となっている標準値と、アンケート調査結果から算出した床面積当たりの排水量を比較したところ、標準値よりも高い値を示す店舗が多く存在することがわかりました。グリストラップの滞留時間は、0.02~40.7分と大きなばらつきがあり、標準的な滞留時間(約2分)よりも長いものが多い一方、1分未満の短い滞留時間のものも存在することがわかりました。
3. グリストラップの清掃頻度と管理方法
グリストラップの清掃頻度については、大学食堂では毎日浮上した油やゴミの除去を行っているのに対し、アンケート調査の結果では、毎日清掃を行っている店舗は1割にも満たないことが分かりました。月1回以上の清掃を行う店舗は約50%でしたが、年に数回やほとんど清掃を行っていない店舗も少なくありませんでした。専門業者による清掃は、月1回~年1回の頻度で行っている店舗が30%を占める一方で、ほとんど行っていない、もしくは無回答の店舗が半数以上であり、清掃が適切に行われていない店舗が多いと推定されます。このような管理の不徹底が、悪臭などの問題を引き起こす原因となっている可能性が考えられます。グリストラップの管理を容易にするため、油吸着材、微生物製剤、界面活性剤などの投入、ばっ気、オゾン処理などの様々な方法が考案されていますが、その効果については不明な点が多く、油分を分散させて本来の機能を損なう可能性も懸念されます。アンケートでは、水切り袋、バイオ製剤、酵素剤は効果があると回答した店舗が7割以上だった一方、油吸着材は効果がないと回答した店舗が約半数でした。ばっ気やオゾン処理を導入している店舗はまだ少数でした。また、自由記述欄からは、「油やゴミを流さないようにする」「清掃に気をつけている」といった回答が多く見られました。
IV.飲食店由来油分の下水道 公共用水域への影響
金沢市城北水質管理センターのデータを用いた分析では、飲食店由来の年間油分負荷量は230トンと推定され、排水量割合9%に対し、油分排出割合は43%と非常に高い割合を占めていました。下水道未整備地域では、飲食店からの油分が直接公共用水域に流出し、水質汚濁の原因となっている可能性が高いです。御祓川を例に、下水道未接続の飲食店からの油分による河川への影響を調査した結果、油膜の発生が確認され、特に冬季の雪解け水の影響で油分濃度が高まる可能性が示唆されました。特に、下水道未接続率28%の七尾市では、年間9.3トンの油分が公共用水域に流出すると推定されました。
1. 金沢市城北水質管理センターへの飲食店由来油分負荷量の推計
金沢市城北水質管理センター処理区における飲食店由来の油分負荷量を推計するため、金沢市事業所統計から従業員規模別の飲食店数と従業員数を取得しました。城北水質管理センター処理区は、金沢市で最初に下水道が整備された地域で、旧市街地の大部分をカバーし、多くの飲食店が集中しています。金沢市の指導により、処理区内の飲食店はすべて下水道に接続されています。油分濃度の算出には、第2章で実施した大学食堂の調査結果におけるグリストラップからの流出水中の油分濃度を用いました。平成20年から22年の3年間の城北水質管理センターの運転データから、流入排水量とノルマルヘキサン抽出物質濃度を用いて、飲食店由来の年間油分負荷量を算出した結果、230トンと推定されました。さらに、飲食店、一般家庭、その他からの排水量と油分負荷量の割合を比較したところ、排水量の割合は飲食店が9%、家庭が49%、その他が42%であるのに対し、油分排出割合は飲食店が43%、家庭が45%、その他が12%と、飲食店からの油分排出割合が排水量割合に比べて非常に高いことが分かりました。このことから、飲食店における発生源での油分削減や処理が強く求められることが示唆されました。
2. 下水道未整備地域における公共用水域への油分流出 御祓川を例としたケーススタディ
下水道が未整備の地域では、飲食店からの油分が直接公共用水域に流出し、水質汚濁を引き起こす可能性があります。そこで、金沢市における御祓川下流域を対象に、飲食店由来の油分による河川への影響を調査しました。御祓川下流の仙対橋下では、2009年度までは環境基準を達成していませんでしたが、近年の市街地区域の下水道整備により、2010年度に初めて環境基準値を下回りました。しかし、下水道が未普及の地域が流域に存在するため、御祓川分岐点より下流域を対象に、飲食店由来の油分による河川への影響を詳細に調査しました。調査では、複数の水路における水質(水温、pH、油分濃度、SS、TOC、DOC)を測定しました。その結果、下流付近の下水道未接続の飲食店が多い水路③では、油分濃度が最大2.4mg/Lと高い値を示し、水面に油膜が確認されました。これは、下水道未接続の飲食店からの油分排水が御祓川の水質汚濁に影響を与えていることを示唆しています。七尾市全体を対象とした推計では、下水道未接続率28%を考慮し、大学食堂の調査結果を基に年間9.3トンの油分が公共用水域に流出すると推定されました。
文書参照
- 全国下水道普及率 (公益社団法人 日本下水道協会)
