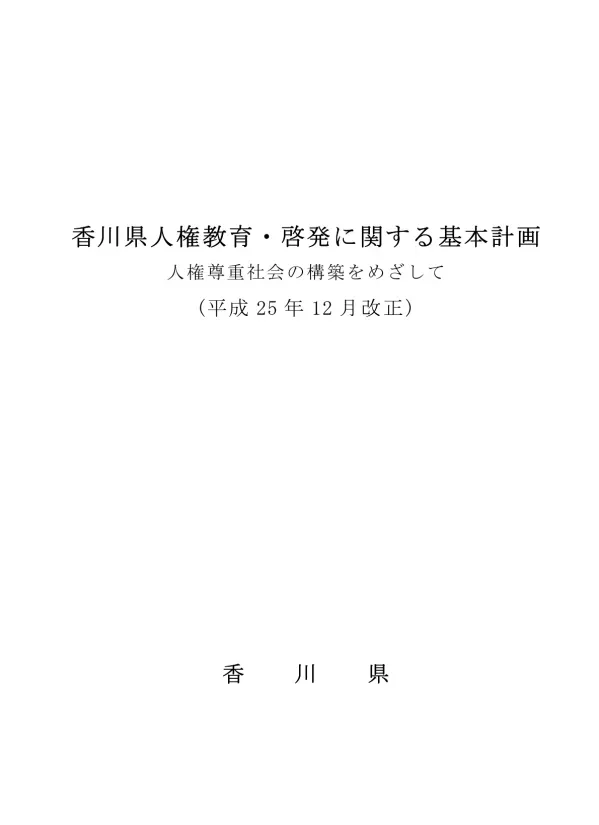
香川県人権教育啓発計画
文書情報
| 著者 | 香川県人権啓発推進会議 |
| 専攻 | 人権教育 |
| 場所 | 香川県 |
| 文書タイプ | 基本計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 336.47 KB |
概要
I.学校における人権教育の推進
本計画は、学校教育において、教職員の資質向上のための研修(人権教育に関する研修)や学習指導資料の配布を通して、幼児・児童・生徒一人ひとりを大切にした教育を進めます。社会科をはじめとする各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などで、発達段階に応じた人権の意義や大切さを教え、様々な人権問題(差別、偏見、いじめなど)への正しい理解と解決に向けた学習を行います。人権集会での意見発表や、障害者・高齢者との交流活動などの実践的な取り組みも推進します。家庭や地域社会、校種間の連携を強化し、より効果的な人権教育を展開します。
1. 教職員の資質向上と人権教育推進体制の強化
学校における人権教育の推進のため、教職員の資質向上を図るための研修が実施されます。研修内容は、人権教育に関する様々な内容を含み、教職員の専門性を高めることを目指しています。具体的には、人権教育に関する最新の知識やスキル、効果的な指導方法などを学ぶ機会が提供されます。さらに、研修と並行して、各学校への学習指導資料の配布や人権教育実践に対する指導・助言も行われ、学校現場での人権教育を効果的に推進するための支援体制が構築されます。これらの取り組みを通じて、教職員が人権尊重の精神に基づいた教育を円滑に進められるよう、体制の強化が図られます。 また、教材や指導方法の開発・提供も重要な要素であり、実践事例の共有や学習教材に関する情報提供を通して、各学校の状況に合わせた柔軟な対応を可能にしています。教職員一人ひとりが、生徒一人ひとりの人権を尊重した教育を実践できるよう、継続的な支援が行われます。
2. 各教科 活動における人権教育の展開
人権教育は、社会科のみならず、道徳、特別活動、総合的な学習の時間など、あらゆる教科や活動を通じて展開されます。それぞれの教科や活動の特性を活かしつつ、発達段階に合わせた適切な人権教育が行われるよう、カリキュラムが編成されます。低年齢層には、人権の基礎的な概念や重要性を分かりやすく伝える工夫がなされ、高年齢層には、より複雑な人権問題や社会問題を深く掘り下げて学習する機会が提供されます。 具体的には、人権の意義や大切さを学ぶだけでなく、差別や偏見、いじめといった具体的な人権問題について、正しい理解と解決策を学ぶ学習活動が組み込まれます。これにより、生徒が人権問題への意識を高め、主体的に問題解決に取り組む姿勢を養うことを目指しています。さらに、人権集会での意見発表や、障害者や高齢者との交流活動など、実践的な活動を通して、人権尊重の意識をより深く理解できるよう工夫が凝らされています。
3. 家庭 地域社会との連携による人権教育の充実
学校における人権教育の効果を高めるためには、家庭や地域社会との連携が不可欠です。そのため、保護者への人権教育に関する資料配布や、地域住民向けの研修会や講演会などを積極的に開催します。家庭での人権教育の重要性を強調し、保護者と協力して人権教育を推進できるよう、連携体制を構築します。 地域社会との連携は、学校だけではカバーできない範囲の教育を補完する役割を果たします。地域住民との交流やボランティア活動などの実践的な機会を通じて、人権尊重の意識を醸成する取り組みを推進します。また、幼稚園・保育所から高等学校・特別支援学校まで、各校種の連携を強化することで、年齢や発達段階に合わせた継続的な人権教育を実現するための体制づくりを推進します。
II.社会教育における人権啓発の促進
学校、家庭、地域社会との連携を重視し、公民館等での研修講座の開催や人権講演会の実施、啓発資料・パンフレットの配布を通して、家庭や地域住民への人権教育(人権啓発)を推進します。社会教育指導者への研修による資質向上にも取り組みます。特に家庭は子どもの人権意識を育む上で非常に重要であるため、家庭用指導資料の配布など、家庭教育の支援を強化します。 人権意識の向上に繋がるよう、多様な啓発活動を実施します。
1. 地域住民への人権啓発活動の展開
社会教育における人権啓発の促進のため、学校や家庭、地域社会との連携を重視した活動が展開されます。公民館などを活用した研修講座や、地域住民を対象とした人権講演会が開催され、人権に関する正しい知識や理解を深める機会が提供されます。 啓発資料やパンフレットの配布も重要な活動であり、分かりやすく、多様な人権問題に関する情報を提供することで、住民の理解促進を目指します。これらの活動は、地域住民が人権問題への意識を高め、人権尊重の社会を築くための基盤となることを目指しています。特に、家庭での人権教育の重要性が高く認識されているため、保護者向けの指導資料なども配布され、家庭教育への支援も強化されます。地域住民が日常的に人権問題に関心を持ち、行動に移せるよう、多角的なアプローチが図られます。
2. 社会教育指導者養成による人権啓発の質向上
人権啓発活動の質を高めるためには、指導者の資質向上も不可欠です。社会教育指導者などを対象とした研修が実施され、人権教育に関する専門知識やスキル、効果的な指導方法などが習得されます。研修内容は、最新の知識や事例を取り入れ、常に質の高い人権教育を提供できるよう、内容の充実が図られます。 指導者自身が人権問題への深い理解を持ち、熱意を持って活動に取り組めるよう、研修を通してモチベーションの向上も目指します。研修修了者による地域での活動支援や、他の指導者への指導・助言を通して、人権啓発の輪を広げていく仕組み作りも重要な要素となります。質の高い指導者が育成されることで、地域全体での人権意識の向上に繋がるよう、継続的な人材育成への投資が続けられます。
3. 家庭教育支援による人権意識の涵養
家庭は、子どもの人権意識を育む上で重要な役割を担います。そのため、家庭への支援を強化し、家庭における人権教育を促進するための取り組みが実施されます。具体的には、幼児・小学生・中学生の保護者に対して、人権教育に関する家庭用指導資料が配布され、家庭での人権教育をサポートする情報を提供します。 また、子育てに関する不安や悩みへの相談体制の充実も図られ、保護者が安心して子育てに取り組めるよう、必要な支援が提供されます。保護者向けの学習機会の充実や、家庭教育に役立つ様々な情報の提供を通して、保護者が人権尊重の意識を高め、子どもたちに正しい価値観を育むための支援がなされます。家庭と学校、地域社会が連携することで、より効果的な人権教育が実現することを目指します。
III.県民を対象とした人権啓発活動
人権週間などの節目を捉えた県全体での取り組みや、「じんけんフェスタ」の開催、街頭キャンペーン、啓発ポスター・パネル展などを年間を通して実施します。リーフレット・パンフレット・ポスターの配布、講習会・研修会の開催、マスコミを活用した啓発活動など、多様な手法を用いた創意工夫を凝らした啓発活動を展開します。国、市町、公益法人、民間団体、企業等との連携も強化します。 人権問題への理解を深めるため、多角的なアプローチを行います。
1. 人権週間等の節目行事と継続的啓発活動
県民を対象とした人権啓発活動は、人権週間などの節目行事を効果的に活用し、県全体を巻き込んだ取り組みが展開されます。これにより、県民全体の人権意識の向上を図ると共に、人権問題への関心を高める機会を創出します。 単発的なイベントだけでなく、年間を通じた継続的な啓発活動も重要な要素です。 「じんけんフェスタ」のような、イベント的な要素を取り入れた明るく楽しい雰囲気の中で人権問題を考えてもらう機会の提供や、街頭キャンペーン、啓発ポスター・パネル展なども実施され、様々な年齢層や関心を持つ県民にアプローチします。これらの多様な活動を通じて、人権問題への理解を深め、人権尊重の意識を県民全体に浸透させることを目指します。多様な啓発手法を用いることで、より多くの県民に人権問題への関心を促し、理解を深める効果的な啓発活動を目指します。
2. 多様な啓発手法と情報発信
人権啓発活動においては、多様な手法と情報発信が用いられます。リーフレット、パンフレット、啓発ポスターなどの配布による情報提供、人権に関する講習会や研修会の開催による学習機会の提供、新聞報道やテレビ・ラジオのスポット放送など、マスコミを活用した啓発活動も積極的に行われます。 これらの多様な手法は、人権問題全般や個別の課題に応じて適切に選択・活用され、それぞれの対象者にとって分かりやすく、理解しやすい方法が用いられます。 各手法においては、創意工夫を凝らし、より効果的な情報発信を行うために、工夫が凝らされています。例えば、視覚的に分かりやすいデザインのポスターや、簡潔で分かりやすい言葉遣いのリーフレットなど、それぞれの媒体に適した表現方法が用いられます。県民一人ひとりが理解しやすいように、情報伝達の質を高める努力が続けられます。
3. 関係機関との連携による啓発活動の強化
人権啓発活動の効果を最大化するために、国、市町、公益法人、民間団体、企業など、様々な関係機関との連携が強化されます。それぞれの機関が持つ資源やノウハウを共有し、協力することで、より総合的で効果的な啓発活動を展開します。 連携強化の取り組みによって、啓発活動の範囲を広げ、より多くの県民にリーチすることを目指します。また、連携を通して、啓発活動の企画立案から実施、評価に至るまで、各機関の役割分担を明確化し、効率的な運営体制を構築します。 これにより、重複を避け、資源の無駄遣いを防ぎながら、県民全体への啓発効果を高めることが期待されます。関係機関との緊密な連携により、人権啓発活動の持続的な発展を目指します。
IV.人権教育 啓発の充実に向けた取り組み
人権教育・啓発においては、人権の意義・重要性に関する知識の習得に加え、人権問題を直感的に捉える感性、日常生活における人権への配慮を態度や行動に表せるような人権感覚を養うことが重要です。そのため、対象者の発達段階や日常生活経験を踏まえた創意工夫を凝らした指導を行います。特に幼児期からの人権尊重の精神の芽生えを育むことに力を注ぎます。人権一般の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権問題に即した個別的な視点からのアプローチの両方を重視します。
1. 人権感覚の涵養 知識 感性 行動の三位一体
人権教育・啓発の充実のためには、人権の意義や重要性を単なる知識として理解するだけでなく、人権問題を直感的に捉える感性と、日常生活の中で人権に配慮した態度や行動をとれる人権感覚を育むことが不可欠です。 そのため、対象者の発達段階や日常生活経験を考慮した、より実践的で具体的な指導方法の開発・導入が求められます。 単なる知識の詰め込みではなく、体験を通して人権の大切さを実感できるような教育、例えばロールプレイングやディスカッションなど、参加型の学習方法を取り入れることが重要になります。 また、人権尊重の精神は人格形成の早い時期から育むべきであり、幼少期からの継続的な教育が重要となります。 これらの取り組みを通して、知識、感性、行動の三位一体となった、真に実効性のある人権感覚の育成を目指します。
2. 人権教育 啓発手法の多様化 普遍的視点と個別的視点の融合
人権教育・啓発の手法として、法の下の平等や個人の尊重といった人権一般に関する普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権問題に即した個別的な視点からのアプローチの両方が重要となります。 この両者のアプローチを効果的に組み合わせることで、人権尊重の理念についての理解を深めることができます。 普遍的な視点からのアプローチでは、人権の普遍的な価値や重要性を理解させ、個別的な視点からのアプローチでは、地域の実情や具体的な人権問題を踏まえた上で、人権問題を正しく理解し、物事を合理的判断できる精神を養うことを目指します。 多様な手法を効果的に組み合わせることで、より深く、多角的に人権問題を理解できるよう、柔軟な指導方法の確立が求められます。
3. 早期からの人権尊重の精神の育成 感性と行動への重視
人権尊重の精神は、人格形成の早い時期から感性として育むことが重要です。幼少期から、人権尊重の精神が自然と身につくよう、工夫を凝らした指導が必要となります。 そのためには、遊びや生活の中で、自然と人権尊重の考え方に触れられるような環境づくりが大切です。 また、人権教育・啓発は、知識の習得にとどまらず、人権問題を敏感に感じ取る感性や、人権尊重の気持ちが態度や行動に自然と表れるような、豊かな人権感覚を育むことを目指します。 これらの取り組みを通じて、将来、社会で活躍する上で必要な、人権感覚を備えた人材の育成を目指します。 人権尊重の精神を社会全体に浸透させるために、早期からの教育が不可欠であるという認識が重要です。
V.実施主体間の連携強化
人権教育・啓発は様々な主体によって行われていますが、問題の複雑化・多様化に対応するため、各実施主体間の有機的で補完的な関係を構築し、連携を強化します。特に、人権意識の深化と意欲・態度の育成を目的とした指導内容・方法の充実、地域社会等との連携強化、大学等との連携強化、家庭教育の充実、そして関係機関との連携強化と協働の推進に力を入れます。
1. 関係機関との連携強化 総合的かつ効果的な推進体制の構築
人権教育・啓発をより総合的かつ効果的に推進するためには、様々な実施主体間の連携強化が不可欠です。学校、家庭、地域社会、企業、そして国や地方自治体など、それぞれの役割と責任を踏まえ、有機的で補完的な関係を構築することで、より効率的で効果的な人権教育・啓発体制を構築します。 具体的には、「香川県人権啓発推進会議」や「香川県人権啓発活動ネットワーク協議会」などの既存の連携組織との連携強化を図り、情報共有や意見交換を密に行います。 また、ボランティア団体やNPO法人などの民間団体との協働も推進し、それぞれの役割や立場を尊重しながら、連携を深めていきます。これにより、人権教育・啓発活動をより広範かつ継続的に展開するための基盤を整備します。各主体がそれぞれの強みを活かし、役割分担を明確化することで、重複や無駄を省きながら、より効果的な人権啓発を目指します。
2. 理解 認識の深化と意欲 態度の育成 指導内容 方法の充実
人権についての理解と認識を深め、人権を尊重する意欲や態度の育成を促進するため、指導内容と方法の充実が図られます。学校(園・所)においては、人権問題の当事者による講演会や人権フィールドワークなどの学習活動の導入、ボランティア活動や参加型学習などの主体的な取り組みの促進、そして日常生活における不合理を敏感に感じ取る感性を育む指導法の開発などが行われます。 これらの取り組みを促進するため、指導資料の整備、実践事例や学習教材などの情報提供、活用に関する指導・助言なども実施されます。 より効果的な教育実践のため、多様な学習方法の導入や、個々の生徒のニーズに合わせたきめ細かい指導が提供されます。 人権教育の質を高め、人権尊重の意識をより深く生徒に理解させるための継続的な改善と努力が続けられます。
3. 地域社会 家庭 大学等との連携強化 一貫性のある人権教育
人権教育を効果的に推進するため、地域社会、家庭、大学等との連携が強化されます。地域社会との連携では、社会奉仕活動などの多様な体験活動や地域住民との交流機会の充実を通して、実践的な人権教育を推進します。 家庭との連携では、家庭における人権教育の重要性を示し、保護者の協力を得ながら人権教育を推進するため、保護者との連携を強化します。 保育所から高等学校・特別支援学校までの一貫した指導体制の構築を目指し、各教育機関間の連携を密にすることで、年齢や発達段階に合わせた、継続性のある教育を展開します。 大学等との連携では、人権尊重の理念の理解を深め、これまでの教育の成果を確かなものとするため、大学における人権教育の充実を支援します。 これらの連携強化を通して、学校、家庭、地域社会、大学が一体となった、一貫性のある人権教育システムの構築を目指します。
VI.女性の 人権 に関する理解と認識の促進
性差別の解消、個人の個性と能力の尊重を促すため、社会制度や慣行の見直しを促す広報・啓発を行います。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点からの総合的な健康対策、妊娠・出産に関する健康支援、HIV/エイズや性感染症など健康を脅かす問題に関する広報・啓発を推進します。また、女性へのあらゆる暴力の根絶に向け関係機関と連携し、総合的な対策を推進します。
1. 性別役割分担や偏見の見直し 社会制度 慣行の改革
女性の権利に関する理解と認識を促進するため、まず、性別だけで個人の意思に反して役割を固定的に決めつける社会制度や慣行の見直しを促す啓発活動が行われます。 性別による固定的な役割分担や偏見が、個人の個性や能力の発揮を阻害している現状を認識し、社会全体でこれらの問題を改善していく意識の定着を目指します。 具体的には、社会制度や慣行の中に存在する可能性のある性差別を分析し、個人が主体的に選択できる社会環境づくりを促進する情報発信を行います。 女性のライフステージに合わせた多様な働き方や生き方が尊重される社会を目指し、個人の自由な選択を保障する社会構造の構築に向けた啓発を行います。 性別による不平等を解消し、男女が平等に機会を得られる社会の実現を目指した啓発活動が展開されます。
2. リプロダクティブ ヘルス ライツへの理解促進 包括的な健康対策
女性の健康と権利を包括的に捉えるリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の視点から、女性のライフステージに応じた総合的な健康対策と、妊娠・出産に関する健康支援が推進されます。 女性の健康を脅かす問題、例えばHIV/エイズや性感染症、薬物乱用、喫煙や過度な飲酒などについても、啓発活動を通して正しい知識と理解を深めます。 女性の健康を維持・増進するための情報提供や、必要な医療サービスへのアクセスを確保するための支援体制の構築に努めます。 女性の健康と権利を尊重する社会を実現するため、多角的なアプローチによる啓発活動が展開されます。 女性の健康に関する情報を正確に伝え、誤解や偏見を解消することで、より健康的な生活を送れるよう支援します。
3. 女性への暴力根絶 社会意識の醸成と総合的対策
配偶者からの暴力、性犯罪、子どもに対する性暴力、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対するあらゆる暴力行為は重大な人権侵害です。 これらの暴力行為を許さない社会意識の醸成と暴力根絶に向けた取り組みが、関係機関の連携強化と総合的な対策によって推進されます。 具体的には、被害者の支援体制の強化、加害者への適切な対応、再発防止策の検討など、多角的なアプローチによる対策を講じます。 女性への暴力に関する相談窓口の周知や、被害者支援に関する情報の提供を通して、より多くの女性が適切な支援を受けられるよう努めます。 女性が安心して暮らせる安全な社会の実現のため、社会全体で問題解決に真剣に取り組む姿勢が重要視されます。
VII.子どもの人権と 人権教育
少子化、核家族化、共働き世帯の増加など、子どもを取り巻く環境の厳しさから、児童虐待、児童買春・児童ポルノ、いじめ、不登校、少年非行などの問題への対策を強化します。児童虐待の早期発見・安全確保、再発防止のための心のケア、里親制度の普及啓発、社会的な養護体制の充実を図ります。 人権意識の醸成に努めます。
1. 少子化 核家族化の進展と子育て環境の厳しさ
近年、少子化の進行、核家族化の進展、共働き世帯の増加などにより、子どもや子育てを取り巻く環境は厳しさを増しています。 特に、児童虐待が深刻な社会問題となっているほか、児童買春・児童ポルノ、薬物乱用など、子どもの健康や福祉を害する犯罪も発生しています。 また、学校においては、暴力行為やいじめ、不登校などの問題が依然として憂慮すべき状況にあり、少年非行についても、人口比や再犯者の割合が全国平均を上回るなど、厳しい状況が続いています。 こうした状況を踏まえ、子どもたちの安全と健やかな成長を確保するための対策が急務となっています。 子どもの人権を尊重し、安全で安心して暮らせる環境を確保するために、多様な支援策の必要性が高まっています。
2. 児童虐待防止と早期発見体制の構築
児童虐待の防止と早期発見のため、関係機関との連携強化による迅速な対応体制の構築が重要です。 児童虐待は重大な人権侵害であり、早期発見と適切な対応が被害拡大を防ぐ上で不可欠です。 そのため、虐待の早期発見システムの構築、そして虐待を受けた子どもへの心のケアやカウンセリング体制の充実が図られます。 虐待を行った保護者へのカウンセリングや、再発防止に向けた指導なども行われ、家庭環境の改善にも力を入れます。 また、里親制度の普及啓発や、児童養護施設における家庭的な養護の推進、自立支援機能の強化なども進められ、保護を必要とする子どもたちへの適切な支援体制が整備されます。 子どもたちの安全と幸せを最優先に考え、社会全体で子どもたちを守っていくための体制づくりが推進されます。
3. いじめ 不登校 少年非行対策の強化 学校 家庭 地域社会の連携
学校を巡る暴力行為やいじめ、不登校などの問題、そして少年非行についても、継続的な対策が求められます。少年非行については、総数は減少傾向にあるものの、人口比や再犯率が依然として高い状況であり、更なる対策強化が不可欠です。 いじめや暴力行為の防止、不登校児童生徒への支援、そして少年非行の予防教育などは、学校、家庭、地域社会が連携して取り組むことが重要です。 学校では、いじめ防止のための教育プログラムの充実や、早期発見・対応体制の強化が図られます。 家庭では、保護者への啓発活動や相談体制の充実を通して、家庭での適切な指導を促します。 地域社会では、子どもたちが安心して生活できる環境づくりや、地域住民による見守り活動の推進などが重要です。 これらの連携によって、子どもたちが安全で健やかに成長できる環境を整備します。
VIII.高齢者の 人権 と虐待防止
高齢者虐待(暴力行為、財産権の侵害など)の防止に向け、啓発活動を通して社会意識の醸成を図ります。関係機関との連携のもと、地域包括支援センターの相談窓口の周知、虐待への対応、成年後見制度の普及・利用促進を図ります。 高齢化の進展、核家族化の増加による高齢者の孤立化への対策も必要です。
1. 高齢者虐待への啓発と社会意識の醸成
高齢者に対する虐待(暴力行為、財産権の侵害、暴言、無視、介護の放棄など)は、高齢者の尊厳と人権を著しく侵害する行為です。 この問題の深刻さを広く県民に認識させ、高齢者を尊重し、虐待を許さない社会意識を醸成するため、啓発活動が積極的に展開されます。 啓発活動では、高齢者虐待の具体的な事例やその影響、そして虐待を防ぐための具体的な方法などを分かりやすく説明します。 高齢者虐待は、高齢者自身だけでなく、家族や地域社会全体の問題であることを伝え、一人ひとりが責任を持って高齢者の人権を守る意識を持つことの重要性を強調します。 高齢者虐待の相談窓口の周知や、高齢者支援に関する情報の提供を通じて、虐待の早期発見と適切な対応につなげ、高齢者が安心して暮らせる社会の構築を目指します。
2. 関係機関との連携による虐待防止対策
高齢者虐待の防止には、関係機関の連携による総合的な対策が不可欠です。各市町の地域包括支援センターが、介護や日常生活の悩みごとに関する相談に対応していることを周知するとともに、虐待への対応や成年後見制度の普及と利用促進を図ります。 地域包括支援センターを中心に、市町高齢者虐待防止センター、警察、関係機関と連携し、高齢者からの相談や通報に迅速かつ適切に対応する体制を構築します。 虐待の早期発見、迅速な対応、そして再発防止のための支援体制を整備します。 高齢者の状況把握、リスク要因の特定、そして適切な支援策の提供など、多様な機関が連携することで、高齢者虐待を未然に防ぎ、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 成年後見制度の活用促進についても積極的に取り組んでいきます。
3. 高齢化社会の進展と高齢者の課題 孤立化 孤独感への対策
今後、高齢化のさらなる進展に伴い、寝たきりや認知症など介護を必要とする高齢者が増加し、核家族化の進展により高齢者のみの世帯や高齢者のひとり暮らし世帯も増加すると予想されます。 このような状況において、高齢者の権利に関わる問題として、虐待や財産権の侵害に加え、社会参加の困難さ、職業生活からの引退や配偶者との死別による孤独感や生きがい喪失などが挙げられます。 高齢者が社会参加しやすい環境づくり、地域における交流機会の充実、そして孤独感や生きがい喪失への支援策の充実が求められます。 高齢者が地域社会の中でいきいきと生活できるよう、関係機関との連携を強化し、総合的な支援体制の構築を図ります。 高齢者の尊厳と人権を尊重し、安心して暮らせる社会の実現に向けた継続的な取り組みが重要です。
IX.障害者の 人権 と虐待防止
『かがわ障害者プラン』に基づき、地域社会のバリアを取り除き、誰もが心豊かに暮らせる社会を目指します。「香川県福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化も推進します。障害者に対する偏見・差別意識の解消、虐待防止、社会復帰支援のため、県障害者権利擁護センターを中心に関係機関と連携し、相談対応、早期発見、迅速な対応、成年後見制度の活用などを進めます。
1. 障害者プランとバリアフリー化の推進 住み慣れた地域での安心生活
本県では、「かがわ障害者プラン」(2012年3月策定)に基づき、地域社会におけるあらゆるバリア(障壁)の除去、相互支援、誰もが心豊かに暮らせる社会を目指した取り組みが進められています。 また、「香川県福祉のまちづくり条例」に基づき、バリアフリー化を推進し、全ての人が住み慣れた地域で安心して生活し、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりも推進されています。 これらの取り組みは、障害者の社会参加促進と生活の質の向上に大きく貢献しています。 しかし、障害者に対する偏見や差別意識、そして理解不足が依然として存在し、それらが障害者虐待や社会復帰の困難さに繋がっているという問題も指摘されています。 障害者の人権を尊重し、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、更なる努力が求められます。
2. 障害者虐待防止 関係機関との連携と早期発見 対応体制
障害者虐待の未然防止と早期発見、そして迅速な対応のため、県障害者権利擁護センターを中心に、市町障害者虐待防止センター、警察、香川労働局など関係機関が連携し、相談や通報への対応体制が強化されます。 家庭、障害者施設、事業所など、あらゆる場所で発生する可能性のある障害者虐待を未然に防ぐための啓発活動や、虐待の早期発見のための体制整備が推進されます。 相談や通報があった際には、関係機関が連携して迅速に対応し、必要な支援を提供します。 成年後見制度の活用促進なども含め、障害者一人ひとりに適切な支援が行き届くよう、効果的な支援体制の構築を目指します。 障害者の人権を守るため、関係機関が連携し、一体となって取り組む姿勢が重要です。
3. 障害の有無による差別のない共生社会の実現 理解と認識の促進
障害者の権利に関する正しい理解と認識を促進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、県民全てが相互に人格と個性を尊重しながら共生できる社会の実現を目指します。 そのため、障害者の人権に関する啓発活動が積極的に展開され、障害者に対する偏見や差別意識の解消に努めます。 障害者理解のための研修会や講演会、そして啓発資料の配布などが行われ、県民一人ひとりが障害者への理解を深めるよう促します。 また、障害者と健常者が共に生活する中で、それぞれの個性や能力を認め合い、尊重し合う社会の構築を目指します。 障害者と健常者が共に支え合い、共に生きる社会の実現に向けて、継続的な努力が続けられます。
X.同和問題と差別意識の解消
同和地区の生活環境の改善、県民の同和問題への理解・認識の深化を図ります。「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」に基づき、教育・就労分野における課題の解決、結婚問題における差別意識の解消に取り組みます。「えせ同和行為」の排除に向け、市町、法務局、警察等と連携します。 公正な採用選考に関する啓発、同和問題に関する正しい理解・認識の深化、差別意識の解消に努めます。隣保館の活動支援を通して、地域住民の自立支援を図ります。
1. 同和問題への正しい理解と認識の徹底 県民一人ひとりの課題として
同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりがこの問題を自分自身の課題として捉えることが重要です。そのため、同和問題を人権問題の重要な柱として位置づけ、国、市町、関係団体と連携し、あらゆる機会と媒体を活用した啓発活動を推進します。 啓発活動では、同和問題の歴史的背景や現状、そして差別や偏見の具体的な事例などを分かりやすく説明します。 同和問題に対する誤解や偏見を解消し、正しい理解と認識を県民に広めることで、差別のない共生社会の実現を目指します。 特に、福祉の向上や人権啓発の拠点である隣保館において、日常生活に根ざした啓発活動を充実させるよう支援します。 県民の理解と協力を得ながら、同和問題の解決に向けた取り組みを継続的に推進します。
2. えせ同和行為 の排除 誤った認識の是正と不正行為への対応
同和問題を口実とした不当な要求や行為である「えせ同和行為」は、これまでの啓発の効果を覆し、同和問題に対する誤った意識を植え付ける大きな原因となっています。 「えせ同和行為」の横行は、行政や企業などの適正な活動の障害となるため、放置することはできません。 市町、法務局、警察などの関係機関と連携し、「えせ同和行為」への適切な対応について、事業主をはじめ広く県民に周知を図るなど、排除に向けた取り組みを強化します。 「えせ同和行為」に関する正しい知識の普及や、相談窓口の周知、そして具体的な対応方法の提示などを含めた啓発活動を実施します。 これにより、県民一人ひとりが「えせ同和行為」を正しく理解し、適切に対処できるよう支援します。
3. 教育 就労分野における課題解決と差別意識の解消 公正な社会の実現
教育や就労の分野において、同和問題に起因する差別的な扱いなどが依然として存在しています。結婚問題などにおいても、差別意識が根強く残っていることが懸念されています。 これらの問題を解決するため、国などの雇用施策を実施する機関と連携し、公正な採用選考に関する啓発活動や、同和問題に関する正しい理解と認識を深めるための研修会などを計画的に実施します。 公正採用選考人権啓発推進員や事業主を対象とした講演会などを活用し、個人の適性や能力に応じた公正な採用選考を推進します。 これらの取り組みを通して、教育や就労の分野における差別を解消し、誰もが平等に機会を得られる社会の実現を目指します。 隣保館などの地域活動拠点を通じた啓発活動も継続的に行われ、地域住民間の相互理解の促進に努めます。
XI.外国人住民の人権と 人権啓発
外国人に対する偏見・差別意識の解消、文化・習慣の多様性の尊重を目的とした啓発活動、地域での交流促進、相互理解と協力関係の構築を図ります。日常生活における摩擦の解消に努めます。
1. 外国人住民の人権に関する啓発活動 偏見 差別意識の解消
外国人住民の人権に関する理解と認識を促進するため、外国人に対する偏見や差別意識を解消し、多様な文化や習慣を尊重する啓発活動が推進されます。 具体的には、外国人住民が直面する課題や問題点、そして彼らの文化や習慣に関する正しい知識を県民に伝える啓発活動が展開されます。 人種、言語、宗教、文化、習慣の違いに対する理解不足から生じる偏見や差別を解消し、国際化社会にふさわしい人権意識を県民に育むことを目指します。 外国人住民と県民との相互理解を深めるため、地域での交流や相互の文化・習慣を体験できる機会の提供など、具体的な交流プログラムの企画・実施も重要な取り組みとなります。 外国人住民が安心して暮らせるよう、地域社会全体で受け入れる体制づくりを推進します。
2. 相互理解と協力関係の構築 地域社会における共生
外国人住民と県民との相互理解と協力関係の構築を促進するため、地域社会における共生に向けた具体的な取り組みが推進されます。 地域での交流機会の提供や、相互の文化・習慣を体験できるプログラムを通して、県民と外国人住民が互いに理解を深め、良好な関係を築けるよう支援します。 外国人住民が地域社会にスムーズに溶け込み、安心して生活できる環境づくりを目指します。 また、日常生活における摩擦を最小限に抑えるため、県民と外国人住民双方への適切な情報提供や、問題発生時の対応マニュアルの整備なども行われます。 多文化共生社会の実現に向けて、県民一人ひとりが積極的に関わり、協力していくことが重要視されます。
3. 日常生活における摩擦への対応 相互理解に基づく共存
外国人住民の雇用や居住など、日常生活における摩擦が時として発生する現状を踏まえ、その背景にある人種、言語、宗教、文化、習慣の違いへの理解不足からくる偏見や差別意識の解消に努めます。 これらの偏見や差別意識は、県民と在住民外国人との相互理解の増進により改善の方向に向かっていますが、完全な解消には至っていません。 そのため、外国人住民が直面する困難な状況を理解し、適切な支援を提供する体制を整えます。 また、県民に対しては、外国人住民に対する偏見や差別を解消するための教育啓発を継続的に行い、多様な文化を受け入れる寛容な社会の構築を目指します。 相互理解に基づいた共存関係を築くことで、より平和で豊かな地域社会の実現を目指します。
XII.ハンセン病回復者 HIV感染者等の人権
ハンセン病問題解決促進法に基づき、ハンセン病回復者やHIV感染者への偏見・差別意識の解消、社会復帰の促進のための推進体制の充実、関係機関との連携強化に努めます。人権尊重の観点からの理解・認識の促進を目指します。
1. ハンセン病回復者 HIV感染者等への偏見 差別解消 正しい理解と認識の促進
ハンセン病回復者やHIV感染者など、感染症に対する理解不足から偏見や差別意識を持たれる現状があります。 これらの偏見や差別は、人権侵害につながる重大な問題です。 ハンセン病については、らい予防法の廃止により強制隔離政策は終了しましたが、長期間の隔離などにより、家族・親族や地域社会との関係が断絶し、社会復帰が困難な状況にある人が多くいます。 ハンセン病問題解決促進法(ハンセン病問題基本法、2009年4月施行)に基づき、ハンセン病回復者への差別や偏見の解消を更に推進します。 HIV感染者についても、感染症に対する正しい知識と理解を普及することで、偏見や差別を解消し、社会参加を促進します。 これらの取り組みを通じて、ハンセン病回復者やHIV感染者の人権を守るため、正しい理解と認識の促進に努めます。
2. 社会復帰支援 推進体制の充実と関係機関との連携強化
ハンセン病回復者やHIV感染者など、社会復帰が困難な状況にある人々に対して、社会復帰を促進するための推進体制の充実と関係機関との連携強化が図られます。 長期間の隔離生活により、社会とのつながりを失ってしまった人々に対して、社会生活への再適応を支援するための具体的なプログラムや制度が検討・導入されます。 関係機関との連携強化により、医療・福祉・就労支援など、必要な支援を切れ目なく提供できる体制を構築します。 また、社会復帰を妨げる偏見や差別を解消するための啓発活動を行い、社会全体の理解と協力を得ながら、社会復帰支援を推進します。 これらの取り組みを通して、ハンセン病回復者やHIV感染者などが、地域社会の一員として安心して生活できるよう、支援体制の充実を図ります。
3. 感染症への正しい理解 偏見 差別を生む誤解の解消
感染症に対する理解不足が、ハンセン病回復者やHIV感染者などに対する偏見や差別意識を生み出しているという問題意識に基づき、感染症に関する正しい知識の普及啓発に力を入れます。 感染経路や予防方法、そして治療法などの正確な情報を提供することで、誤解や偏見に基づく差別を解消し、人権尊重の意識を高めます。 感染症に関する正しい情報を分かりやすく伝えるための教材やツールを開発し、学校教育や地域社会への普及を推進します。 感染症を持つ人々に対する偏見や差別をなくし、彼らが安心して暮らせる社会環境をつくることが、社会全体の課題であることを県民に訴えます。 これらの啓発活動を通して、感染症への正しい理解を促進し、差別のない共生社会の実現を目指します。
XIII.犯罪被害者の人権保護
犯罪被害者が被る精神的・経済的な被害への支援、捜査・裁判過程における負担軽減、近隣住民やマスコミによる二次被害の防止に努めます。
1. 犯罪被害者の多様な被害と苦悩 直接的被害と間接的被害
犯罪被害者は、生命、身体、財産に対する直接的な被害だけでなく、事件に遭ったことによる精神的ショック、日常生活への支障、医療費の負担、失職・転職などによる経済的困窮など、様々な苦悩を抱えています。 事件後の生活再建は容易ではなく、精神的・経済的な負担は長期に渡り継続される可能性があります。 捜査や裁判の過程においても、精神的負担や時間的負担を感じたり、近隣住民からの無責任な噂話やマスコミ報道による二次被害に苦しむケースも多く見られます。 犯罪被害者の人権を尊重し、被害者支援を強化するため、これらの多様な被害と苦悩を理解することが重要です。 犯罪被害者が安心して生活できるよう、社会全体で支援していくための取り組みが求められます。
2. 被害者支援 多様なニーズへの対応と迅速な支援体制の構築
犯罪被害者の様々なニーズに対応するため、迅速かつ適切な支援体制の構築が不可欠です。 経済的な支援、医療・カウンセリングなどの心のケア、そして法律相談や生活再建のための支援など、多様な支援策が必要となります。 被害者支援を行う関係機関との連携強化を通じて、切れ目のない支援体制を構築し、被害者が安心して相談できる環境を整えます。 また、被害者のプライバシー保護にも配慮し、相談内容の秘密厳守など、信頼関係を構築するための仕組みづくりが重要となります。 警察など捜査機関においても、被害者の心情を理解した丁寧な対応を行うとともに、二次被害を防ぐための対策も強化していきます。 被害者支援を充実させることで、犯罪被害者が安心して生活を再建できるよう、社会全体で支援していく体制を強化します。
3. 社会全体の意識改革 偏見や差別のない共生社会の実現
犯罪被害者に対する偏見や差別をなくし、社会全体で被害者を支える意識を醸成することが重要です。 近隣住民による無責任な噂話や、マスコミによる不適切な報道などは、被害者に深刻な二次被害をもたらす可能性があります。 そのため、犯罪被害者への理解を深めるための啓発活動を行い、社会全体で被害者を支援する意識を高める必要があります。 また、犯罪被害者への支援体制の充実を図るだけでなく、犯罪を未然に防ぐための取り組みも重要です。 犯罪をなくすための社会全体の努力と、被害者の人権を守るための社会全体の意識改革の両方が不可欠です。 犯罪被害者も社会の一員であり、彼らが安心して生活できる社会の構築を目指します。
XIV.インターネット上の人権侵害対策
インターネット上の匿名性を悪用した人権侵害(誹謗中傷、差別助長など)への対策として、プロバイダー等への情報停止・削除要請、個人情報のプライバシーや名誉に関する正しい理解・認識を深めるための啓発活動、学校教育における情報モラル教育の推進などを実施します。
1. インターネット上の人権侵害の現状 匿名性と情報拡散の容易さ
インターネットの匿名性を悪用し、人権を侵害する情報が書き込まれる事例が増加しています。電子掲示板やホームページなどに、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現などが掲載され、個人のプライバシーや名誉を侵害する問題が深刻化しています。 インターネットでは、特定の利用者間の通信だけでなく、不特定多数への情報発信や、不特定多数間の情報交換が容易に行われ、情報拡散のスピードも速いため、一度拡散した情報は容易に削除することができません。 発信者への匿名性があり、情報発信が技術的・心理的に容易であることが、人権侵害を助長する要因となっています。 これらの問題に対し、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解と認識を促進することが喫緊の課題となっています。 インターネットの特性を理解した上で、人権侵害を防ぐための対策が必要不可欠です。
2. 悪質情報への対策 プロバイダー等への対応と自主規制の促進
一般に許される限度を超えて他人の人権を侵害する悪質な情報発信に対しては、憲法の保障する表現の自由にも十分配慮しながら、プロバイダーなどに対して当該情報の停止・削除を申し入れるなど、業界の自主規制を促すことで個別的な対応が図られています。 しかし、個別の対応だけでは限界があり、より効果的な対策が必要とされています。 インターネット利用者やプロバイダーなどが、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解と認識を深めるための啓発活動が推進されます。 これらの啓発活動を通して、インターネット利用における責任や情報モラルの理解を深め、人権侵害を未然に防ぐことを目指します。 インターネット上での情報発信における個人の責任を明確化し、自主規制の強化を図ることで、人権侵害を抑制していく必要があります。
3. 学校教育における情報モラル教育 情報化社会における個人責任の啓発
学校教育においては、情報に関する教科などで、インターネット上の誤った情報や偏った情報、そして情報化が社会にもたらす影響について学び、情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルに関する理解を深めるための教育を推進します。 具体的には、インターネット上での情報発信に潜むリスクや責任、そして情報モラルの重要性などを、生徒に分かりやすく伝える教育プログラムの開発・導入が検討されます。 インターネット利用におけるルールやマナーを学び、責任ある情報発信を行うことができる人材育成を目指します。 また、インターネット上での人権侵害を防ぐためには、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解と認識を、早い段階から身につけることが重要です。 情報化社会を生き抜く上で必要な、情報モラル教育の重要性が改めて強調されます。
XV.教職員の人権教育研修の充実
教職員は人権尊重の精神に基づいた教育を展開できるよう、県教育委員会は参加体験型学習を取り入れた研修会や指導資料の整備を通して教職員研修を充実させます。いじめなどの人権にかかわる課題解決のための学習機会も設けます。
1. 教職員研修の充実 人権問題に関する深い知識と指導力の向上
教職員は、学校教育のあらゆる場面で人権を尊重する意欲と態度を身につけた子どもを育成するという重要な役割を担っています。 そのため、全ての教職員が人権問題についての深い認識と人権教育に関する高い指導力を持つよう、県教育委員会は、参加体験型学習などの効果的な手法を取り入れた研修会の開催や、各種指導資料の整備などを推進します。 研修内容としては、いじめなどの人権に関する今日的な課題の解決に向けた学習機会の充実や、教職員一人ひとりが子どもの人権に配慮した行動や適切な対応ができるための内容が盛り込まれます。 県関係課や市町教育委員会においても、人権問題に関する様々な研修会が実施され、教職員の専門性向上を支援します。 これらの研修を通して、教職員の資質向上を図り、人権尊重の精神に根ざした学校教育の推進を目指します。
2. 実践的な研修内容 今日的な課題への対応と具体的な指導法の習得
研修内容は、いじめなど、今日的な人権問題への対応を重視し、教職員が現場で直面する課題に効果的に対応できるよう、実践的な内容が中心となります。 具体的な指導方法や、生徒への効果的な働きかけ方などを学ぶ機会が提供され、教職員が実践で活用できるスキルを習得することを目指します。 また、研修では、人権問題に関する最新の知見や事例研究を取り入れ、常に最新の状況に対応できるよう、内容のアップデートを図ります。 研修修了後も、継続的なスキルアップを支援するため、各種資料の提供や相談窓口の設置なども検討されます。 研修を通して、教職員が人権尊重の意識をより一層高め、実践的な指導力を身に付けることを目指します。
3. 研修体制の強化 県教育委員会 関係機関との連携
県教育委員会は、研修プログラムや研修教材の充実を図るなど、教職員研修の取り組みを強化します。 県内の関係課や市町教育委員会も連携し、人権問題に関する研修会などを共同で実施することで、より効果的な研修体制の構築を目指します。 研修内容や方法については、定期的に見直しを行い、常に最新のニーズに対応できるよう改善を図ります。 また、研修の効果測定を行い、研修内容の改善に役立て、より質の高い研修を提供できるよう努めます。 県全体で連携した研修体制を構築することで、全ての教職員が人権教育に関する高い専門性を持ち、子どもたちのために最善の教育を提供できるよう支援します。
XVI.県職員の人権意識向上
県職員は公務員としての責務と使命を自覚し、人権問題に対する正しい理解と認識を深め、人権尊重の精神に立った行政施策の推進を図るため、人材育成センター等における研修の充実を図ります。
1. 人権尊重の精神に基づいた行政施策の推進 職員の責務と使命の自覚
県行政に携わる職員は、公務員としての責務と使命を自覚し、人権問題に対する正しい理解と認識を深める必要があります。 そのため、人材育成センターなどでの研修を充実させ、それぞれの職場で人権尊重の精神に基づいた行政施策の推進を図るための研修が提供されます。 研修では、人権に関する基本的な知識や、具体的な人権問題への対応方法などを学びます。 また、県民の立場に立った窓口対応や、日常業務における人権配慮の重要性についても学び、実践的なスキルを習得します。 これらの研修を通して、職員一人ひとりが人権尊重の意識を高め、県民にとってより良い行政サービスを提供できるよう、職員の資質向上を目指します。
2. 研修内容の充実 人権問題への正しい理解と対応力の向上
研修内容は、人権問題に関する正しい理解と、具体的な状況への対応力を高めることを目指します。 研修では、人権に関する法律や条例、判例などの知識、そして具体的なケーススタディを通して、人権問題への対応方法を学びます。 また、ロールプレイングなど、実践的な研修方法を取り入れることで、より効果的な学習を促します。 研修後も、人権問題に関する情報を継続的に提供することで、職員の知識・理解のアップデートを支援します。 さらに、職場における相談体制の整備など、人権問題への対応体制を強化することで、職員が安心して業務に取り組める環境づくりにも力を入れます。
3. 職場の雰囲気づくり 人権尊重の意識の定着
研修に加え、職場全体で人権尊重の意識が定着するような雰囲気づくりも重要です。 そのため、職場におけるハラスメント防止研修の実施や、相談窓口の設置、そして相談しやすい雰囲気づくりのための研修などが行われます。 職員同士が互いに尊重し合い、協力し合える職場環境の醸成に努めます。 また、上司や先輩職員が率先して人権尊重の意識を示すことで、職場全体の人権意識の向上を目指します。 研修と職場環境の両面から人権尊重の意識を醸成することで、県民にとって信頼できる、質の高い行政サービスを提供できる組織を目指します。
XVII.特定職種従事者への人権研修
人権にかかわりの深い特定の職種(公務員、教職員、警察職員等)に対する研修を強化し、研修プログラムや教材の充実を図ります。警察職員は個人の権利や自由を尊重した警察活動を徹底できるよう、警察学校における教育や職場研修を充実させます。
1. 人権に関わりの深い特定職種への研修 公務員 教職員 警察職員等
人権教育・啓発の推進においては、人権に関わりの深い特定の職種従事者に対する研修が不可欠です。 本県では、「人権教育のための国連10年」香川県行動計画に基づき、公務員、教職員、警察職員など、人権に関わりの深い特定の職種に従事する者に対する研修をこれまで実施してきました。 これらの職種は、職務上、人権侵害に関わる可能性が高いため、人権に関する専門的な知識や対応能力の向上が求められます。 研修内容は、人権の概念や重要性に関する基本的な知識から、具体的な人権問題への対応方法、そして最新の法令や判例に関する情報まで、幅広く網羅されています。 研修プログラムや研修教材の充実を図り、研修の質を高めることで、これらの職種従事者の資質向上を図り、人権尊重の意識をより高めていきます。
2. 研修プログラムと教材の充実 実践的スキルと対応能力の向上
研修プログラムの充実のため、最新の事例や法改正を反映した内容に更新し、実践的なスキルを習得できる研修を行います。 ロールプレイングやグループワークなど、参加型の研修方法を取り入れることで、より効果的な学習を促進します。 また、研修教材として、分かりやすく、実践的な内容のテキストや動画などを活用します。 研修後も、継続的な学習を支援するために、関連資料の提供や、専門家による相談窓口の設置などを検討します。 これらの取り組みを通じて、人権侵害への対応能力を高め、人権尊重の意識をより深く定着させることを目指します。
3. 警察職員への専門研修 人権尊重に基づいた警察活動の徹底
警察職員は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するという重要な責務を負っています。 そのため、警察職員が個人の権利や自由を尊重した警察活動を徹底し、職務遂行において人権に配慮した適切な対応ができるよう、警察学校における教育や職場研修の充実が図られます。 特に、女性や少年の被害者などに対する専門的な対応ができるよう、相談業務などに携わる職員の研修が強化されます。 研修では、被害者の特性を理解した上で、適切な対応や支援を行うためのスキルを習得します。 また、職場の教養を充実させ、相談者、被害者、被疑者など全ての人々に対して、適切な対応ができるよう、職員の資質向上に努めます。
