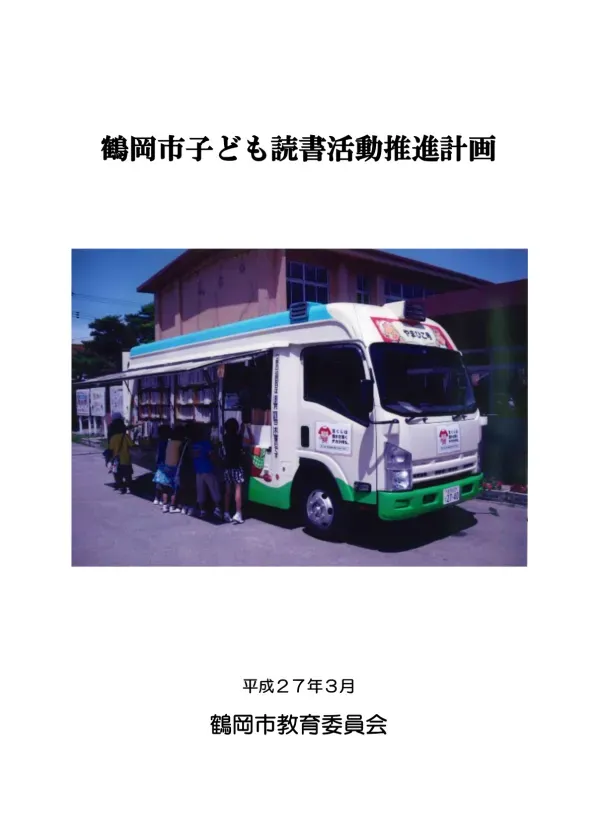
鶴岡市子ども読書活動推進計画
文書情報
| 著者 | 鶴岡市教育委員会 |
| 専攻 | 教育学、図書館情報学 |
| 出版年 | 平成27年(2015年) |
| 場所 | 鶴岡市 |
| 文書タイプ | 行政計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.30 MB |
概要
I.鶴岡市子ども読書活動推進計画の概要
本計画は、鶴岡市における子どもの読書活動推進を目的とし、読み聞かせボランティア育成、学校図書館の充実、図書館サービスの向上などを軸に、家庭、学校、地域社会全体での連携を図ることを目指しています。平成27年、市立図書館開館100周年を機に策定されました。読書習慣の醸成、読書環境整備の充実、そして情報化社会に対応した新たな取り組みが盛り込まれています。特に、小学校では年間一人当たり142.7冊の貸出冊数と高い読書率を維持している一方、中学校では20.8冊に減少するなど、年齢による読書離れの傾向が見られます。この課題に対処するため、朝読書の推進や、中学生・高校生をターゲットにしたヤングアダルトコーナーの設置などが計画されています。市内には6カ所の児童館、子ども家庭支援センター、11カ所の子育て支援センターがあり、それぞれが読書活動に貢献しています。また、自動車文庫による巡回貸出も実施し、地域全体での読書環境の充実を目指します。
1. 計画策定の背景と目的
鶴岡市では、子どもたちの読書活動推進のため、図書館を核とした様々な取り組みを長年行ってきました。絵本の読み聞かせボランティアの育成や、学校図書館への司書配置などを通じて、読書環境の整備に力を入れてきました。平成27年は市立図書館開館100周年にあたり、これを機に『鶴岡市子ども読書活動推進計画』を策定することで、子どもたちの読書活動の更なる活性化を目指しています。この計画は、家庭、学校、図書館、地域社会が連携協力し、子どもたちが生き生きと読書に親しめる環境づくりを総合的に推進することを目的としています。情報化社会において、読書活動は言葉の習得、感性の涵養、表現力や創造力の向上に不可欠であり、人生を豊かに生きるための基盤となることを、この計画は強く認識しています。国や山形県が策定した読書活動推進計画を参考に、鶴岡市独自の取り組みを推進していきます。
2. 計画策定のプロセスと実態調査
本計画の策定にあたっては、「鶴岡市子ども読書活動推進委員会」と「鶴岡市子ども読書推進計画策定庁内会議」を設置し、市立図書館が事務局となって2年間をかけて計画を策定しました。その過程において、平成25年度には小・中・高生とその保護者、未就学児の保護者を対象とした読書アンケートを実施し、鶴岡市の読書活動の実態把握と課題の明確化を行いました。アンケートの結果、特に中学生、高校生の読書率の低さが大きな課題として浮き彫りになりました。中学2年生で53.4%、高校2年生で63.8%の子どもたちが「あまり読まない」「全く読まない」と回答しており、その主な理由は「勉強や塾、部活などで忙しい」ことでした。年齢が上がるにつれ、子どもたちが読書活動から遠ざかる傾向にあることが明らかになりました。この実態調査の結果を踏まえ、計画の具体的な内容が策定されました。
3. 計画の主要な取り組みと目標
本計画では、家庭、学校、図書館、地域社会の連携を重視し、年齢に応じた読書活動を推進するための具体的な施策が盛り込まれています。家庭では、読み聞かせの重要性を啓発し、ボランティア養成講座などを開催して、家庭での読書環境を支援します。保育園・幼稚園では、絵本の読み聞かせや絵本コーナーの設置などを通じて、子どもの読書体験を豊かにします。学校では、学校図書館の機能充実、朝読書の推進、必読図書の選定、授業改善による学校図書館の活用促進などを実施します。図書館では、自動車文庫による巡回貸出、ヤングアダルトコーナーの設置、読み聞かせボランティアの育成・支援、団体貸出による地域への読書環境整備などを計画しています。これらの取り組みを通じて、全ての子どもたちが読書に親しみ、豊かな心を育むことができるよう、読書環境の整備・充実を図ることが計画の主要な目標です。市立図書館開館100周年という節目を迎えるにあたり、この計画が鶴岡市の読書文化の更なる発展に貢献することが期待されます。
II.家庭における読書活動
家庭は子どもが最初に本に触れる場所であり、愛情のこもった読み聞かせが重要です。絵本の選び方や読み聞かせの方法に関するボランティア養成講座を開催し、家庭での読書を支援します。アンケート結果では、中学生の53.4%、高校生の63.8%が「あまり読まない」「全く読まない」と回答しており、勉強や部活動の忙しさが原因として挙げられています。このため、家庭での読書時間の確保と、親子の良好なコミュニケーションを促進するための支援が必要です。
1. 家庭における読書の重要性と現状
家庭は子どもが初めて読書に接する場であり、家族による愛情のこもった読み聞かせは、子どもの読書習慣形成に大きな影響を与えます。読書を通して子どもは幸せを感じ、心安らぐ時間を過ごすことができ、親子の絆も深まります。しかし、アンケート調査の結果、中学2年生の53.4%、高校2年生の63.8%が「あまり読まない」「全く読まない」と回答しており、勉強や塾、部活動の忙しさなどが理由として挙げられています。このことから、家庭における読書時間の確保、そして子どもが自主的に読書に取り組める環境づくりが課題となっています。計画では、家庭での読書環境の整備と充実を図るための支援策を検討する必要があると指摘されています。
2. 家庭向け支援策 読み聞かせと絵本選び
家庭での読書を促進するため、読み聞かせの方法や絵本の選び方などを学ぶボランティア養成講座の開催が計画されています。この講座を通して、多くの保護者の方々に絵本や読み聞かせへの関心を高め、ボランティア活動への参加促進、スキルアップの機会を提供します。また、おはなし会においても、ボランティアが家庭での読み聞かせの方法や意義、重要性について伝えます。図書館では、「おすすめの絵本リスト」を作成し、「おすすめ絵本コーナー」を設置することで、家庭での読み聞かせに適した絵本選びを支援します。これらの取り組みを通じて、保護者が子どもに効果的に読み聞かせを行い、読書習慣を育むためのサポートを提供していきます。さらに、親子のコミュニケーションを深めるための効果的な方法についても検討する必要があると考えられます。
III.保育園 幼稚園における読書活動
保育園・幼稚園は、家庭以外の場所で初めて読書体験をする場所です。絵本の読み聞かせや絵本コーナーの設置、絵本だよりの発行など、各施設が工夫を凝らした取り組みを行っています。平成26年度の子育て推進課調べによると、3歳以上の幼児の9割以上が保育所、幼稚園等に入所・入園しており、未就園児への絵本を使った活動も盛んです。読書推進活動の情報共有を通して、関係機関が連携し、各施設での読書活動を支援していきます。
1. 保育園 幼稚園における読書活動の現状と意義
保育園や幼稚園は、子どもにとって家庭に次ぐ重要な生活の場であり、集団生活の中で読書に親しむ経験を積む場所です。心身の発達に重要な時期である幼児期において、子ども同士や大人との交流を通して、本に親しみ、豊かな感性を育むための環境整備が不可欠です。平成26年度の子育て推進課調べによると、3歳以上の幼児の9割以上が保育所、認可外保育施設、幼稚園等に入所・入園しており、これらの施設における読書活動の重要性は非常に高いと言えます。多くの保育園や幼稚園では、絵本の読み聞かせ、絵本コーナーの設置、絵本だよりの発行など、創意工夫を凝らした様々な取り組みが行われており、未就園児に対しても絵本を使った活動が盛んになっています。これらの活動をさらに発展させ、より効果的な読書活動の推進を目指します。
2. 保育園 幼稚園向け支援策 連携と情報共有
保育園・幼稚園における読書活動を支援するため、図書館や関係機関・団体との連携強化を図ります。具体的には、読書活動に関する情報(年間計画、活動目標、具体的な取り組みなど)を関係機関間で共有し、各施設での活動を支援します。発達段階に応じた読み聞かせ活動や、絵本に触れる機会を増やすための支援も提供します。言葉への感性を育むことを目的とした年間計画や活動目標を共有することで、各施設が効果的な読書活動を展開できるようサポートします。また、必要に応じて、専門家による指導や研修などを実施することで、保育士や幼稚園教諭の読書活動に関するスキル向上を図り、より質の高い読書指導を提供できる体制づくりを目指します。これらの取り組みを通じて、保育園・幼稚園が、子どもたちの読書活動の拠点として更に重要な役割を果たせるよう支援します。
IV.学校における読書活動
学校図書館は、子どもたちが日常的に多くの本と出会える重要な場所です。学校図書館の活用を促進し、調べ学習や授業改善に役立てていきます。小学校では年間一人当たり142.7冊の貸出冊数を維持していますが、中学校では20.8冊に減少しており、年齢が上がるにつれて読書離れが深刻化しています。朝読書や全校一斉読書などの取り組み、必読図書や推薦図書の選定・提示、学校図書館職員の配置などを通して、読書活動の推進を図ります。また、市立図書館との連携を強化し、資料の有効活用を図ります。特に、中学校・高等学校においては、ヤングアダルト世代をターゲットとした図書の充実を図ります。
1. 学校図書館の現状と課題 小学校と中学校 高等学校の読書活動の現状
学校における読書活動の推進は、生涯にわたる読書習慣の形成に大きく貢献します。特に学校図書館は、子どもたちが日常的に読書に親しむ場として重要な役割を担っています。鶴岡市では、小学校では年間一人当たりの貸出冊数が142.7冊と高い水準を維持しており、多くの児童が学校図書館を利用し、読書を楽しんでいる状況です。しかし、中学校になると年間一人当たりの貸出冊数は20.8冊に減少し、高校ではさらに減少傾向にあります。学校図書館の利用率も中学2年生で24.0%、高校2年生で7.5%と低くなっており、年齢が上がるにつれて読書離れが顕著になっています。この原因としては、部活動や学習時間の増加による時間的制約、携帯電話やスマートフォンの利用増加などが挙げられます。この課題に対処するため、全小中学校で授業開始前の「朝読書」や全校一斉読書活動を導入し、読書の機会を積極的に確保する取り組みがなされています。また、学校図書館図書標準冊数の達成率は、小学校で97.3%、中学校で90.9%と高いですが、全ての学校で標準を達成できるよう、さらなる環境整備が必要とされています。
2. 学校図書館の機能強化と読書活動の推進 人的環境と施設整備
学校図書館の機能強化のため、人的環境の整備も重要です。各学校には図書館担当の教員が配置され、12学級以上の学校には司書教諭が配置されていますが、担任業務と図書館運営を両立させる必要があり、負担軽減が課題となっています。鶴岡市では、昭和41年から学校図書館職員を配置するなど、全国に先駆けて人的環境整備を進めてきました。今後、学校図書館が子どものニーズに応じた読書センター、学習・情報センター、そして心の居場所としての機能を果たせるよう、環境整備と活用の促進に努めます。具体的には、地域ボランティアや保護者ボランティア、教員による読み聞かせ、必読図書や推薦図書の選定・提示、全校一斉読書や読み聞かせの充実、図書資料の整備充実(特に中学校・高等学校ではヤングアダルト世代向け図書の充実)、地域資料の整備充実などが計画されています。市立図書館との連携強化も図り、調べ学習のための団体貸出やレファレンスサービスなどを活用していきます。
3. 学校における読書活動の連携強化 学校 図書館 地域との連携
学校における読書活動の円滑な実施のため、学校、市立図書館、地域、保護者ボランティア等の連携を促進し、必要な体制整備に努めます。授業においては、担任、司書教諭、図書館主任、学校図書館職員が連携し、学校図書館や市立図書館の資料を有効活用した授業改善に取り組みます。各教科で学校図書館の活用を促進し、思考力・判断力・表現力を育む言語活動の充実を図ります。各学校の特色を生かしながら、読書に親しむ多様な活動を展開し、子どもの自主的・自発的な読書活動の推進を目指します。 また、鶴岡市の歴史や教育を伝える資料として、『親子で楽しむ庄内論語』を市内小学校1年生に配布し、学校図書館にも整備することで、地域に根ざした読書活動の推進を図ります。これらの取り組みを通じて、学校が子どもたちの読書活動における中心的な役割を果たせるよう、支援体制を強化していきます。
V.図書館 地域における読書活動
市立図書館は、読書活動の核となる施設です。読み聞かせボランティアの養成、自動車文庫による巡回貸出、ヤングアダルトコーナーの設置など、利用しやすい環境整備を進めます。アンケート結果では、「本を読むのが好き」と答えた人は72.6%いる一方、「市立図書館にほとんど行かない・全く行かない」と答えた人は73.1%と、図書館利用率の低さが課題となっています。地域住民やボランティアとの連携を強化し、公民館やコミュニティセンターなどへの団体貸出による読書環境の整備を進めます。
1. 市立図書館の現状と課題 図書館利用率の低さと課題
市立図書館は、読書活動推進の中核を担う施設です。しかし、アンケート調査によると、「本を読むのが好き」と回答した人は72.6%である一方、「市立図書館にほとんど行かない」「全く行かない」と回答した人は73.1%にも上り、図書館の利用率が低いことが課題として挙げられています。特に、年齢が高くなるにつれて図書館への来館率が低くなる傾向が見られます。この現状を踏まえ、図書館の魅力を再認識させ、より利用しやすい環境整備を進める必要があります。情報化社会の進展に伴い、読書の方法も多様化しており、図書館は単なる本の貸出場所ではなく、課題解決の支援や、本を通して人と人とのつながりを創出する場としての役割を担うことが重要になります。図書館の機能を充実させ、魅力的なサービスを提供することで、市民の図書館利用率向上を目指します。
2. 図書館のサービス向上策 多様なサービスの提供と地域連携
図書館サービスの向上策として、自動車文庫による保育園・幼稚園・学校・コミュニティ施設への巡回貸出、中学生・高校生をターゲットにしたヤングアダルトコーナーの設置、読み聞かせボランティアの養成と支援などが挙げられます。自動車文庫は、図書貸出サービスの充実を図り、地域住民へのアクセス向上に貢献します。ヤングアダルトコーナーは、中学生・高校生が興味を持つような魅力的な書籍の提供を通じて、読書への関心を高めます。読み聞かせボランティアの育成・支援は、図書館と地域団体との連携を強化し、読書活動の推進を促進します。さらに、図書館本館では年間を通してテーマに沿った関係書籍の展示を行い、読書への関心を高める取り組みを行います。これらの多様なサービスを通じて、市立図書館が地域住民にとってより身近で魅力的な存在となるよう努めます。
3. 地域との連携 コミュニティセンター等との連携強化
図書館は、地域全体での読書活動推進のため、他の施設との連携を強化していく必要があります。コミュニティセンター、地域活動センター、地区公民館などでは、一部施設を除き図書が配置されておらず、図書館までの距離が読書活動の障壁となっている現状があります。そこで、これらの施設との連携を深め、図書室や図書コーナーでの読み聞かせやおはなし会を積極的に告知し、子どもたちが本に触れる機会を増やします。パンフレットやチラシなどを活用し、図書、読書、読み聞かせに関する情報を提供します。また、地域のコミュニティセンターなどにまとまった数の本を貸し出す団体貸出制度などを活用し、地域における子どもの読書活動を積極的に推進します。これらの連携強化を通して、地域全体で読書を促進する環境づくりを目指します。
