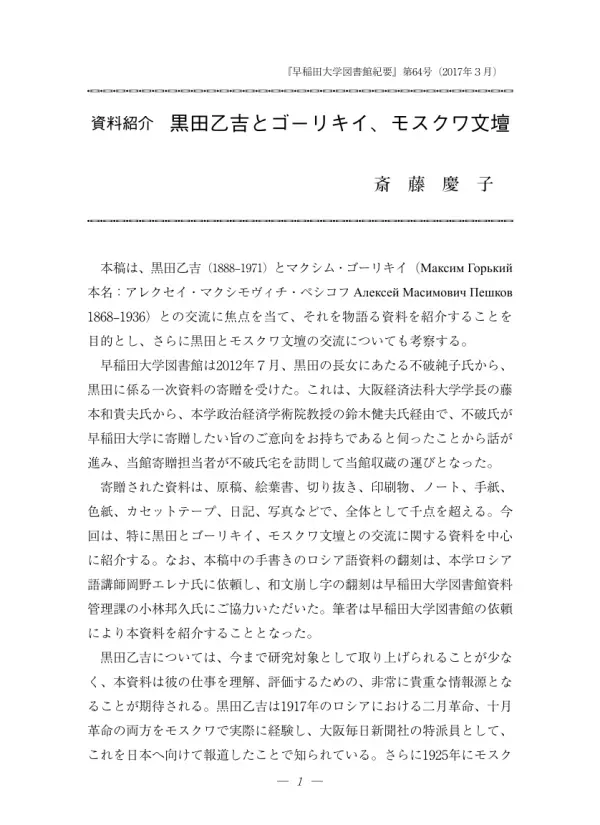
黒田乙吉とモスクワ文壇:ゴーリキイとの交流を中心に
文書情報
| 著者 | 筆者 |
| 学校 | 早稲田大学図書館 |
| subject/major | ロシア文学、ジャーナリズム史 |
| 文書タイプ | 資料紹介 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.65 MB |
概要
I.早稲田大学図書館所蔵 黒田乙吉関連資料の紹介
早稲田大学図書館は2012年、黒田乙吉の長女である不破純子氏から、黒田乙吉に関する貴重な一次資料を寄贈された。これらの資料は、原稿、絵葉書、手紙、写真など千点以上にも及び、特に黒田乙吉とマクシム・ゴーリキイ、そしてモスクワ文壇との交流に関する資料が中心となっている。黒田乙吉は1917年のロシア革命をモスクワで体験した大阪毎日新聞特派員であり、その経験に基づいた著作『悩める露西亜』(1920)、『ソヴィエト塑像』(1948)を残している。本資料は、これまで研究が進んでこなかった黒田乙吉の活動を知る上で非常に貴重な情報源となる。
1. 資料の概要と寄贈経緯
早稲田大学図書館は2012年7月、黒田乙吉の長女である不破純子氏から、黒田乙吉に関する膨大な一次資料の寄贈を受けました。資料は原稿、絵葉書、切り抜き、印刷物、ノート、手紙、色紙、カセットテープ、日記、写真など多岐に渡り、総数は千点を超えます。寄贈に至った経緯は、大阪経済法科大学学長の藤本和貴夫氏から、早稲田大学政治経済学術院教授の鈴木健夫氏を通じて、不破純子氏が早稲田大学への寄贈を希望しているとの連絡があったことに端を発しています。その後、早稲田大学図書館の担当者が不破氏宅を訪問し、資料の受け入れが行われました。これらの資料は、これまで研究対象として取り上げられることの少なかった黒田乙吉の仕事内容を理解・評価するための、極めて貴重な情報源となると期待されています。黒田乙吉は1917年のロシア二月革命と十月革命をモスクワで体験し、大阪毎日新聞社の特派員として活動していました。本稿では、特に黒田乙吉とマクシム・ゴーリキイ、モスクワ文壇との交流に関する資料を中心に紹介していきます。本稿作成にあたり、ロシア語資料の翻刻は本学ロシア語講師岡野エレナ氏に、和文崩し字の翻刻は早稲田大学図書館資料管理課の小林邦久氏にご協力をいただきました。
2. 黒田乙吉の経歴と先行研究
黒田乙吉(1888-1971)は、大阪毎日新聞のモスクワ特派員としてロシア革命を体験した人物です。彼のロシアでの経験は、著書『悩める露西亜』(1920)と『ソヴィエト塑像』(1948)に結実しています。黒田乙吉に関する先行研究としては、黒田とロシアとの関わりを中心にまとめた菊地昌典による短い伝記「黒田乙吉翁小伝」(1974)があります。また、小山内道子は「『月刊ロシヤ』(1935~1944)を渉猟して──雑誌の起源、そして米川文子、マトヴェーエフ、黒田乙吉を読む──」(2010)、「『日本最初のモスクワ特派員』・黒田乙吉──明治末期日本のロシア文化環境からハルビンへ──」(2013)という2本の論考を発表しています。しかしながら、これらの研究は主に、黒田がモスクワを訪れる前に6年間滞在したハルビンでの生活、そして二度目の訪ソからの帰国後の時期に関するものです。最近では、太田丈太郎の著書『「ロシア・モダニズム」を生きる─日本とロシア、コトバとヒトのネットワーク』(2014)でも黒田乙吉について触れられています。本稿で紹介する資料は、これらの先行研究では扱われていない新たな知見を提供すると期待されています。特に、黒田乙吉とマクシム・ゴーリキイ、そしてモスクワ文壇との交流に関する一次資料は、彼の生涯と活動をより深く理解するために不可欠なものです。
3. 本稿の構成と目的
本稿は、黒田乙吉とマクシム・ゴーリキイとの交流に焦点を当て、それを物語る資料を紹介することを目的としています。さらに、黒田乙吉とモスクワ文壇の交流についても考察します。前半では、モスクワ文壇との関わりを示す断片的な資料を、事実関係を補足しながら紹介し、後半では、ゴーリキイに関する原稿を掲載情報とともに列挙します。最後に、未刊行と思われる黒田乙吉の本学における口頭発表原稿「人間ゴーリキイを語る」(和文)を抜粋して紹介し、本稿を締めくくります。本稿で紹介する資料の翻刻と和訳は末尾に掲載しています。 本稿では、先行研究において触れられてこなかった資料についても紹介することで、黒田乙吉の研究に新たな知見を提供することを目指しています。 黒田乙吉の活動は、これまで十分に研究されておらず、今回寄贈された資料は、彼の仕事内容をより深く理解するための貴重な情報源となるでしょう。特に、黒田乙吉とロシアの文化人との交流に関する資料は、その貴重な側面を明らかにする上で重要な役割を果たします。
II.黒田乙吉とモスクワ文壇の交流
黒田乙吉はモスクワ特派員として二度滞在(1916年、1925-1927年)し、モスクワ文壇の人々と親交を深めた。二度目の滞在中には、フセヴォロド・イワノフ(ゴーリキイ門下)ら多くの作家と交流し、中でもボリス・ピリニャークとの親交は深かった。 特に「ゲルツェンの家」というレストランは、作家たちとの交流の場として重要な役割を果たした。これらの交流は、黒田乙吉の著作や、今回寄贈された寄せ書き、手紙などの資料から確認できる。重要な人物としては、フセヴォロド・イワノフ、ボリス・ピリニャーク、オリガ・クニッペル(チェーホフ未亡人)、アレクセイ・スヴィルスキー、パーヴェル・ニゾヴォイなどが挙げられる。
1. 黒田乙吉とモスクワ文壇との最初の接点 ゴーリキイへの憧憬
黒田乙吉がモスクワ文壇と本格的に交流を持つようになる以前、1916年(大正5年)6月からの最初のモスクワ滞在では、ゴーリキイとの面会を期待して文芸協会に出入りしていました(黒田、1920、附録p.77)。しかし、この時点ではゴーリキイとの直接の交流は実現しませんでした。それでも、ゴーリキイに会うという強い目的意識が、黒田をモスクワ文壇という世界へと導いた重要な契機となりました。 この初期のモスクワ滞在経験は、後に彼とモスクワ文壇との深い交流関係を築くための重要な土台となり、黒田のロシア文学への関心の深まりを象徴する出来事でした。 新聞記者としての活動を通じて、黒田はゴーリキイという偉大な作家への憧れを募らせ、その憧憬が彼をロシア、そしてモスクワ文壇へと引き寄せたのです。この初期の経験は、後の彼のモスクワ文壇との交流、そしてゴーリキイとの交流へと繋がる重要な一歩だったと言えるでしょう。
2. 二度目のモスクワ滞在と文壇との親交 ゲルツェンの家と寄せ書き
黒田乙吉がモスクワ文壇の人々と個人的な交流を深めるようになったのは、大阪毎日新聞のモスクワ特派員として二度目の滞在期間(1925-1927)中でした。1925年7月にモスクワに到着した黒田は、「広くそして深くその国の人々と交らねば」という新聞記者の使命感(黒田、1954、p.59)を持ちながらも、ソ連の政治情勢から政府要人との交流は困難でした。しかし、「文化関係」の人々、つまり文壇、美術界、演劇関係者とは比較的自由に交流することができました。 特に「ゲルツェンの家」というレストランが重要な役割を果たしました。そこで黒田は多くの作家と出会い、交流を深めました。 この「ゲルツェンの家」で出会った人々を記録した寄せ書き(資料1、図版1)は、黒田自身も発表済みですが(黒田、1948、p.50)、今回寄贈された資料に原本が含まれています。この寄せ書きには、ピリニャーク、ブダンツェフ、キリロフ、ノビコフ=プリボイ、リーヂン、リーヂナなど、黒田が後に作品の中で取り上げたり、手紙を交わす仲になった作家たちの名前が記されています。 この寄せ書きは、黒田とモスクワ文壇の作家たちとの緊密な関係性を示す重要な資料と言えるでしょう。
3. 主要な文壇人との交流 イワノフ ピリニャーク そしてクニッペル
モスクワで黒田乙吉が最初に訪れた作家は、フセヴォロド・イワノフでした。彼は「セラピオン兄弟」というグループの代表的な作家であり、ゴーリキイ門下でもありました。イワノフは後に黒田にゴーリキイとの面会を仲介し、紹介状を用意してくれました。イワノフのポートレートと思われる絵(図版2)も資料として残されています。 イワノフに次いで黒田に強い印象を与えたのはボリス・ピリニャークでした。「ソヴエト文壇人との交友録」(黒田、1947)から、黒田がピリニャーク宅に招かれたり、行動を共にした様子が分かります。ピリニャークは黒田の「知友録」に感動的な詩的献辞を残しており(資料2、図版3)、二人の親しい交流を示しています。 さらに、黒田はチェーホフの未亡人でモスクワ芸術座の看板女優であったオリガ・クニッペルとも親交があったことが、ピリニャークとの座談会記事(ピリニャークら、1932、p.103)や黒田自身の著作『悩める露西亜』から分かります。これらの交流は、黒田のモスクワ文壇における人脈の広さと深さを物語っています。 これらの交流は、単なる社交的な繋がりではなく、黒田のロシア文学、そしてソ連社会に対する深い理解を培う上で重要な役割を果たしたと考えられます。
4. 留別の スキヤキ会 と多様な交流 多国籍 多様な分野の交わり
1927年11月11日もしくは12日、黒田乙吉はモスクワの自宅で「留別の『スキヤキ会』」を開催し、多くの友人や知人を招きました(黒田、1947、p.272,276)。この宴には、アレクセイ・スヴィルスキー夫妻やパーヴェル・ニゾヴォイなどロシア人作家だけでなく、米川(おそらく正夫)ら日本人、フランス人など、多国籍で様々な分野の人々が集まりました。 「知友録」(資料4)には、この宴に参加した人々の署名が残されており、その多様性が見て取れます(図版5)。 スヴィルスキーとは十分な時間を共有できなかったものの、ニゾヴォイとは日本文学やロシア文学について熱心に語り合ったことが記録されています(資料4-2)。 この「スキヤキ会」は、黒田乙吉の広範な人脈と、多様な文化交流の場としての彼の存在を示す象徴的な出来事でした。 この宴の賑やかさは、黒田乙吉の人間性と、彼を取り巻く人々の温かさを感じさせるものであり、単なる送別会以上の意味を持っていたと考えられます。
III.黒田乙吉とマクシム ゴーリキイの交流
黒田乙吉のモスクワ滞在における最大の目標はマクシム・ゴーリキイとの面会であった。当初は実現しなかったものの、ゴーリキイへの強い憧憬が黒田乙吉をモスクワ文壇へと導いた。帰国後もゴーリキイと手紙を交わしており、その手紙は今回寄贈された資料に含まれている。黒田乙吉は、ゴーリキイ生誕百年祭(1968年)に関連するイベントにも参加し、講演「人間ゴーリキイを語る」を行っている。この講演原稿もまた、貴重な資料として残されている。 ゴーリキイとの交流は、黒田乙吉の人生において重要な位置を占め、彼のロシア研究の原点ともいえる。
1. ゴーリキイとの交流の目標と最初のモスクワ滞在
黒田乙吉のモスクワ滞在の目的は、当初からゴーリキイとの面会に絞られていました。そして、このゴーリキイとの交流は、黒田の人生においても極めて重要な位置を占めることになります。1916年(大正5年)6月からの一度目のモスクワ滞在では、「少なからぬ期待を以て文芸協会にも出入りしたが」(黒田、1920、附録p.77)ゴーリキイに会うことは叶いませんでした。しかし、このゴーリキイへの強い憧憬こそが、黒田をモスクワ文壇へと導き、後の彼とゴーリキイ、そしてモスクワ文壇との深いつながりを生み出す出発点となりました。ゴーリキイという目標の存在が、黒田のロシアにおける活動を大きく方向づけたと言えるでしょう。この最初のモスクワ滞在は、単なる失敗ではなく、黒田のロシア文学、そしてソ連社会への理解を深めるための貴重な経験であったと捉えることができます。
2. 二度目のモスクワ滞在とゴーリキイとの邂逅
二度目のモスクワ滞在(1925-1927)において、黒田はついにゴーリキイと会うことができました。 この出会いは、新聞記者としての活動において、ソ連政府関係者との接触が難しかった中で、文化界の人々との交流が比較的自由にできた状況下で実現しました。黒田自身は「一般市民はもち論のこと、我々を疫病神のように扱った」(黒田、1954、p.59)と記しており、ソ連社会の閉鎖性の中で、文化人との交流がいかに貴重であったかを物語っています。 『東京日日新聞』1927年12月の「イタリーにゴーリキイを訪ふ」という特集記事(掲載情報及び写真部分は切り取られているが、本稿のための調査により掲載日が特定された)は、黒田とゴーリキイの出会いを詳細に記述した貴重な記録です。記事には、ゴーリキイ宅へ向かう道中の様子から、家並み、内装に至るまでが細かく描写されており、二人の出会いの日の15時から24時まで、そして翌日も遅くまで話し合ったことが記されています。この出会いは、単なる一過性の出来事ではなく、黒田の生涯に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
3. 帰国後の交流 手紙のやり取りとゴーリキイ生誕百年祭での活動
帰国後も、黒田はゴーリキイと手紙を交わしました。ゴーリキイからの手紙が二通、黒田からゴーリキイ宛ての手紙が一通、寄贈資料に収められています(資料6、7、8)。ゴーリキイからの手紙については、黒田自身が『ソヴィエト塑像』の中で全文翻訳と注釈を掲載しています(黒田、1948、pp.29-39)。これらの手紙は、二人の交流の深さ、そして黒田のゴーリキイに対する敬意を示す重要な資料です。 さらに、1968年のゴーリキイ生誕百年祭では、黒田は講演「人間ゴーリキイを語る」を行いました(早稲田大学大隈講堂)。この講演では、それまでの著作には見られなかった、黒田自身のロシアへの憧憬やゴーリキイへの個人的な感情が述べられています。 この講演原稿は、黒田がゴーリキイとの交流を通して何を学び、何を考え、どのように自身の活動に繋げてきたのかを理解する上で、極めて重要な資料となります。また、この講演会には、ゴーリキイ研究者のボリス・ビャーリクも参加していました(『日本とソビエト』1968年6月5日)。
IV.関連研究と資料の現状
黒田乙吉に関する先行研究としては、菊地昌典による「黒田乙吉翁小伝」や小山内道子の論考などがあるが、今回寄贈された資料は、先行研究では触れられてこなかった新たな情報を提供する。これらの資料は、黒田乙吉のロシア文学研究、ソ連理解、そして日本とロシアの文化交流の歴史を解明する上で、極めて重要な役割を果たすものである。
1. 先行研究の現状と課題
黒田乙吉に関する先行研究としては、黒田とロシアとの関わりに焦点を当てた菊地昌典の「黒田乙吉翁小伝」(1974)や、小山内道子の2本の論考(2010年、2013年)などが挙げられます。小山内道子の論考では、黒田乙吉がモスクワを訪れる前に6年間滞在したハルビンでの生活や、二度目の訪ソからの帰国後の時期が主に扱われています。また、近年では太田丈太郎の著書『「ロシア・モダニズム」を生きる─日本とロシア、コトバとヒトのネットワーク』(2014)でも黒田乙吉について触れられています。しかし、これらの研究では、今回寄贈された資料に含まれるような、黒田乙吉とゴーリキイ、モスクワ文壇との交流に関する詳細な一次資料は扱われていませんでした。そのため、今回紹介する資料は、既存の研究では明らかにされていなかった黒田乙吉の活動の一端を明らかにする上で非常に貴重な存在と言えるでしょう。特に、黒田乙吉の私的な側面や、ロシア文学研究における彼の真意を理解する上で、これらの資料は重要な役割を果たします。
2. 今回寄贈された資料の重要性と可能性
今回早稲田大学図書館に寄贈された資料は、黒田乙吉に関する一次資料であり、その数は千点を超えます。これには、原稿、絵葉書、切り抜き、印刷物、ノート、手紙、色紙、カセットテープ、日記、写真などが含まれています。これらの資料は、黒田乙吉の仕事内容を理解し、評価するための非常に貴重な情報源となることが期待されています。 特に、黒田乙吉とマクシム・ゴーリキイ、モスクワ文壇との交流に関する資料は、これまで研究が進んでこなかった部分であり、新たな知見を提供するものと期待されています。 これらの資料を詳細に分析することで、黒田乙吉のロシアにおける活動の実態、彼の人間関係、そして彼のロシア文学研究の深まりなどを、より多角的に解明することが可能になるでしょう。 本稿では、これらの資料の一部を紹介することで、黒田乙吉研究における新たな視点を提供することを目指しています。特に、先行研究では触れられてこなかった資料についても紹介することで、今後の研究の発展に貢献したいと考えています。
