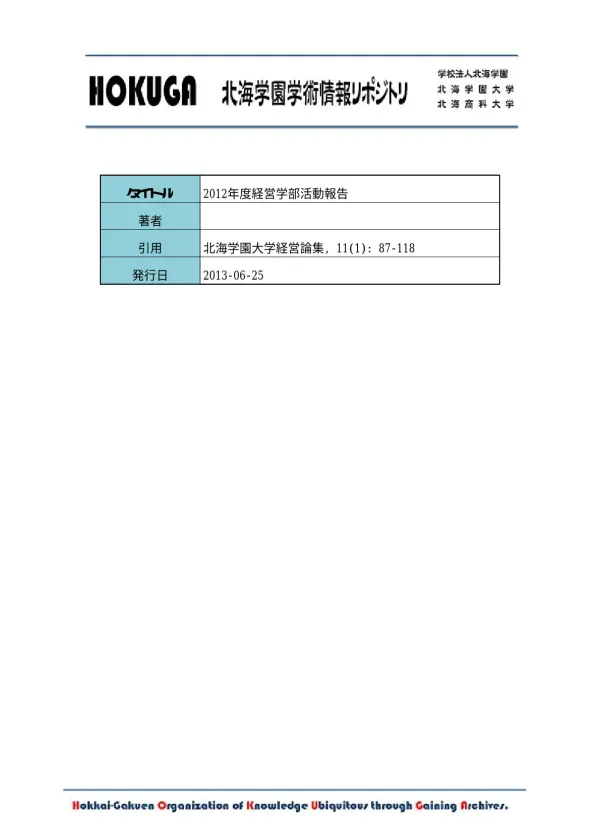
2012年度経営学部活動報告:魅力再発見
文書情報
| 著者 | 経営学部 |
| 学校 | 北海道大学経営学部 (推定) |
| 専攻 | 経営学 |
| 文書タイプ | 活動報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.42 MB |
概要
I.北海道経済産業局特別講義 地域産業政策と中小企業
北海道の地域産業政策をテーマとした特別講義では、急速に変化する経済環境下における地域産業の課題と対応策、国の支援メカニズムを具体例を交えて解説。北海道中小企業家同友会と連携し、中小企業経営者の経験に基づく実践的な経営ノウハウを学ぶ機会を提供。新製品開発やサービス設計における工夫、経営戦略、イノベーションを学ぶことを目指す。(講師:大平義隆教授他、北海道オフィスマシン株式会社神野裕三社長など)
1. 北海道の地域産業政策 現状と課題
この講義では、北海道の豊かな道民生活を支える地域経済の現状と課題を分析します。急速に変化する経済環境の中で、道内の各地域、産業、企業が置かれている状況と、求められる対応について検討します。具体的には、各地域や産業が直面する課題、競争力強化のための戦略、持続可能な発展のための取り組みなどが議論されます。また、国による地域産業イノベーション支援の認識やメカニズムについても、現場の具体例を交えながら解説することで、学生の理解を深めます。北海道経済の現状、課題、そして将来展望といったキーワードを軸に、地域産業政策の重要性と複雑さを理解する事がこのセクションの目的です。講義を通して、学生は北海道の地域経済を多角的に理解し、地域活性化に貢献できる人材育成を目指します。
2. 北海道中小企業家同友会との連携 実践的経営ノウハウの習得
北海道中小企業家同友会で活躍する経営者を講師に招き、実践的な経営ノウハウを学びます。講義では、成功事例だけでなく、失敗から得られた教訓や工夫、蓄積された知識、創造的なアイデアなど、多様な視点からの経営論を展開します。学生は、経営者の意思決定プロセス、問題解決能力、組織運営、イノベーション創出などを具体的に学ぶことができます。特に、新製品やサービスの開発における工夫や設計プロセスは、実践的な経営学の理解に繋がる重要な要素となります。講義を通して、学生は経営学の理論と実践を結びつけ、現実のビジネスシーンにおける課題解決能力を養います。中小企業の経営戦略、起業家の視点、そして持続可能な経営といったキーワードが、このセクションの学習内容を的確に表しています。
3. 講師紹介 多様な業界からの専門家
この特別講義では、多様な業界の第一線で活躍する専門家を講師として招へいしています。具体的には、北海道オフィスマシン株式会社代表取締役社長の神野裕三氏、株式会社プリプレス・センター代表取締役の藤田靖氏、株式会社白石ゴム製作所代表取締役の千葉武雄氏、環境開発工業株式会社代表取締役の山田太郎氏、株式会社レイジックス代表取締役社長の敬禮匡氏など、それぞれの分野で豊富な経験を持つ方々が、自身の経験や知見に基づいた講義を行います。それぞれの講師の専門性や経験は、学生の学びを多角的に深める上で重要な役割を果たしています。これらの講師陣の専門知識、実務経験は、学生が将来、ビジネスパーソンとして活躍していく上で貴重な財産となるでしょう。北海道におけるビジネスシーンの多様性と、それぞれの業界で活躍する専門家の知見を学生が吸収できる点が、このセクションの大きな特徴です。
II.特別講義 地域金融と信用組合の役割
地域金融機関、特に信用組合の制度と役割に焦点を当てた特別講義。札幌中央信用組合をはじめとした関係者による講義を通して、地域経済における信用組合の重要性を理解。北海道の中小企業の現状や経済動向、金融行政についても学ぶ。(講師:野村功氏、松本柾人氏、大島政實氏、川島俊通氏、赤堀吉則氏、天満屋敷誓氏、千葉武雄氏、一関脩氏)
1. 地域金融と信用組合 これまでになかった学びの機会
この特別講義は、日本の大学では類を見ない、地域経営者にとって極めて重要な外部環境である地域金融機関を深く学ぶ機会を提供します。特に、信用組合の制度と役割に焦点を当て、その実態や重要性を理解することを目指します。全国信用組合中央協会の協力を得て、札幌中央信用組合の経営者や管理者などを講師に迎え、実践的な講義を行います。学生たちは、地域経済における金融機関の役割、中小企業への支援、地域社会への貢献などを多角的に理解することができます。地域経済の活性化に貢献できる人材育成を目的とし、地域金融の専門家による講義を通して、学生は実践的な知識とスキルを習得します。これまで学ぶ機会の少なかった地域金融の専門性を深く理解することで、地域経済への貢献を視野に入れたキャリアプランを構築することが期待されます。
2. 信用組合の制度 役割と北海道経済への影響
講義では、信用組合の歴史、その役割、地域経済への貢献について体系的に学びます。札幌中央信用組合理事長である松本柾人氏をはじめ、全国信用組合中央協会常勤顧問の野村功氏など、信用組合の第一線で活躍する専門家から直接指導を受けることができます。さらに、北海道中小企業団体中央会専務理事の大島政實氏による北海道中小企業の現状分析、北海道財務局財務部理財部長川島俊通氏による経済動向と金融行政の解説、日本銀行札幌支店課長赤堀吉則氏による北海道の経済と金融の現状分析など、多角的な視点からの講義を通して、信用組合の地域経済における位置づけを深く理解します。これらの専門家による講義を通して、学生は地域金融の専門知識を深め、北海道経済の現状と課題を多角的に分析する能力を養うことができます。特に、中小企業支援における信用組合の役割は、地域経済を支える重要な要素として深く理解する必要があります。
3. 実践事例と多様な視点 現場からの学び
講義では、札幌中央信用組合西野支店支店長である天満屋敷誓氏による現場からの生の声、株式会社白石ゴム製作所社長千葉武雄氏による顧客目線からの信用組合の評価、そして北海道中小企業家同友会理事の一関脩氏(株式会社北海道フキ社長)による信用組合による中小企業支援の事例紹介など、多様な視点からの実践的な講義が展開されます。これらの多様な視点を取り入れることで、学生は信用組合の役割や重要性をより深く理解することができます。具体的には、顧客のニーズに応えるための信用組合の取り組み、中小企業の成長を支援する具体的な方法、地域経済の活性化に向けた戦略など、実践的な知識を学ぶことができます。これらの講義を通して、学生は地域金融機関の業務内容、顧客との関係性、そして地域社会への貢献などを多角的に理解し、将来のキャリアプランに活かすことができます。
III.金融 証券講座と特別講演会 実践的なビジネススキル習得
北海道銀行、野村證券との連携による金融・証券に関する公開講座と、グローバルなビジネスシーンで活躍する講師陣による特別講演会を開催。グローバル化、高度情報化に対応した実践的な英語力とビジネススキルを育成。アジア観光ビジネスや、プレゼンテーション能力向上をテーマに、実践的な講義や交流会を実施。(講師:ナザレチャク博士他)
1. 北海道銀行 野村證券との連携 金融 証券に関する実践的学習
2012年度も、前年度に引き続き、北海道銀行と野村證券との連携により、金融・証券に関する4コマの公開講座を開講しました。学生と一般の方々を対象としたこの講座は、実践的な知識とスキルを習得する場として提供され、開かれた知的な刺激の場として機能しています。講座の内容は、金融市場の動向、投資戦略、リスク管理、証券取引の基礎など、幅広い分野をカバーし、学生たちは専門家からの指導を受けることで、実践的な知識を身につけることができます。北海道銀行と野村證券という、金融業界を代表する企業との連携は、学生にとって貴重な学習機会を提供し、実践的なスキルを習得することに繋がります。これらの企業との連携を通して、学生は業界の最新動向を理解し、就職活動にも役立つ実践的な知識とスキルを身につけることが期待できます。
2. 特別講演会 グローバルなビジネスシーンを学ぶ機会
経営学部では、総合実践英語の企画として、2012年度に4回の特別講演会を開催しました。国内外のビジネスシーンで活躍する講師を招き、それぞれの経験や仕事内容などを、メールやビデオなどを活用しながら紹介しました。特に、第1回のナザレチャク博士による講演会は全編英語で行われ、学生にとって英語力の向上と同時に、国際的なビジネスの理解を深める機会となりました。講演会後には、講師を交えた学生との交流会も実施され、活発な意見交換が行われました。延べ200名ほどの学生が参加し、活気のある講演会となりました。講演会のテーマは、アジア観光ビジネスの将来展望など、グローバルな視点を取り入れた内容となっており、学生たちは国際的なビジネス感覚を養うことができました。ビジネス英語、グローバル化、国際ビジネスといったキーワードが、このセクションの学習内容を象徴しています。
3. 特別講演会の内容 多様なビジネス分野からの学び
4回の特別講演会では、それぞれ異なるビジネス分野をテーマに、実践的な内容が展開されました。例えば、第1回は「世界から人を呼び込め~アジア観光ビジネスのこれから~」をテーマに、アジアにおける観光ビジネスの現状と将来展望について深く掘り下げました。講演では、グローバル化、高度情報化、産業構造変化といった社会情勢の変化が、求められる人材像にも大きな影響を与えていることが強調されました。これらの講演会を通して、学生は多様なビジネス分野の現状と課題、将来展望などを理解し、自身のキャリアプランを考える上で貴重な経験を得ることができました。講演会における活発な質疑応答や講師との交流は、学生の学習意欲を高める上で大きな効果がありました。多様なビジネスモデル、国際的な競争環境、そして人材育成といったキーワードが、このセクションの重要な論点となります。
IV.企業研修 実践的な企業体験とキャリア形成支援
単位認定科目「企業研修」では、学生が企業・団体で実地研修を行い、企業社会で求められる能力を実体験。大学教育と連携し、キャリア形成を支援。保険加入(学生負担210円、補償額1億円)と事前指導により安全性を確保。
1. 企業研修の概要 実践的学習を通じたキャリア形成支援
本学部の「企業研修」は、単位認定科目として位置づけられ、学生が実際の企業や団体で実習や研修を行うプログラムです。学生は、企業における実地研修を通して、現実の企業社会で求められる人材像を肌で感じ、大学教育で学んだ知識を実践的に活用する機会を得ます。この研修を通して、学生は実践的なビジネススキルを習得し、より効果的な学習を実現します。グローバル化や高度情報化が進む現代社会において、実践的な経験は学生のキャリア形成に不可欠です。企業研修は、こうしたニーズに応えるために設計されており、学生の成長とキャリア形成を強力に支援します。企業研修は、単なる就業体験ではなく、大学教育と密接に連携した、高度な教育プログラムとして位置付けられています。
2. 企業研修の目的 大学教育との連携による教育効果の最大化
企業研修の主要な目的は、学生が現実の企業社会で求められる人材像を実体験を通して理解し、大学教育と実践を結びつけることで、教育効果を最大限に高めることにあります。学生は、企業での研修を通して、理論と実践のギャップを認識し、自身の成長すべき点を明確に把握することができます。この研修は、学生のキャリア形成を支援するだけでなく、より質の高い人材育成に貢献します。企業研修を通して得られる実践的な経験は、卒業後の就職活動や社会人生活において大きなアドバンテージとなります。学生は、研修を通して得られた経験や学びを活かし、将来のキャリアプランを具体的に描くことができるようになります。企業社会へのスムーズな適応、そして将来の活躍を支援するプログラムとして、企業研修は重要な役割を担っています。
3. 安全対策と事前指導 万全の体制による研修実施
企業研修の安全性を確保するため、学生教育研究災害傷害保険(インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険)への加入を義務付けています。保険料は210円(学生負担)で、対人賠償と対物賠償を合わせて1事故につき1億円を限度とする補償が提供されます。万が一の事故発生にも備え、安全な研修環境を提供することにより、学生は安心して研修に臨むことができます。また、研修開始前には、十分なガイダンスを実施し、問題発生を未然に防ぐための徹底した事前指導も行っています。安全な研修環境の提供は、学生の安心感を高め、研修効果の向上にも大きく貢献します。学生の安全と安心を最優先に考え、万全の体制で企業研修を実施することで、学生の成長を支援しています。
V.プレゼン資料作成入門講座 ビジネスコミュニケーション能力向上
パワーポイントを活用したプレゼンテーション能力向上を目的とした講座。効果的なプレゼンテーション手法、資料作成、ビジネスコミュニケーションスキルを習得。実践的な演習を通して、情報伝達能力を高める。(講師:天笠道裕氏)
1. プレゼンテーション能力の重要性 ビジネスと日常生活における必須スキル
現代社会では、ビジネスシーンのみならず日常生活においても、効果的なコミュニケーション能力が不可欠です。プレゼンテーションはその重要な手段の一つであり、相手に情報を正確に伝え、理解と共感を促すためのスキルが求められます。この講座では、プレゼンテーション能力の重要性を強調し、そのスキル習得の必要性を明確に示します。ビジネスにおいては、優れた商品やサービスを開発しても、その価値を相手に効果的に伝えられなければ、販売競争に勝ち残ることができません。同様に、日常生活でも、魅力的なアイデアや企画を相手に伝えられなければ、賛同を得ることが困難です。そのため、情報やメッセージを分かりやすく正確に表現する能力、すなわち高いプレゼンテーション能力が求められるのです。この講座は、そうしたニーズに応えるために開講されました。
2. パワーポイント活用 効果的なプレゼンテーションのためのツール
効果的なプレゼンテーションを行うためには、適切なツールを活用することが重要です。本講座では、パワーポイントを効果的に活用するための技術を、基礎から丁寧に解説します。パワーポイントの様々な機能の使い方を、初心者にも分かりやすく説明し、実際にパソコンを操作しながら実践的なスキルを習得できるよう設計されています。受講者は、講座を通して、パワーポイントの基本操作から高度なテクニックまでを習得し、効果的なプレゼンテーション資料を作成できるようになります。講座では、視覚的な効果を最大限に活かした資料作成方法、情報の整理・構成、デザイン、そして効果的な表現方法などを学びます。これにより、受講者は、単に情報を伝えるだけでなく、聴衆の心を動かす魅力的なプレゼンテーションを実現することができます。
3. 講座の構成と成果 実践的なプレゼンテーションの実施
本講座は、全3回にわたって開催され、段階的にスキルを習得できるよう構成されています。1回目はオリジナルテーマの設定、ストーリー作り、情報収集などの基礎的な部分、2回目はプレゼン資料の作成、そして3回目は最終調整とプレゼンテーションの実施という流れです。最終回では、受講者各自が作成したオリジナルプレゼン資料を用いて、実際にプレゼンテーションを行います。これは、学習成果を実践的に確認し、フィードバックを得るための重要な機会です。受講者は、講座を通して、プレゼンテーション資料作成から発表までの一連のプロセスを体験し、実践的なスキルを身につけることができます。この実践的な学習を通して、受講者は自信を持ってプレゼンテーションを行うことができるようになり、ビジネスシーンにおいても大きなアドバンテージとなります。プレゼンテーションスキル、情報デザイン、そしてコミュニケーション能力といったキーワードが、この講座の成果を的確に表しています。
VI.保護者懇談会 学部教育 学生生活への理解促進
新入生・在学生の保護者を対象に、学部教育、学生生活、就職支援に関する説明と相談会を実施。大学への理解を深め、学生生活の充実に向けた支援を促進。
1. 保護者懇談会の目的 学部教育 学生生活への理解促進と安心感の提供
経営学部では、毎年、新入生および在学生の保護者を対象とした懇談会を実施しています。この懇談会は、学部教育の内容、学生生活、大学施設、卒業後の進路といった情報を保護者の方々に提供し、疑問や不安を解消することを主な目的としています。新入生の保護者にとっては、本学経営学部への進学決定にあたり、どのような教育を受けられるのか、卒業後の就職状況はどうなのかといった疑問を解消する機会となります。また、上級生の保護者にとっては、履修状況、成績、就職活動の進捗など、学生の学習状況や将来への不安を払拭し、安心して学生生活を支援できるよう、大学への理解を深めてもらう場となっています。保護者の方々の大学への理解を深めることで、学生はより安心して勉学に励むことができ、充実した学生生活を送ることが期待できます。
2. 懇談会の内容 学部教育 学生生活 就職支援に関する情報提供
懇談会では、学部教育の理念やカリキュラム、学生生活におけるサポート体制、大学施設の利用方法、そして卒業後の進路支援について、詳細な説明が行われます。保護者の方々は、これらの説明を通して、本学経営学部の教育内容や学生生活の状況を具体的に理解することができます。また、質疑応答の時間も設けられ、保護者の方々からの質問に教員が丁寧に回答することで、疑問点を解消し、大学への理解を深めます。さらに、内定を得た先輩学生からのアドバイスや体験談なども紹介することで、学生の将来への不安を軽減し、保護者の方々に安心感を与えます。就職支援体制の説明は、保護者にとって特に重要な情報であり、大学が学生の就職活動に対して積極的に取り組んでいることを示すことで、安心感を高める効果があります。
3. 保護者からの意見 大学への期待と改善点
懇談会では、保護者の方々から大学への要望や意見を収集しています。これらの意見は、大学における教育活動の改善や、学生支援体制の充実を図る上で貴重な情報となります。保護者からの意見を参考に、大学は教育内容や学生支援の改善に取り組みます。例えば、建学の精神や学部の教育理念への理解、社会が求める人材像、就職支援体制の充実など、肯定的な意見が多く寄せられる一方で、情報提供の内容が分かりにくい、内容がまとまっていないといった改善点も指摘されています。これらの意見を真摯に受け止め、今後の懇談会や大学運営に反映させることで、より良い教育環境を提供し、学生の成長を支援していきます。保護者の意見を反映した改善は、学生と保護者双方にとって、より良い大学生活を送る上で不可欠な要素となります。
VII.高校生向け授業 出前講義 高大連携による教育機会拡大
北海道内の高校を対象に、経営学、経済学、ビジネスに関する出前講義を実施。高大連携による教育機会の拡大と、高校生への進路指導。
1. 高大連携による教育機会の拡大 高校生の学びを支援
経営学部では、地域社会への貢献の一環として、高校生を対象とした出前講義、いわゆる高大連携授業を積極的に展開しています。2012年度は、寿都高校、北海学園札幌高校、遠軽高校など、北海道内の複数の高校に教員を派遣し、多様なテーマに基づいた授業を行いました。これらの授業を通して、高校生は大学教育に触れる機会を得ると同時に、経営学や経済学に関する基礎的な知識を習得することができます。大学教員による質の高い授業は、高校生の学習意欲を高め、将来の進路選択に役立つ貴重な経験となります。高大連携は、地域社会の活性化に貢献するだけでなく、将来の優秀な人材育成にも繋がる重要な取り組みです。大学と高校の連携強化は、教育の質の向上、そして地域社会の発展に大きく貢献します。
2. 授業内容 多様な分野を網羅した実践的な講義
高校生向け授業では、「日本企業における採用と昇進のしくみ」、「広告を通じた私たちと企業の関係」、「間違いだらけの意思決定」、「NARUTOの経営学~マンガに見る仕事と組織~」、「企業スポーツ挫折のあとに」、「大学入門~経営学の場合~」、「流通と商業経営」、「集団は賢いか~体験ゲームを通じて考える~」、「経営学と経済学」、「日本の会社と社会②~セブンイレブンと流通革命~」など、多様なテーマを取り上げています。これらのテーマは、経営学、経済学、ビジネス、社会学など、幅広い分野をカバーしており、高校生にとって興味深い内容となっています。実践的な内容や身近な事例を取り入れることで、高校生は経営学や経済学をより身近に感じ、学習への意欲を高めることができます。多様なテーマ設定は、高校生の興味関心を高め、将来の進路選択に役立つ知識やスキルを習得できる機会を提供します。これらの授業は、単なる知識の伝達にとどまらず、高校生自身の探求心を刺激し、主体的な学びを促すことを目的としています。
3. 参加高校と教員 地域に根ざした高大連携
2013年3月15日時点での情報に基づき、出前講義を実施した高校と担当教員をリストアップします。寿都高校(澤野雅彦)、北海学園札幌高校(大平義隆)、遠軽高校(下村直樹)、札幌東陵高校(鈴木修司)、札幌国際情報高校(春日賢)、札幌啓北商業高校(澤野雅彦)、札幌新川高校(田中昭憲)、札幌あすかぜ高校(春日賢)、札幌創成高校(佐藤芳彰)、札幌光星高校(増地あゆみ)、倶知安高校(澤野雅彦)、網走南ヶ丘高校(春日賢)、札幌月寒高校(澤野雅彦)、新得高校(春日賢)、苫小牧南高校(春日賢)などです。これらの高校は、北海道の様々な地域に位置しており、地域に密着した高大連携活動となっています。それぞれの高校の特色や生徒のニーズに合わせた授業内容を準備することで、より効果的な教育機会を提供しています。担当教員も経営学部の様々な分野の専門家であるため、幅広いテーマに対応できます。地域貢献、教育支援、そして人材育成を目的とした、北海道全体に広がる高大連携活動が展開されています。
VIII.講義支援システムGOALS 学習環境の充実
講義支援システムGOALS(CoursePower)を活用し、24時間いつでもどこでも講義情報、資料、課題にアクセス可能。学習の効率化と理解度向上を支援。
1. GOALSシステムのリニューアル CoursePowerへの移行と機能強化
経営学部では、従来から利用してきた講義支援システムGOALSを、2011年度からCoursePowerへとソフトウェアをリニューアルしました。このリニューアルによって、システムの機能が強化され、学生総合支援システムG-PLUS!と連動することで、全学的な利用が可能となりました。CoursePowerへの移行により、より多くの学生がシステムの恩恵を受けることができるようになり、学習環境の充実が図られています。リニューアルされたシステムは、機能性と利便性を向上させ、学生の学習をサポートする上で重要な役割を果たします。より多くの学生が利用できるようになったことで、情報共有の効率化、学習効果の向上、そして大学全体の教育環境の改善に貢献しています。
2. システムの機能 24時間365日アクセス可能な学習環境
リニューアルされたGOALS(CoursePower)は、24時間いつでもどこでもインターネットを通じてアクセス可能です。学生は、講義資料や配布プリントを事前にダウンロードしたり、予習・復習課題に取り組むことができます。これにより、授業への理解度が向上し、学習効率が大きく改善されます。さらに、科目によってはレポート課題の指示や提出、テストや補習もGOALS上で行われるため、学生はシステム一つで学習に必要な全ての情報を管理することができます。いつでもどこでも学習できる環境は、学生の学習スタイルに合わせた柔軟な学習を可能にし、学習効果の向上に繋がります。このシステムは、単なる情報提供ツールではなく、学生の学習活動を包括的に支援する重要なインフラとして機能しています。
3. 教員サポート 教材コンテンツ作成支援
GOALS(CoursePower)は、学生の学習支援だけでなく、教員の教材コンテンツ作成支援にも役立っています。システムには、ヘルプデスクが設置されており、教員は教材作成に関する様々な相談やサポートを受けることができます。これにより、教員はより質の高い教材を作成し、学生に提供することが可能となります。質の高い教材提供は、学生の学習意欲を高め、教育の質向上に繋がります。教員と学生双方にとって使いやすいシステムであることが、このシステムの大きな特徴であり、効果的な教育活動を実現するための重要な要素となっています。質の高い教育コンテンツの提供を通して、学生の学習成果の最大化を目指しています。
IX.産学連携 企業との協働による実践的な教育
多くの企業と連携し、インターンシップ、特別講義、就職支援など、実践的な教育プログラムを提供。(企業例:北海道銀行、野村證券、札幌中央信用組合、多数の道内企業)
1. 産学連携の広がり 多様な企業との協働体制
本学部の教育活動は、多くの企業との幅広い産学連携によって支えられています。インターンシップ、特別講義、就職支援など、多様なプログラムにおいて、企業との協働体制が構築されています。この連携を通して、学生は実践的なビジネススキルを習得し、企業社会への理解を深めることができます。企業との繋がりは、学生の就職活動にも大きなメリットをもたらします。企業からのリアルな声を直接聞くことで、学生は社会で求められる能力を理解し、自身のキャリアプランを具体的に描くことができます。企業側にとっても、優秀な人材の育成に貢献できるというメリットがあり、相互に有益な関係を築いています。この産学連携は、単なる協力関係ではなく、大学と企業が共に発展していくための戦略的なパートナーシップです。
2. 企業との連携事例 金融機関 製造業 不動産業界など
産学連携の具体例として、北海道銀行、野村證券といった金融機関との連携による金融・証券講座、札幌中央信用組合などの金融機関による地域金融に関する特別講義などが挙げられます。また、北海道オフィスマシン株式会社、株式会社プリプレス・センター、株式会社白石ゴム製作所、環境開発工業株式会社、株式会社レイジックスといった、多様な業種の企業が特別講義や企業研修に協力しています。さらに、ミサワホームイング北海道株式会社、積水ハウス株式会社、大和ハウス工業株式会社など、不動産業界の企業も連携しており、幅広い業界との繋がりを持つことが本学部の特徴となっています。これらの企業との連携は、学生に多様なビジネスモデルや業界の現状を学ぶ機会を提供し、実践的な教育に大きく貢献しています。企業の多様性は、学生の視野を広げ、多様なキャリアパスを考える上で役立ちます。
3. 産学連携による教育効果 実践的な知識 スキルの習得とキャリア形成支援
企業との連携による実践的な教育は、学生の知識・スキルの向上とキャリア形成に大きく貢献しています。特別講義や企業研修を通して、学生は最新のビジネス動向や企業の経営戦略を学ぶことができます。また、企業で働く社員との交流を通して、企業文化や仕事のやり方などを理解し、社会人としてのマナーや倫理観を養うことができます。これらの経験は、卒業後の就職活動や社会人生活において大きなアドバンテージとなります。企業との連携は、学生の就職活動を支援するだけでなく、社会に貢献できる人材育成にも繋がります。企業が求める能力を学生が理解することで、より効果的な学習を行い、社会に貢献できる人材へと成長することができます。産学連携は、学生と企業、そして地域社会全体にとって、大きなメリットをもたらす取り組みです。
X.研究活動 経営学に関する学術研究発表
教員による経営学に関する研究活動。学会発表等の活動を通して、学術的知見の共有と発展に貢献。(学会例:日本経営学会、北海道心理学会など)
1. 教員の研究活動 多様な分野における学術貢献
経営学部の教員は、経営学に関する幅広い分野で活発な研究活動を行っています。その成果は、国内外の学会で発表されるなど、学術界に大きく貢献しています。研究テーマは多岐に渡り、コーポレート・ガバナンス、人的資源管理、マーケティング、消費者行動、中国の企業統治など、現代の経営学における重要な課題に取り組んでいます。研究活動を通して、教員は最新の知見を習得し、学生への教育に役立てています。また、研究成果は論文や書籍として発表され、学術界の発展に貢献しています。これらの研究活動は、経営学部の教育・研究水準の向上に大きく寄与しており、学生にも刺激を与え、研究への関心を高める効果があります。質の高い研究活動は、大学としての社会的責任を果たす上でも重要な役割を担っています。
2. 学会発表 研究成果の発表と情報共有
教員は、日本経営学会、北海道心理学会、経営哲学学会、経営学史学会、日本広告学会、実践経営学会など、様々な学会で研究成果を発表しています。発表内容は、コーポレート・ガバナンスと人的資源管理、メタ認知尺度検証、バーチャルリアリティによる空間学習、社会科学の法則性と経営哲学、ドラッカー研究、物語広告の効果、コミュニティ・レストランのマネジメント、マーケティング論、中国の老舗企業の経営戦略、情報品質文脈形成条件など多岐に渡ります。これらの発表を通して、教員は自身の研究成果を広く共有し、他の研究者との議論や交流を行うことで、研究を深化させています。また、学会発表は、新たな研究テーマの発掘や研究ネットワークの構築にも繋がる重要な機会となります。学術界との連携強化を通して、研究の質を高め、社会に貢献できる研究成果を生み出しています。
3. 研究テーマ例 具体的な研究内容の紹介
具体的な研究テーマの一例として、市場参入順位と消費者行動に関する研究(特定保健用食品市場を事例として)、マーケティングの体系化における人間概念に関する研究、中国における老舗企業の認定とその経営戦略(瀋陽老辺餃子館を事例に)、マーケティング・ミックス4Pに関する研究、ドラッカー研究、情報品質文脈形成条件の検討(求貨求車システムの事例に基づく考察)、拡張された市場志向に関する研究、ピーナッツ効果における選択・拒否・交換様式の比較、物語広告に対する男女の共感差、ストレッチ・バジェッティングの発現形態、大学生ライフスタイルと健康に関する研究、取引仲介サイトにおける人的交流の研究、中国の地方国有企業における企業統治と党の関与に関する研究などが挙げられます。これらの研究は、経営学の様々な分野を網羅しており、現代社会の複雑な経済状況を多角的に分析することを目指しています。これらの研究成果は、学術論文や研究報告書として発表され、社会に貢献しています。
