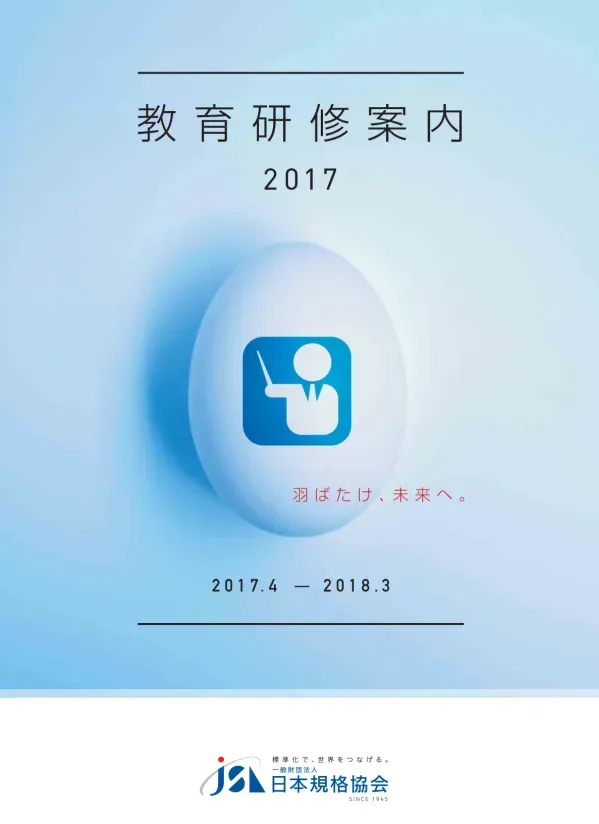
2017年度セミナー一覧:品質管理研修
文書情報
| 著者 | 日本規格協会 |
| 専攻 | 品質管理、標準化、生産管理、リスクマネジメント等 |
| 会社 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| 文書タイプ | セミナー案内パンフレット |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 27.30 MB |
概要
I.品質管理 改善のための各種セミナー
本資料は、日本規格協会が提供する様々な品質管理・改善に関するセミナーの概要です。品質管理、QCサークル、5S、ムダ取り、不良低減、設備管理などのテーマを網羅した入門から実践レベルまでのコースが用意されています。特に、実験計画法、多変量解析法、品質工学(タグチメソッドを含む)といった統計的手法を用いた改善手法に関するセミナーが充実しています。ISO9001、ISO14001、FSSC22000などの国際規格に準拠した研修も提供されており、内部監査員育成コースも含まれています。 1953年開講以来、5万人以上の修了者を輩出する実績があります。
1. QCサークル入門コース
QCサークル活動の基礎を学ぶ入門コースです。QCサークルを組織し、活動を開始するための基本的な知識や手法を習得できます。具体的には、QCサークルの目的、役割、活動手順、そして効果的な活動を行うためのノウハウなどを学びます。チームワークの構築や問題発見、解決のためのツール、データ分析の基本などを習得することで、現場の改善活動にすぐに役立つ実践的なスキルを身につけることができます。 また、リーダーシップについても触れられ、円滑なチーム運営のためのコミュニケーションスキルや問題解決能力を向上させるためのトレーニングが含まれています。このコース修了後には、QCサークルを主体とした現場改善活動に自信を持って取り組めるようになるでしょう。さらに、QC検定1級、2級の受験対策にも役立ちます。
2. 日常管理 5S 目に見える管理 ポカヨケ ムダ取りコース
これらのコースは、現場における日常的な改善活動に焦点を当てています。日常管理コースでは、日々の業務における効率化、標準化、そして問題発生時の迅速な対応を学ぶことができます。5Sコースでは、整理整頓、清掃、清潔、清潔維持、しつけの5S活動を通して、職場環境の改善と効率向上を実現するための具体的な方法を習得します。目に見える管理コースでは、視覚的なツールを用いた管理手法を学び、異常や問題点を早期に発見し、迅速に対処するためのスキルを身につけます。ポカヨケコースでは、ミスを未然に防ぐための工夫や仕組み作りを学び、不良発生率の低減を目指します。ムダ取りコースでは、ムダをなくすための様々な手法を習得し、生産性向上に繋げます。これらのコースは、互いに関連性があり、総合的に学ぶことで、より効果的な現場改善を実現できるでしょう。
3. 異常 クレーム管理 不良低減 設備管理 試験 計測器管理コース
これらのコースは、品質管理における重要な要素である異常、クレーム、不良、設備、試験・計測器の管理に特化しています。異常・クレーム管理コースでは、異常発生時の対応手順、クレーム処理の方法、そして再発防止策などを学びます。不良低減コースでは、不良発生原因の分析、対策、そして改善活動の推進方法について学びます。設備管理コースでは、設備の維持管理、保全、そして効率的な運用方法を学びます。試験・計測器管理コースでは、正確な測定、データ管理、そして計測機器の適切な使用方法について学びます。これらのコースは、実践的なスキルを身につけるための演習やケーススタディが多く含まれており、修了後は、現場で直ちに役立つ知識と技術を習得できます。特に、不良低減コースは、市場競争力向上のため高度化・複雑化する製品開発における、従来手法では対応できない課題解決に役立つでしょう。
4. 作業改善 作業標準 リーダーシップ OJT 現場指導コース
これらのコースは、人材育成と組織全体の能力向上に焦点を当てています。作業改善コースでは、作業効率の向上、安全性、品質向上のための具体的な方法を学びます。作業標準コースでは、標準作業手順書の作成、そしてその運用方法を習得します。リーダーシップコースでは、チームを効果的にリードし、モチベーションを高めるためのスキルを学びます。上手くい OJTの進め方とコミュニケーションの取り方コースでは、効果的なOJTの実施方法、そして部下との良好なコミュニケーションを築くためのスキルを習得できます。現場指導者のための正しい仕事の教え方コースでは、現場で働く従業員への効果的な指導、教育方法を学びます。これらのコースを通して、個々の従業員の能力向上、そして組織全体の生産性向上を目指します。特に、OJTに関するコースは、熟練者の減少や非正規社員増加といった現状を踏まえ、現場のブラックボックス化を防ぎ、技術ノウハウの伝承を促進するのに役立ちます。
5. 生産性向上のための職場配置 物の流し方 現場における問題解決コース
これらのコースは、生産システム全体の最適化と効率向上に焦点を当てています。生産性を向上するための職場配置と物の流し方コースでは、レイアウト設計、そして材料の流れの最適化を学び、ムダをなくし、生産性を最大限に高める方法を習得できます。現場における問題解決コースでは、問題解決のプロセス、そして効果的な問題解決手法を学びます。ムリ・ムダ・ムラの見つけ方・探し方コースでは、現場に潜むムリ、ムダ、ムラを特定し、改善するための具体的な方法を学びます。生産性向上のための生産システムの設計と運用コースでは、生産システム全体の設計、導入、そして運用方法を学びます。これらのコースは、実践的な演習を多く含んでおり、修了後は、現場で直ちに役立つ知識と技術を習得できます。これらの知識と技術を活用することで、企業の競争力を強化することが期待できます。
II.統計的手法を用いた品質管理 改善
統計的手法を用いた品質管理・改善に関するコースでは、実験計画法、多変量解析法、データ分析の基礎から応用までを網羅しています。JMPなどの統計解析ソフトウェアを用いた実践的な演習を通して、管理図、パレート図、ヒストグラムなどのQC七つ道具の活用方法を習得できます。 応答曲面法やコンピュータ実験といった高度な手法も取り上げられています。 QC検定1・2級対策にも役立ちます。
1. 実験計画法セミナー
入門コースから活用入門コースまで、実験計画法の基礎から実践的な応用までを網羅したセミナーです。入門コースでは、実験計画法の基本概念、用語、そして実験計画の立て方などを学びます。活用入門コースでは、実際に実験計画を立案し、実行するための具体的な方法を学びます。多様な実験計画法の種類やそれらを選択する基準、そして実験データの解析方法についても習得できます。実践的な演習を通して、統計的思考力とデータ分析力を養い、QC検定1級・2級の受験対策にも役立ちます。Excelを用いた解析手順も解説され、受講者はすぐに職場での活用が可能となります。企業における実験計画法の設計から解析までのプロセスを学ぶことで、より実践的なスキルを身につけることができます。
2. 多変量解析法セミナー
多変量解析法の実践的なスキルを習得できるセミナーです。多変量データの解析手法、特に、複数の変数間の関係性を分析し、最適な解を見つけるための高度な統計的手法を習得します。このセミナーでは、数式を極力避け、具体的な事例を用いた「解析ストーリー」を中心に解説することで、統計的思考力を養います。演習を通して、データの可視化、分析、そして解釈のスキルを向上させます。また、多変量解析において重要な層別の重要性や、それを取り込んだダミー変数を用いた変動要因のための回帰分析を用いた工程解析についても解説します。複雑なデータから有用な情報を抽出する能力を向上させることで、より高度な品質管理・改善活動に貢献できるようになります。QC検定2級対策にも有効です。
3. 統計解析ソフトウェアJMP活用セミナー
統計解析ソフトウェアJMPを用いたデータ分析を学ぶセミナーです。JMPは、データの可視化や解析を容易に行えるソフトウェアとして、産業界で広く利用されています。本セミナーでは、JMPを用いた品質管理、多変量解析、実験計画法、応答曲面法、コンピュータ実験などの最新の統計手法を習得できます。数式を極力使わず、具体的な例を用いた解説で、統計的思考力とデータ分析力を効率的に向上させます。「詰め込み型」の講義により、受講者はJMPの機能を効果的に活用できるようになります。さらに、JMPを使った応答曲面法やコンピュータ実験についても解説することで、高度なデータ分析スキルを習得できます。このセミナーは、統計ソフトから新しい知識を得るという学習スタイルを体験できる機会を提供します。
4. 品質工学セミナー
品質工学の基礎から応用までを網羅したセミナーです。入門者向けコースでは、品質工学の基本概念、そしてその考え方や応用事例について学びます。実践コースでは、社内ですぐに活用できる実践的なスキルを習得できます。さらに、開発・設計者向けの高度なスキル向上コースでは、タグチメソッド(ロバスト設計)などを用いた、高信頼の製品開発を短期間で実現するための手法を習得できます。 統計解析ソフトウェアJMPを用いた多特性最適化や統計モデルによるロバスト最適化についても解説されます。 受講者は、品質工学の知識とスキルを習得することで、製品開発や設計における効率化、品質向上、そしてコスト削減に貢献できるようになります。ベテラン講師陣による丁寧な指導と演習により、初めて品質工学を学ぶ方にも最適です。
III.現場力強化と問題解決のための研修
製造現場における問題解決、生産性向上、コスト低減のための研修を提供しています。見える化によるムリ・ムダ・ムラの排除、ポカヨケによるミス防止、作業改善、設備管理、クレーム管理など、現場の課題解決に直結した実践的な内容となっています。リーダーシップ育成、OJTの進め方に関するコースも用意され、現場力の向上を目指します。VE(価値工学)を用いたコスト削減手法も学べます。
1. 問題解決と改善のキーポイント
現場で発生する様々な問題を効率的に解決し、改善に繋げるための研修です。問題解決のプロセスを体系的に学び、問題の定義、原因分析、そして対策立案といった各段階における具体的な手法を習得します。 特に、改善活動におけるキーポイントとして、問題の見える化、潜在的要素の見える化、アイデアの見える化、そして実用化への見える化の4つのステップが紹介されます。顧客の声や経営方針からテーマを掘り起こし、問題発生のシステムや従業員の能力を分析し、成功事例からノウハウを見つけ出し、実用化に向けて課題を解決していくプロセスを学ぶことができます。 この研修は、QCサークル活動や部署を問わず、現場の改善活動に携わる全ての人にとって役立つ実践的な内容となっています。歩留まり向上、生産性向上、チョコ停削減、ムリ・ムダ・ムラの削減、ポカミス削減など、様々な現場課題の解決に役立つノウハウを習得できます。
2. ムリ ムダ ムラの発見と排除
現場におけるムリ、ムダ、ムラの発見と排除に特化した研修です。ムリ、ムダ、ムラの定義、種類、そしてそれらを見つけるための具体的な手法を学びます。 5S、見える化、ポカヨケなどの手法を効果的に活用し、ムダを削減し、生産性を向上させるための実践的なスキルを習得できます。 また、効率を優先した業務の分業化による弊害、技術ノウハウの伝達不足、作業の意味の理解不足、そして迅速な対応の遅れといった問題点とその解決策についても解説します。熟練者の退職や非正規社員の増加といった現状を踏まえ、現場のブラックボックス化を防ぎ、より効率的で効果的な改善活動を行うためのノウハウを習得できます。この研修を通して、現場の潜在能力を最大限に引き出し、持続可能な改善活動を実現するための基盤を築くことができます。
3. 品質保証のための見える化と体系化
現場における品質保証を確実に行うための研修です。技術セクションが定めた設計品質に対する設計思想の理解、そして暗黙知である品質標準の見える化(形式知化)について学びます。QC工程表、作業標準、工程FMEA、品質マトリックス、なぜなぜ分析といった個々のツールを理解するだけでなく、それらのツール間の関連性と体系的な工程管理の仕組みについても習得します。企業戦略、商品開発、製品設計など、様々なシーンにおける各手法の目的、効果、考え方、そしてそれらの連携について、事例を交えて解説します。 この研修では、企業とアカデミアの最前線で活躍する2名の講師が、双方向型のインタラクティブな講義を行い、受講者からの質問だけでなく、講師間での鋭い議論を通して、深い理解を促します。現場で働く技術者にとって、品質保証の仕組みを理解し、運用するための非常に有益な研修となります。
4. 生産システムの設計と運用
生産システム全体の設計、導入、そして運用方法を学ぶ研修です。生産性を向上させるための職場配置、物の流し方、そして効率的な生産ラインの構築について学びます。 また、VE(Value Engineering:価値工学)と原価管理を組み合わせたコスト低減手法も習得できます。製品・サービスの機能とコストに着目し、機能の変更による価値向上、そしてコスト削減のための具体的な方法を学びます。 単なるコスト削減だけでなく、製品・サービスの価値を高めるための戦略的な視点も習得できます。日々の生産活動における改善活動がコスト面でうまくいかない、なかなか進まないといった課題を抱えている企業にとって、この研修は非常に有効です。この研修を通して、生産システム全体を最適化し、持続的な生産性向上を実現するための戦略を立てることができます。
5. コミュニケーションと人材育成
組織内における円滑なコミュニケーションと人材育成のための研修です。仕事が円滑に、効率よく、継続的に伝承・伝達・教育されていくためのコミュニケーションの考え方、取り方について、コーチングの手法を交えて学びます。個人演習、グループ討論、そして発表・講評を通して、実践的なスキルを習得します。 この研修は、スタッフや事務部門など、組織内の人材育成に関わる全ての人にとって有益です。効果的なコミュニケーションスキルを習得することで、組織全体の能力向上、そして生産性向上に貢献できます。特に、近年増加している非正規社員への教育や、熟練者の退職による技術・知識の伝承において有効なスキルを身につけることができます。工場管理の最終目的である利益確保、そして長期的な視点での工場管理体制の構築にも役立ちます。
IV.国際規格対応と管理者育成
ISO9001、ISO14001、FSSC22000、IATF16949といった国際規格に準拠した品質マネジメントシステム(QMS)構築・運用のための研修です。内部監査、管理責任者の役割と責任、継続的改善のための仕組み作りを学びます。 JRCA(マネジメントシステム審査員評価登録センター)推奨カリキュラムに準拠したコースもあり、管理技術者登録申請に必要な知識・スキルを習得できます。
1. ISO9001 内部監査員養成研修
ISO9001:2015版の要求事項に基づいた内部監査の実施方法を習得する研修です。2008年版からの変更点、要求事項と実際の業務との連携方法、そして現実的な監査の実施方法を学びます。 内部監査の有効性向上、特にプロセスアプローチに基づくプロセス監査の実施方法を習得することで、QMS(品質マネジメントシステム)の改善に繋げることができます。演習、講師からのフィードバック、そして受講生同士のディスカッションを通して、実践的なスキルを習得します。認証機関による監査や内部監査の有効性について不満を持つ組織のニーズに応え、パフォーマンス重視の監査の実施に必要な体系的な教育を提供します。 研修後には、ISO9001:2015版に準拠した内部監査を実施し、自社のQMSをさらに充実させることができるようになります。
2. ISO9001 管理技術者養成研修
組織におけるQMS活動を継続的に維持、改善していくために必要な管理技術者の力量を育成する研修です。JRCA(マネジメントシステム審査員評価登録センター)で推奨されているカリキュラムを網羅しており、研修受講と実務経験を満たすことで、JRCAのISO9001管理技術者登録申請が可能になります。 2015年9月のISO9001改訂で「管理責任者」の記述がなくなりましたが、組織がQMS活動を維持し、改善を続けるためには、管理責任者に求められていた力量を継続的に維持することが不可欠です。本コースでは、組織(企業)活動に効率的なQMS運営を目指し、JRCA登録による第三者評価で管理技術者の力量を証明することを可能にします。演習時間を多く取り入れた実践的なコースで、管理技術者の力量を組織が継続的に維持できるようサポートします。
3. ISO14001 環境マネジメントシステム研修
ISO14001に基づいた環境マネジメントシステム(EMS)の構築・運用、そして継続的改善を推進するための研修です。ISO14001の要求事項を表面的な理解にとどまらず、その意図を正しく理解し、自組織に最適なEMSを企画できる基礎力を養成します。 管理責任者・推進担当として、組織全体の環境管理活動をリードするための知識・スキルを習得できます。2004年版からの移行を支援する研修も提供しており、新旧規格の相違点、そして2015年版の要求事項を活かした内部監査の実施方法を学ぶことができます。 特に、ISO14001:2015の5.1c)項で求められる「組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合」について、製品・サービスのライフサイクル全体を考慮した実践的な内容となっています。 環境上の成果を高めるための戦略的な視点と、具体的な内部監査の実施方法を習得できます。
4. IATF 16949 認証取得支援研修
自動車産業向け品質マネジメントシステム規格であるIATF 16949の要求事項を理解し、認証取得のためのシステム構築・運用を支援する研修です。 規格の意図を正しく理解し、顧客満足の向上に繋がるパフォーマンスの継続的改善を重視したシステム構築・運用方法を習得します。ISO9001認証制度とは異なるIATF16949の認証制度、そして全面改定されたIATF16949認証ルール第5版の内容についても説明します。 演習や審査事例を通して、規格の解説を行い、分かりやすく理解を深めます。 IATF16949について初めて学ぶ方、パフォーマンス向上のためのシステム構築・運用でお悩みの組織のご担当者様におすすめです。この研修を通して、グローバルな競争環境において、高い品質と顧客満足を実現するためのシステムを構築・運用できるようになります。
5. FSSC 22000 食品安全マネジメントシステム研修
食品安全マネジメントシステム規格FSSC22000の要求事項を理解し、認証取得のための準備を支援する研修です。近年増加している食中毒問題やコンプライアンス問題への対応として、食品安全に対する消費者の意識の高まりに対応するためのシステム構築を学びます。 FSSC22000は、ISO22000とPRP(前提条件プログラム)を統合した規格であり、GFSI(国際食品安全イニシアティブ)が認証スキームとして認めているため、国内でも認証取得が進んでいます。 本コースでは、ISO22000の要求事項を具体的事例を交えて解説し、食品安全ハザードの概要も説明します。ワークショップを中心とした実践的なコースで、食品安全に関わるハザード分析や継続的改善のためのスキルを習得できます。経営者層、食品安全チームリーダー、メンバー候補、内部監査員などを対象としています。
V.品質工学とタグチメソッド
品質工学、特にタグチメソッドを用いたロバスト設計に関するセミナーです。開発期間の短縮、コスト削減、品質向上のための効果的な手法を学びます。幾何公差に関する知識も習得できます。グローバルな競争環境下での製品開発・設計に役立つ内容です。
1. 品質工学入門と実践
品質工学の基礎を学ぶ入門コースと、企業ですぐに活用できる実践的なスキルを習得する実践コースがあります。入門コースでは、品質工学の基本的な考え方、概念、そして様々な手法について学びます。実践コースでは、具体的な事例や演習を通して、品質工学の手法を実際の業務に適用するためのノウハウを習得します。 これらのコースは、開発・設計部門の技術者だけでなく、研究者やスタッフ層にも適しており、初めて品質工学を学ぶ方にも分かりやすい内容となっています。 ベテラン講師陣による丁寧な指導と、演習や適用事例の紹介により、効率的に品質工学の知識とスキルを習得することができます。QC検定1級・2級対策にも役立つ内容です。
2. 開発 設計者のための品質工学スキル向上
開発・設計部門の技術者向けに、高度な品質工学スキルを習得するためのコースです。 このコースでは、より高度な品質工学の知識とスキルを習得し、開発期間の短縮、手戻りの低減、そして市場におけるトラブルやクレームの減少を実現するためのノウハウを習得します。特に、タグチメソッドを用いたロバスト設計、高信頼な製品を短期間で開発するための手法について深く学びます。 演習を通して、実践的なスキルを身につけ、研究開発、設計、設備設計、設備仕様決定などの効率的な進め方を体系的に理解することができます。 タグチメソッドの誤解を解き、本来の有効な活用法を学ぶことで、グローバルな競争環境下でも高い競争力を維持するための能力を身につけることができます。
3. タグチメソッドの有効活用
田口玄一博士が提唱したタグチメソッド(品質工学)の正しい理解と有効な活用法を学ぶコースです。 タグチメソッドは、米国での成功を皮切りに、日本、中国、韓国、そしてヨーロッパまで世界中で活用されている手法ですが、その理解や活用には誤解も多いです。このコースでは、日米でタグチメソッドを推進、指導してきた講師が、講義と参加者との討論を通じて、タグチメソッドの誤解を解き、本来あるべき有効な活用法を学びます。 タグチメソッドを闇雲に適用することの危険性、そして開発期間短縮、手戻り低減、市場トラブル減少を実現するための導入方法を重点的に解説します。 このコースは、グローバルなモノづくりに対応し、製造コストを下げながら製品品質を向上させたいと考えている企業にとって、非常に有益な内容となっています。
4. 幾何公差入門
グローバルなモノづくりに対応するために必須となる幾何公差の基礎を学ぶコースです。「寸法公差主体の図面作り」から「幾何公差主体の図面作り」への移行を支援します。 幾何公差をこれから学びたい方、あるいは既に使用しているが正しい理解に自信がない方に向けて、図面に幾何公差を描くための基本的なルールとテクニックを、講義と演習を通して習得できます。 具体的な事例を用いた解説と実践的な演習を通して、幾何公差に関する知識とスキルを習得できます。 このコースは、グローバルな競争環境において、製品の品質と精度を高めるために不可欠な知識と技術を提供します。 特に、新興国企業との競争が激化する中、開発・生産の効率化を図りたい企業にとって、非常に役立つ内容です。
