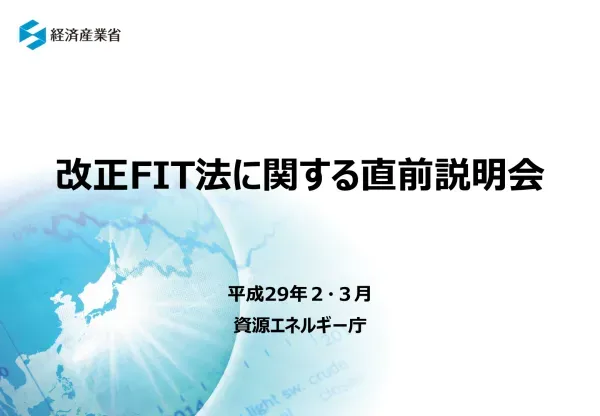
FIT制度見直し:再生可能エネルギー導入拡大と国民負担抑制
文書情報
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | エネルギー政策、経済学、または関連分野 |
| 出版年 | 2016 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 政策資料、報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.77 MB |
概要
I.再生可能エネルギー発電設備の認定制度とFIT制度改正
本資料は、日本の再生可能エネルギーの導入拡大に向けた政策、特にFIT(固定価格買取制度)に関する制度改正と認定基準について説明しています。2012年の制度開始以来、再生可能エネルギー導入量は約2.5倍に増加していますが、国民負担の増大も課題となっています。改正FIT法では、再生可能エネルギー電気の調達価格を低減させるため、入札制度の導入や、送配電事業者への買取義務者の変更などが行われました。太陽光発電, 風力発電, 地熱発電, バイオマス発電など様々な発電方法について、認定基準や手続き、保守点検、設備廃棄に関する詳細な情報が提供されています。特に、50kW未満の太陽光発電設備については、申請手続きの簡素化が図られています。また、既存の小売買取契約から送配電買取への移行についても、具体的な手続きや条件が説明されています。調達価格の算定方法や、回避可能費用についても言及されており、事業者にとって重要な情報が網羅されています。
1. 再生可能エネルギー導入拡大とFIT制度の現状
再生可能エネルギーの導入拡大は、エネルギー自給率向上と低炭素社会の実現に不可欠です。2012年のFIT制度導入以降、再生可能エネルギー導入量は約2.5倍に増加しましたが、国民負担の増大という課題も浮き彫りになっています。電力コスト低減を前提に、再生可能エネルギー拡大のための費用(買取費用)を3.7兆円~4.0兆円と設定している現状が示されています。この節では、FIT制度導入後の再生可能エネルギー導入状況と、国民負担とのバランス、そしてエネルギーミックスにおける費用配分に関する現状と課題が簡潔にまとめられています。2016年10月末時点での再生可能エネルギー発電設備の導入状況に関するデータも提示されていますが、バイオマス発電については認定時のバイオマス比率を考慮した推計値であること、四捨五入のため合計値と内訳に差異が生じる可能性があることなどが注記として記載されています。それぞれの再生可能エネルギー源(バイオマス、地熱など)の認定基準に関する要件も触れられています。バイオマス発電では安定的なバイオマス調達の見込み、地熱発電では地熱資源の性状と量の継続的な把握などが求められています。
2. 再生可能エネルギー発電設備の認定申請手続き
再生可能エネルギー発電設備の認定申請手続きは、旧制度と新制度で大きく変化しています。旧制度では、太陽光50kW未満を除く発電設備は紙申請でしたが、新制度ではシステムへの入力と申請書のプリントアウト、経済産業局への提出という流れになっています。このオンライン化により、申請内容の不備をシステムを通じてメールで連絡し、システム上で不備の確認と修正が可能となりました。特に、太陽光50kW未満の設備については、設備設置者へのメールによる申請内容の確認と承諾・拒否のシステムが導入されており、設置者側の意向確認を重視した手続きとなっています。この変更により、申請手続きの効率化と迅速化が期待されます。しかし、50kW未満の太陽光発電設備においては、設備設置者へのメール送信ができない場合があるという課題も示唆されています。この節では、申請手続きにおける旧制度と新制度の違い、オンライン化によるメリットと残された課題について解説されています。 経済産業局への申請という点では、両制度に共通点があります。
3. 認定基準と審査基準の詳細
再生可能エネルギー発電設備の認定取得には、複数の認定基準と審査基準を満たす必要があります。具体的には、「分割禁止」に関する基準では、特段の理由なく同一箇所に複数の設備を設置することを禁止し、同一地番や地権者における他の認定事業計画の有無を審査します。さらに、「標識の掲示」では、事業者名等の記載された標識の設置が義務付けられており、太陽光発電設備20kW未満・屋根置きは除外されています。必要書類としては、設備所在地の登記簿謄本が求められ、分割の疑義が生じた場合は、追加の書類提出が求められる可能性があります。「保守点検及び維持管理」では、適切な体制整備と実施が求められ、責任者と計画の明確化が審査基準となります。「設備の廃棄」に関しても、適切な計画と必要書類の提出が求められます。地熱発電については、継続的・安定的な発電のための措置が特に強調されており、資源の把握や事業の円滑な実施などが求められています。この節では、各項目の認定基準と審査基準、そして必要書類について詳細に説明されており、申請者にとって重要な情報が網羅されています。
4. FIT法改正と入札制度の導入
FIT法の改正により、各電源別に中長期的な価格目標が設定され、事業者の努力によるコスト低減が促されています。この改正の一環として、入札制度が導入され、調達価格を入札によって決定する仕組みが導入されました。入札制度では、入札対象となる再生可能エネルギー発電設備の区分、入札量、参加資格、保証金、供給価格上限額、調達期間、認定申請期限などが新FIT法第4条第1項で規定されています。入札参加者は、入札前に事業計画を提出し、参加資格審査を受けます。また、接続契約を事前に締結し、コストを確定した上で応札額を決定できるよう、落札後の一定期間まで支払期限の延長措置も設けられています。大規模太陽光発電については、地域との共生のための取り組みが求められるなど、入札プロセスに様々な考慮がなされています。保証金は、第1次保証金500円/kW、第2次保証金5000円/kWで、正当なプロセスを遂行した事業者には全額返金されます。落札後1ヶ月以内の認定申請が義務付けられ、原則として落札後3ヶ月以内の認定取得が求められています。この節では、FIT法改正による価格目標設定、入札制度の導入、入札手続きの詳細、そして落札後の事業変更に関する規定などが説明されています。
5. 送配電買取への移行と買取義務者の変更
改正FIT法により、FIT電気の買取義務者は送配電事業者(一般送配電事業者と特定送配電事業者)となり、小売電気事業者から変更されました。ただし、平成29年3月31日までに締結された特定契約(買取契約)は、契約期間満了まで小売買取が継続されます。一般送配電事業者は、全社共通の送配電買取要綱を定め、公平・平等な条件で買取を行うことが求められています。この要綱の内容と実際の買取の適切性については、国が確認していきます。小売買取を前提とした既存のモデル契約書は、平成29年4月1日以降廃止されます。送配電買取においても、FIT(全量買取)との整合性を保つため、FITインバランス特例が設けられています。この特例では、FIT発電事業者の代わりに送配電事業者または小売電気事業者が発電計画を作成し、インバランスリスクを負います。小売買取契約においては、回避可能費用の激変緩和措置が維持されますが、送配電買取では原則として対象外となります。この節では、FIT法改正による買取義務者の変更、送配電買取の仕組み、小売買取契約の継続条件、そして特定契約の変更に関する規定について説明されています。新FIT法第2条第5項と第16条についても言及されており、特定契約の定義と電気事業者の接続義務が明確にされています。
II.認定基準と審査基準
再生可能エネルギー発電設備の認定を受けるためには、いくつかの重要な基準を満たす必要があります。主な認定基準としては、複数の再生可能エネルギー発電設備の一箇所の設置制限、保守点検及び維持管理体制の整備、設備廃棄計画の適切性などが挙げられます。審査基準には、土地所有状況の確認、保守点検計画の明確性、廃棄費用の計上などが含まれます。太陽光発電設備(20kW未満を除く)には、外部から見やすい標識の掲示が義務付けられています。申請手続きは、旧制度の紙申請から、新制度のシステムを用いたオンライン申請へと移行し、効率化が図られています。特に、太陽光50kW未満の設備については、委任を受けた工務店などが申請手続きを行い、設備設置者へのメールによる確認を行う仕組みが導入されています。
1. 分割禁止に関する認定基準と審査基準
再生可能エネルギー発電設備の認定においては、特段の理由なく同一の場所に複数の発電設備を設置することを禁止する「分割禁止」に関する基準が設けられています。この基準の審査では、申請日の1年前まで遡って同一の地番または地権者による一団の土地において、他の認定事業計画がないか確認されます。さらに、隣接地番においても、設置事業者または保守点検・維持管理責任者が同一である他の認定事業計画がないかどうかが審査対象となります。これは、不適切な分割による認定取得の不正を防ぎ、適正な事業実施を確保するための重要な基準です。平成29年度内に認定を取得する場合は、審査期間を平成29年4月1日まで遡って確認する必要があります。分割の疑義が生じた際には、登記簿謄本や公図などの追加資料の提出が求められる場合があります。この審査基準は、土地利用の効率性と事業計画の透明性を確保する上で重要な役割を果たしています。
2. 標識の掲示に関する認定基準と審査基準
再生可能エネルギー発電設備を設置する際には、外部から見やすい場所に事業者名等を記載した標識を掲示することが義務付けられています。これは、発電事業者に関する情報を地域住民に明確に示し、透明性を確保するためです。ただし、太陽光発電設備で出力20kW未満、かつ屋根置き設置の場合はこの限りではありません。平成29年度内に認定を取得する場合は、平成29年4月1日まで遡って同一の事業者であることを確認する必要があります。必要書類として、設備所在地の登記簿謄本が提出を求められます。この標識の掲示は、地域住民との良好な関係構築や、事業内容の周知に貢献する重要な要素であり、適切な情報開示を促す役割を果たしています。審査においては、標識の設置状況が確認され、不備があれば是正が求められます。申請書類の不備によって認定が却下される可能性があるため、正確な情報と書類の提出が重要です。
3. 保守点検及び維持管理に関する認定基準と審査基準
再生可能エネルギー発電設備の適切な保守点検と維持管理は、安定的な電力供給と設備の長寿命化に不可欠です。そのため、認定基準として、適切な保守点検及び維持管理に必要な体制を整備し、実施することが求められています。審査基準においては、保守点検及び維持管理の責任者が明確にされていること、そして具体的な保守点検及び維持管理計画が明確に示されていることが重要視されます。これらの基準は、設備の安全な運用と環境保全に寄与するものであり、事業者の責任ある運営を促すためのものです。計画の妥当性や実行可能性なども審査の対象となり、不備があれば是正を求められる可能性があります。この審査基準は、発電設備の長期的な安定稼働を確保し、安全性を担保するために非常に重要な役割を果たします。
4. 設備の廃棄に関する認定基準と審査基準
再生可能エネルギー発電設備の寿命が尽きた際、または事業廃止の際には、適切な廃棄計画が求められます。認定基準では、発電設備の廃棄その他の事業廃止時の設備取扱いに関する計画が適切であることが求められています。審査基準は、必要書類が揃っているかどうかが中心となります。必要書類には、土地登記簿謄本が含まれ、他者所有地の場合は賃貸借契約書等(土地所有者の同意書でも可、ただし認定取得後一定期間内に契約書等の提出が求められ、未提出の場合は認定取消しの対象となる)の提出が求められます。この基準は、環境への負荷を最小限に抑え、安全かつ適切な廃棄処理を行うことを目的としています。廃棄計画の不備は認定の取消しにつながるため、事業者は十分な準備と計画を立てる必要があります。環境配慮と法的責任の両面から、適切な廃棄計画の策定と実行が強く求められています。
5. 地熱発電を継続的かつ安定的に行うための措置
地熱発電の場合、継続的かつ安定的な発電を確保するための特別な措置が求められます。具体的には、地熱資源の性状及び量の把握を運転開始前から継続的に行うこと、その他必要な措置を講じることなどが挙げられます。事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること、電気事業者の接続への同意を得ていること、設備が基準に適合していることも重要な条件となります。これらの措置は、地熱資源の持続可能な利用と発電設備の安定運用を確保するために不可欠です。地熱資源は有限であるため、その有効活用と環境への影響を最小限に抑えるための計画が求められます。この項目は、地熱発電特有の課題と、それに対する具体的な対応策を示しています。
III.FIT価格目標と入札制度
改正FIT法では、電源毎に中長期的な価格目標を設定し、事業者のコスト低減を促しています。入札制度は、再生可能エネルギー発電設備の調達価格を入札によって決定する仕組みです。入札参加者は、事業計画を提出し、資格審査を受けます。入札対象案件の接続契約については、落札後の認定取得後まで支払期限の延長が可能です。大規模太陽光発電については、地域との共生のための取り組みが求められます。保証金制度(第1次保証金500円/kW、第2次保証金5,000円/kW)も導入されています。落札後の事業変更については、原則として認めないこととされ、大幅な変更はペナルティが科せられます。
1. FIT法改正による価格目標の設定
FIT法の改正により、電源ごとに中長期的な価格目標が設定されるようになりました。これは、事業者の努力やイノベーションによるコスト低減を促すことを目的としています。調達価格等算定委員会が示した具体的な価格目標が、資料には記載されているものと思われます(具体的な数値は本文からは読み取れません)。この価格目標の設定は、再生可能エネルギーの導入コストを抑制し、国民負担の軽減に繋がることを目指しています。平成29年4月以降も、旧認定の効力が一定期間維持される猶予対象案件については、従来どおりの調達価格のルールが適用されます。太陽光発電の場合、接続契約日または接続申込日の翌日から270日後の早い日が平成29年度であれば、平成29年度の調達価格が適用されます。太陽光発電以外の場合は、接続申込日または認定日の遅い日が平成29年度であれば、平成29年度の調達価格が適用されます。この価格設定ルールは、既存事業者への配慮と新規事業者への明確な基準を示す役割を果たしています。
2. 入札制度の導入と入札実施指針
再生可能エネルギー電気の調達価格を決定する新たな仕組みとして、入札制度が導入されました。新FIT法第4条第1項では、経済産業大臣が再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格(供給価格)についての入札により認定事業者を決定できることが規定されています。入札実施指針には、入札対象となる再生可能エネルギー発電設備の区分、入札量、参加者の資格基準、保証金の額と提供方法、供給価格の上限額、調達価格の決定方法、調達期間、認定申請期限などが定められます。入札参加者は、入札前に再生可能エネルギー発電事業計画を提出し、参加資格の審査を受けます。接続契約を事前に締結し、系統工事のコストを確定した上で応札額を決定したいというニーズに対応するため、落札後の認定取得後まで支払期限を延長できる措置も設けられています。大規模太陽光発電の場合は、地域との共生のための取り組み(自治体への事業計画説明、他法令の許認可手続きの確認など)が事前に求められます。ドイツなどの例を参考に、第1次保証金は500円/kW、第2次保証金は5000円/kWと設定され、正当なプロセスを経た事業者には全額返金されます。落札結果の公表から1ヶ月以内に認定申請が義務付けられ、原則として落札後3ヶ月以内に認定を取得することが求められます。
3. 入札後の事業変更の取扱い
入札制度では、落札後速やかな認定取得が求められるため、認定取得前の事業変更は原則として認められません。認定取得後、事業内容が大幅に変わるような変更(事業中止、大幅な出力減少など)は、第2次保証金を全額没収し、認定を失効させることになります。これは、他の事業者によるコスト効率的な再生可能エネルギー導入を妨げるためです。一方、事業計画段階からの事情変更を考慮し、応札量に対して20%までの出力減少については、減少分相当の保証金を没収した上で事業実施が認められます。落札後の出力増加は、入札量を超過する可能性があるため、一切認められません(第2次保証金全額没収+認定失効)。速やかな運転開始を促すため、事業計画に記載された運転開始予定日までに運転開始した案件については第2次保証金が返金され、予定日を超過した場合は没収されます(ただし、FITの適用は継続)。この節では、入札制度における事業変更に関する規定、特に落札後の変更に対する厳格な対応について詳しく述べられています。
IV.送配電買取と買取義務者
改正FIT法では、FIT電気の買取義務者が、小売電気事業者から送配電事業者に変更されました。3月31日までに締結された既存の買取契約は、契約期間満了まで有効です。送配電事業者は、全社共通の送配電買取要綱を定め、公平・平等な条件で買取を行う必要があります。計画値同時同量制度との整合性を保つため、FITインバランス特例が設けられています。小売買取を継続するための条件、特定契約の変更、回避可能費用の算定方法など、送配電買取に関する詳細なFAQも掲載されています。
1. 買取義務者の変更と送配電買取
改正FIT法においては、FIT電気の買取義務を負う電気事業者が、送配電事業者(一般送配電事業者と特定送配電事業者)に変更されました。これは、再生可能エネルギー電力の買取をより公平・公正に行うためです。平成29年3月31日までに締結された買取契約(特定契約)は、改正法施行後も契約期間満了まで有効であり、小売買取を継続することが可能です。一般送配電事業者については、全社が再生可能エネルギー電気卸供給約款を経済産業大臣に届け出ています。送配電事業者は、特定契約の申込を原則として拒否することができません。特定契約の基本4要件(当事者、設備、買取期間、買取価格)いずれかの変更は、新規契約締結と同様に見なされます。既存の小売買取契約において、小売事業者の事情で4要件いずれかの変更を行う場合は、慎重な対応が求められます。送配電事業者は、平等・公平の条件でFIT電気の買取を行うことが求められており、全社共通の「送配電買取要綱」を定め、国は内容と買取の適切性を確認します。小売買取を前提とした既存のモデル契約書は、平成29年4月1日以降廃止されます。この買取義務者の変更は、再生可能エネルギー導入拡大における重要な転換点であり、電力システム全体の改革に大きく影響します。
2. 送配電買取と小売買取の連携と特例
送配電買取においても、計画値同時同量制度とFIT(全量買取)との整合性を保つため、FITインバランス特例が設けられています。この特例では、FIT発電事業者の代わりに送配電事業者または小売電気事業者が発電計画を作成し、インバランスリスクを負うことになります。原則として送配電買取は回避可能費用の激変緩和措置の対象外となりますが、小売に帰責性がない場合は、小売買取と激変緩和措置は維持可能です。複数の小売事業者の一部が契約から離脱した場合、残された小売事業者に帰責性がない限り、離脱部分のみを送配電買取の対象とする、部分買取量の変更、全量買取への移行などが認められます。既存の小売買取契約において、発電設備の増設・減設を行う場合、特定契約の基本要件(認定設備)が変化しますが、小売事業者の事情ではないため、特定契約の変更が許容されます。増設分は別契約とすることも可能で、認定と激変緩和措置も同様の扱いです。当事者間の合意があれば、全体を送配電買取の対象とすることも可能です。この節では、送配電買取と小売買取の連携、既存契約への対応、そして様々な特例措置について解説されています。
3. 回避可能費用と激変緩和措置
回避可能費用とは、FIT電気の買取義務者がFIT電気の調達によって支出を免れた費用を指します。平成28年4月の電力小売全面自由化に伴い、回避可能費用単価の算定方法は、従来の総括原価方式から市場価格連動へと見直されました。そのため、送配電買取における回避可能費用もスポット市場価格となります。小売買取では、小売事業者にとってのFIT電気の調達価格が回避可能費用となるため、市場価格連動への見直しに伴い5年間の激変緩和措置が講じられています。一定の条件を満たすものについては、従来の算定方法が維持されます。既存の部分買取(小売買取)で一部小売事業者が契約から離脱する場合、残された小売事業者に帰責性がない限り、離脱部分のみを送配電買取、部分買取量の変更、全量買取への移行などを認めます。ただし、残された小売事業者に帰責性がある場合は、この限りではありません。発電設備の増設・減設の場合も、小売事業者の事情ではないため特定契約の変更を許容し、増設分は別契約とすることも可能です。この節では、回避可能費用の定義、算定方法の変更、そして激変緩和措置について説明されています。
4. FAQ 送配電買取関係
このセクションは、送配電買取に関するよくある質問と回答(FAQ)で構成されています。主な質問と回答の内容は、小売買取を継続するための要件(改正法施行までに運転開始は不要)、送配電買取要綱以外の条件での特定契約締結の可否(公平・平等が求められるため原則不可)、複数の小売事業者による1つのFIT電源からの再生可能エネルギー電気卸供給の可否(可能)、バイオマス混焼における平成29年4月1日以降の買取義務者(FIT電気は送配電、非FIT電気は状況による)などです。これらのFAQは、事業者が送配電買取制度を理解し、スムーズに手続きを進めるために役立つ情報を提供しています。特に、小売買取継続の条件に関する回答は、既存事業者にとって重要な情報となります。また、送配電買取要綱遵守の重要性と、国による買取の適切性確認が強調されています。
V.地域別導入状況と接続プロセス
資料には、2016年から2017年にかけて、複数の地域(岩手県宮古久慈エリア、長崎市琴海エリア、福島県南エリアなど)で再生可能エネルギー発電設備の接続案件募集が行われたことが記載されています。各エリアの募集開始日と予定接続時期の情報が含まれています。電源接続案件募集プロセスは、標準処理期間が1ヶ月程度とされていますが、数ヶ月を要する場合もあります。事業計画提出に必要となる接続契約を証する書類については、資源エネルギー庁HPで公開予定です。
1. 地域別電源接続案件募集状況
この資料では、2016年から2017年にかけて実施された複数の地域における再生可能エネルギー発電設備の電源接続案件募集状況が示されています。具体的には、岩手県宮古久慈エリア、長崎市琴海エリア、福島県南エリア、宮崎県都城エリア、福島県白河エリア、宮崎県日向・一ツ瀬エリア、青森県八戸エリア、大分県速見エリア、福島県矢吹石川エリア、大分県西大分エリア、新潟県村上エリア、大分県日田エリア、東北北部エリア、鹿児島県霧島エリア、宮城県白石丸森エリア、鹿児島県大隅エリア、福島県浜通り南部エリア、熊本県人吉エリア、熊本県御船・山都エリア、群馬県西部エリア、鹿児島県入来エリア、栃木県北部・中部エリア、宮崎県紙屋エリア、山梨県北西部エリア、福岡県北九州市若松響灘エリア、千葉県南部エリアといった広範囲にわたる地域で募集が行われました。各エリアの募集開始日と予定接続時期(2017年6月中旬頃~2018年9月下旬頃)が記載されており、地域ごとの導入状況の一端を示しています。これらの情報は、再生可能エネルギーの地域的な導入状況を把握する上で重要なデータとなります。資料全体から、全国的に再生可能エネルギー導入が進められている状況が伺えます。
2. 電源接続案件募集プロセスと経過措置
電源接続案件の募集プロセスは、申込みから決定まで標準で約1ヶ月とされていますが、実際には数ヶ月かかる場合もあると注意喚起されています。そのため、早期の申込みが推奨されています。このプロセスにおける遅延などを考慮し、経過措置を希望する事業者には、早期にプロセス開始申込みを行うよう促しています。事業計画提出の際に必要となる接続契約を証する書類については、電力会社ごとに具体的な書類名が整理され、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」で近日中に公開予定であると明記されています。事業計画が提出され、内容と接続契約の締結が確認できた案件には、メールで通知される仕組みになっているようです。このプロセスにおける手続きや必要な書類、そしてタイムラインに関する情報が提示されており、事業者にとって重要な情報がまとめられています。特に、接続契約に関する書類の入手方法や確認方法などは、事業計画の策定において重要なポイントとなります。
3. みなし認定事業者と事業計画提出方法
既に接続契約を締結済み(発電開始済みを含む)の案件で、新FIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに契約を締結済みの事業者は、「みなし認定」として扱われ、新認定制度による認定を受けたものとみなされます。ただし、平成29年3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として認定が失効します(一部例外あり)。みなし認定事業者は、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に、新FIT法に基づき認定を受けた場合と同等の事業計画を提出する必要があります(特例太陽光を除く太陽光10kW未満も対象)。この事業計画の提出は、インターネット上で行うことが可能で、電源や出力規模に関わらず全ての対象者に適用されます。提出方法、提出項目、必要な添付書類などは、資源エネルギー庁HPで3月中旬に正式に発表される予定です。接続契約締結前に申請した場合、接続契約書は締結後に速やかに提出する必要があり、内容確認後に認定されます。この節では、みなし認定事業者に対する事業計画提出方法に関する詳細な情報が提供されています。特に、インターネット上での手続きの簡素化が強調されています。
