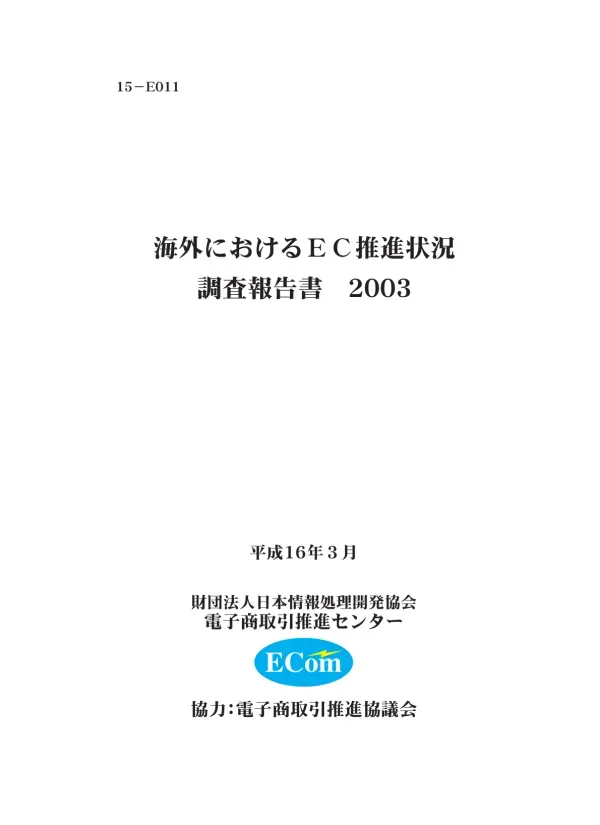
世界EC市場調査報告書
文書情報
| 専攻 | 経済学、経営学、情報学など関連分野 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.82 MB |
概要
I.世界各国のE レディネスと経済低迷の影響
本資料は、世界各国のE-レディネス状況と、経済低迷が電子商取引(電子商取引)を含むデジタル経済に及ぼす影響について分析しています。特に、ブロードバンド普及率や政府のITインフラ整備政策といった要因が、各国間のE-レディネス格差に影響を与える様子が示されています。アメリカ、中国、韓国、ドイツ、フランス、イギリスなど主要国の事例を通して、経済状況とオンラインショッピングの普及状況、B2BおよびB2C市場の成長率などを分析。経済低迷に見舞われたスイス、オーストラリア、カナダ、メキシコ、インド、ロシアなどでは、政治的混乱も相まってデジタル経済の成長が鈍化している様子が示されています。一方、中国は経済成長を継続しており、政府の積極的な政府政策によって電子商取引の発展が期待されています。
1. E レディネスの現状と経済低迷の影響
多くの国でブロードバンドサービスの普及やモバイル市場の拡大、政府によるIT関連支援プログラムによって、前年比でE-レディネススコアが向上しています。しかし、スイス、オーストラリア、カナダ、メキシコ、インド、ロシアなど、前年よりランクを落とした国々では、政治的混乱や不況により経済全般、ひいてはEビジネスも停滞していることが指摘されています。特にカナダやメキシコのように米経済に依存度の高い国は、米経済の低迷による貿易量や投資額の減少の影響を大きく受けています。このことから、E-レディネスは経済状況と密接に関連しており、経済の低迷はデジタル経済の成長を阻害する大きな要因となっていることがわかります。 政府によるIT関連投資やインフラ整備の政策は、E-レディネス向上に大きく貢献していますが、経済状況の悪化によってその効果が薄れる可能性も示唆されています。 世界的な経済情勢の変化が、各国のE-レディネスに直接的な影響を及ぼしていることが、この分析から明らかになります。
2. 各国のE レディネスと政府政策
資料では、韓国の「IT強国e-コリア」構想における成功例が紹介されています。1996年の情報化促進基本計画に基づき、2000年12月には当初計画より2年前倒しで全国144カ所の重要地域にブロードバンド網を敷設し、800万世帯以上が利用、全国の小中高校1018校が無料利用できる環境を実現しました。ITU調査では2003年3月末時点でDSL普及率が29.2%で世界一位となりました。これは、政府の積極的な政策とITインフラ整備への投資が効果的に機能した好例です。対照的に、一部の先進国では、アメリカ、日本、イギリス、ドイツなどに比べ、フランスの情報化レベルが低いことが指摘されており、ITUの調査でも相対的に低い位置付けとなっています。各国のE-レディネスは、政府のIT政策の積極性や、ブロードバンドなどのインフラ整備状況に大きく左右されることがわかります。このことは、政府のIT政策が、デジタル経済の活性化、ひいてはE-レディネス向上において重要な役割を果たしていることを示唆しています。
3. 電子商取引市場の現状と課題
アメリカでは、フォレスター・リサーチ社は2003年のB2C小売売上高を957億ドルと発表し、2008年には2300億ドルに達すると予測しています。特に食料雑貨、スポーツ用品、家庭用品のオンライン販売が伸びると見込まれています。一方、中国では、インターネット人口の31.7%が電子商取引に参加していますが、先進国に比べ低い水準です。中国のB2B市場では、ハイアール(40億元)、パンジョン(38億元)などがトップ企業として挙げられていますが、市場全体としては初期段階であり、企業の情報化レベルが低いことが課題となっています。また、B2C市場では、オフラインでの購買が主流であり、オンラインショッピングが日常生活に浸透するには、安全性、信頼性、配送時間、決済方法などの課題を克服する必要があります。ネチズンがオンラインショッピングをしない主な理由として、安全性と製品の信頼性、配送時間、決済方法の不便さが挙げられており、特に決済方法やアフターサービス、企業の信用に関する問題は増加傾向にあります。中国市場では、低価格帯の商品がオンラインでよく購入され、高価格帯の商品へのオンライン購買は進んでいません。
II.アメリカにおける電子商取引の現状と予測
アメリカでは、フォレスター・リサーチ社の予測によると、2008年までにB2C小売売上高が年間19%増加し、2300億ドルに達するとされています。オンラインショッピングにおいては、食料雑貨、スポーツ用品、家庭用品などが特に成長が見込まれています。また、2003年にはインターネット税モラトリアムを恒久化する法案が可決されるなど、政府はデジタル経済の成長を後押しする政府政策を推進しています。
1. フォレスター リサーチ社の予測とB2C市場の成長
フォレスター・リサーチ社は、2003年の米国のB2C小売売上高を957億ドルと発表し、2008年までに年間19%の成長率で2300億ドルに達すると予測しています。これは、電子商取引が2008年には小売売上高全体の約10%を占めるとの予測にも裏付けられています。同社は、特に食料雑貨類、スポーツ用品(特に中古品)、家庭用品などが、従来の書籍や旅行関連商品・サービスを追い越す勢いで売上を伸ばすと推測しています。この予測は、アメリカにおける電子商取引市場の旺盛な成長を示しており、具体的な商品カテゴリーまで言及することで、その成長の具体的な姿を描き出しています。 この予測は、今後のマーケティング戦略やビジネスプラン策定において重要な指標となるでしょう。
2. 電子商取引市場における主要商品カテゴリー
フォレスター・リサーチ社の分析によると、アメリカにおける電子商取引市場では、食料雑貨、スポーツ用品(特に中古品)、家庭用品といった商品カテゴリーが、今後特に高い成長が見込まれています。これらの商品は、従来からオンライン販売が盛んだった書籍や旅行関連商品・サービスを追い越す勢いで成長すると予想されています。これは、消費者の購買行動の変化や、これらの商品カテゴリーにおけるオンライン販売の利便性の向上を反映した結果と考えられます。 従来型の小売業態にとどまらず、オンラインでの販売戦略を積極的に展開していく必要性が示唆されています。 特に、中古スポーツ用品のようなニッチな市場におけるオンライン販売の成長は、今後の市場動向を把握する上で注目すべき点です。
3. 政府の電子商取引関連政策
2003年9月、アメリカ下院はインターネット税モラトリアムを恒久化する法案(Internet Tax Nondiscrimination)を可決しました。これは、アメリカ政府が電子商取引の活性化に向けて、インターネット関連税制において、ビジネスの成長を阻害しないよう配慮している姿勢を示しています。この政策は、クリントン・ゴア政権下の1997年7月1日に発表された「グローバルな電子商取引のための枠組み(A Framework for Global Electronic Commerce)」を端緒として、デジタル社会の実現と繁栄を目指した様々な施策の一環として位置づけられます。 1998年のデジタル・ミレニアム著作権法、1999年の統一電子処理法、2000年の子供オンライン・プライバシー保護法、電子署名法など、電子商取引関連の法律も制定されています。これらの法整備は、電子商取引の健全な発展と、消費者保護の両面において重要な役割を果たしています。 政府の積極的な政策が、アメリカにおける電子商取引市場の成長を支えている一因と言えるでしょう。
III.韓国のE レディネスとIT政策の成功例
韓国は「IT強国e-コリア」構想のもと、情報化促進基本計画を策定し、ブロードバンド網の全国展開を成功させました。2000年12月には当初計画より2年前倒しで全国144カ所の重要地域にブロードバンド網を敷設、DSL普及率は世界一位となっています。このように韓国は積極的な政府主導のITインフラ整備と政府政策によって高いE-レディネスを実現しています。
1. IT強国e コリア 構想と情報化促進基本計画
韓国は1996年、「IT強国e-コリア」構想を実現するため、情報化促進基本計画を策定し、2010年までの段階的計画を着実に実行しています。その一環として、ブロードバンドインターネット網の全国展開を推進し、2000年12月には当初計画より2年前倒しで、全国144カ所の重要地域にブロードバンド網を敷設しました。この積極的な政策により、数年前にはごく少数の世帯にしか普及していなかったブロードバンド・インターネットが、現在では全世帯の半分以上である800万世帯以上に普及し、全国の小・中・高等学校1018校が無料で利用できるようになりました。これは、政府主導による強力な情報化推進政策が、国民生活や教育現場にまで浸透した成功例として挙げられます。 この計画の成功は、韓国の高度な情報化社会への転換を加速させ、経済成長にも大きく貢献したと言えるでしょう。韓国におけるブロードバンドインフラの整備は、世界でも先進的な事例として注目に値します。
2. ブロードバンド網の全国展開とDSL普及率
韓国の情報化促進基本計画における大きな成果として、ブロードバンド・インターネット網の全国展開が挙げられます。2000年12月には、当初計画より2年前倒しで全国144カ所の重要地域にブロードバンド網が敷設されました。この迅速な展開により、数年前にはごく一部の世帯しか利用していなかったブロードバンド・インターネットが、現在では800万世帯以上、全世帯の半分以上に普及するまでに至っています。さらに、全国の小・中・高等学校1018校が無料でブロードバンドを利用できる環境が整備されています。 ITUの発表資料によると、2003年3月末時点でのDSL(デジタル加入者網)普及率は、電話100回線あたり29.2%で世界一位となっています。この高い普及率は、韓国のE-レディネスの高さ、ひいてはデジタル経済の発展の土台となっています。韓国政府の積極的な政策と、民間企業の協力体制が、この成果に繋がったと言えるでしょう。 この成功事例は、他の国々におけるブロードバンドインフラ整備の政策立案において重要な参考資料となります。
IV.中国の電子商取引 発展と課題
中国の電子商取引市場は発展途上段階にあり、オンラインショッピングの普及率は先進国に比べて低いものの、成長の潜在力は高いと評価されています。しかし、コンピューター情報ネットワークの運用レベルや企業情報化レベルの低さ、セキュリティや認証制度の未成熟、英語の情報が主流であることなどが課題として挙げられています。政府は「企業インターネット接続プロジェクト」などを通して情報化を推進していますが、同時にインターネット利用の統制も強化しており、その二重性が発展を阻んでいます。B2B市場では、ハイアール(売上高40億元)やパンジョン(売上高38億元)などの企業が成功を収めています。決済面では、現金決済や現金前払いが一般的ですが、売掛金取引も多いのが現状です。個人情報保護も大きな課題となっています。
1. 中国電子商取引市場の現状と潜在力
中国の情報産業部(MII)の調査によると、中国のインターネット人口のうち電子商取引を行っている人口は31.7%で、先進国に比べて低いものの、発展速度と潜在力においては世界最高と評価されています。その理由として、中国の電子商取引の歴史が浅いこと、コンピュータ情報ネットワークの運用レベルや企業の情報化レベルが低いこと、セキュリティや認証、法律などの制度が未成熟であることが挙げられています。さらに、インターネット上の情報の大部分が英語であるため、多くのネチズンや企業が情報化の推進や習得に困難を感じていることも要因の一つです。 2002年の資料によると、中国のオンラインサービス提供企業は、オンライン卸売り型サイトが40%、オンライン取引28%、ソリューション提供12%、その他20%と分類され、B2B市場ではハイアール(40億元)、パンジョン(38億元)などが高売上高を記録しています。しかし、多くの企業が2年以内に電子商取引を始める計画を持っていないという現実も示されています。中国市場は、発展途上でありながら大きな成長の可能性を秘めている一方、多くの課題を抱えていると言えるでしょう。
2. 電子商取引普及の阻害要因 安全性 信頼性 決済方法
中国では、多様な分野のB2Cサイトが存在し、多くのネチズンがインターネットを通じて商品やサービスを購入していますが、オフラインでの購買が依然として主流です。インターネットショッピングが日常生活に占める割合はまだ高くなく、消費方法を大きく変えるには至っていません。ネチズンが電子商取引を利用しない主な理由として、安全性と製品の信頼性、配送時間、決済方法の不便さが指摘されています。セキュリティや個人情報保護に関する懸念、配送時間に関する不満は減少傾向にありますが、支払方法、アフターサービス、企業の信用に関する問題は増加傾向にあります。 オンラインショッピングの主な理由としては、時間の節約(48.5%)、費用の節約(43.67%)、利便性(42.4%)が挙げられ、珍しい製品の検索も動機となっています。購入される主な品目は書籍(69%)、オーディオ(38.3%)、コンピュータ関連製品(33.2%)など低価格帯の商品が中心で、高価格帯の商品はオンラインで購入されない傾向があります。これらの課題を解決することが、中国における電子商取引の更なる発展には不可欠です。
3. 中国政府のインターネット規制と電子商取引政策
中国政府は、インターネットが反国家・反社会的ニュースや世論を流布する可能性が高いと判断し、2002年11月からは未成年規制や利用者・接続情報記録に関する強力な規制法を施行しています。インターネットカフェでの検索サイトや情報コンテンツへの接続規制だけでなく、政治的に敏感なウェブサイトへの接続を事実上封鎖するなど、1995年以降60以上の関連法を制定・発表してきました。 一方で、WTO加盟後、電子商取引育成のための政府政策の効率化、安全で利便性の高い金融設備の整備、外国資本誘致のための規制緩和など、積極的な改善努力も行っています。「企業インターネット接続プロジェクト」では、100の大企業、1万の中企業、100万の小企業のインターネット接続を支援し、B2B市場の発展基盤となる企業の情報化レベル向上を目指しています。しかし、政府によるインターネット利用の統制強化と情報化推進の両面性、この二重構造が中国の電子商取引発展における大きな課題となっています。 政府の政策は、電子商取引の促進と規制の両面で、複雑な様相を呈しています。
V.欧州諸国 フランス ドイツ イギリス の電子商取引
フランスは、イギリスやドイツに比べてITインフラ整備レベルが比較的低いものの、オンラインショッピングの普及は進んでいます。ドイツはオンラインショッピング人口がアメリカに次いで世界第2位と高い水準にあります。イギリスは、電子商取引を世界最高の中心地とするビジョンを持ち、包括的な規制構造を整備し、政府政策によって電子商取引の活性化に力を入れています。3国とも電子政府の推進にも注力しており、政府政策によってデジタル経済を促進しています。
1. フランスのITインフラと電子商取引
フランスはヨーロッパの先進国であるにもかかわらず、イギリスやドイツと比較して、情報化とITインフラのレベルが相対的に低いとされています。IDC/World Timesの2002年の情報社会指数調査では、フランスは55カ国中20位と、アメリカ、日本、イギリス、ドイツなどの他国、さらには韓国やシンガポールなどのアジア諸国よりも低い評価でした。ITUの調査でも、通信インフラ、ネットワーク利用率、通信市場環境の3部門で評価された携帯電話・インターネット指数において、21位とイギリスやドイツより低いランクとなっています。 しかし、フランスのITインフラは他の先進国よりは低いものの、概して高いレベルを維持しており、2001年末時点のインターネットホスト数は78万8,897台、人口1万人あたり約132.94台となっています。 2000年時点では、中小企業の73%がオンライン化しており、EU全体のインターネット取引においても、フランスのB2C取引比率は8.8%、B2B取引比率は11%にまで上昇しています。(1998年はそれぞれ4.8%、5%)。
2. ドイツの電子商取引 高い普及率とオンライン消費額
ドイツでは2000年から商品・サービスのオンライン購入が活発化しており、ニールセン/ネットレイティングスの調査によると、2002年第3四半期までに人口の約52%がオンラインショッピングサイトを利用したことがあると報告されています。ドイツのオンライン利用者は12億ユーロをオンライン購入に費やしており、これは世界で2番目に高い数値です。TNS Interactiveの「グローバルeコマースレポート2002」によると、約3080万人の個人インターネット利用者の約28%がオンラインで商品・サービスを購入しており、これはアメリカに次いで世界2位、イギリスを上回るヨーロッパで最も高い比率(約33%対24%)となっています。 これらのデータは、ドイツにおける電子商取引の普及度が高く、消費者のオンラインショッピングへの積極的な姿勢を示しています。 ドイツはアメリカに次ぐオンラインショッピング大国であり、その市場規模の大きさが際立ちます。
3. イギリスの電子商取引戦略と政府の取り組み
イギリスは、自国を電子商取引の世界最高の中心地と位置づけ、EU加盟国との戦略的提携強化によって電子商取引の中心的役割を担うことを目指しています。包括的な規制構造を持ち、世界の電子商取引関連法・制度・政策の変化に柔軟に対応することで、IT、通信、放送関連分野において世界でも有数の競争力のある市場を維持しています。 政府は最高の電子商取引環境維持のための法・制度整備を支援し、活性化のための問題点の解決に努めています。2005年までにインターネットを利用するすべての人々が政府サービスをオンラインで利用できるようにすることを目標に、3種類の目標プログラムを設定しています。また、2002年までにG7諸国の中でB2B、B2C電子商取引比率を最高レベルに引き上げるため、関連機関や産業界と共同で研究、マーケティング、通信戦略の策定を積極的に行っています。 e-Envoy(特使)を任命し、政府の電子商取引関連議題と戦略を提示するなど、政府の積極的な姿勢が伺えます。
VI.国際機関における電子商取引に関する議論
OECD、WTOなどの国際機関は、電子商取引拡大のための国際的な規範整備、個人情報保護、決済システムの標準化、データ保護法の整備などに関する議論を活発に行っています。国境を越えた個人情報保護、電子認証、税制などの問題が主要な論点となっています。特に、データ保護に関するEUのデータ保護指令や、アメリカのHIPAA、Gramm-Leach-Bliley法などの影響が各国の政策に現れています。
1. 国際機関における電子商取引論議の共通認識
OECD、WTO、W3Cなどの国際機関は、電子商取引の拡大に向けた世界的な障害要因の除去や、電子商取引に適合した国際的な規範の制定について議論しています。 これらの機関は、電子商取引に必要な最小限の環境整備は政府が行うべきものの、創造的な民間部門の主導的な役割を重視するという基本原則で一致しています。 議論の中心となるテーマは、情報通信インフラの整備、電子商取引に関わる公共政策・法律・制度、そして技術インフラ(セキュリティ、認証、決済など)の3つの軸に集約されます。 グローバルな電子商取引の発展には、各国政府と民間セクターの協調と、国際的な標準化・規制が不可欠であるという認識が、これらの機関の議論を通して共有されています。
2. OECDにおける電子商取引論議の3つの柱
OECDにおける電子商取引論議は、3つの柱を中心に展開されています。 第一は、有線通信網、CATV網、TV、コードレス通信、衛星通信など、インターネット基盤施設を中心とした情報通信インフラです。第二は、個人情報保護、市場アプローチ、情報利用価格、租税など、電子商取引にかかわる公共政策、法律、制度といった社会的インフラです。第三は、ネットワーク内の技術的標準やセキュリティ、認証、代金決済などの主要な技術を構成要素とした技術インフラです。 これらのインフラ整備と、適切な法整備・政策立案、そして技術標準化が、安全かつ効率的な電子商取引環境を構築するために必要不可欠であるという認識が、OECDの議論を支えています。 特に、個人情報保護に関するOECDプライバシーガイドライン(1980年)とその電子商取引への適用に関する議論は、国際的なプライバシー保護基準確立において重要な役割を果たしています。
3. WTO物品貿易理事会での議論とペーパーレス貿易
WTO物品貿易理事会では、「電子送信」の法的性格(サービスか商品か、あるいは第3の類型か)に関する議論が主要な議題となっています。関税、分類、関税評価、原産地、輸入許可など関連事項よりも優先して解決すべき問題として認識されています。 様々な問題点に関して合意が得られないことから、1999年3月には、それまでの非公式会議での議論内容を「議長要約書」としてまとめ、一般理事会に中間報告として提出しました。 その後、加盟国による検討が行われましたが、新たな意見は出されず、1999年7月に同報告書が物品貿易理事会の最終結果として一般理事会に提出されました。 APEC事務局は、第6回ECSG会議でペーパーレス貿易実現のための個別行動計画(IAPs)の履行報告書を提出しており、各国の計画提出状況、ウェブサイト登録計画、今後の措置などが報告されています。 国際的な電子商取引の拡大には、貿易における様々な規制や法的枠組みの明確化と国際的な協調が不可欠であることが示されています。
