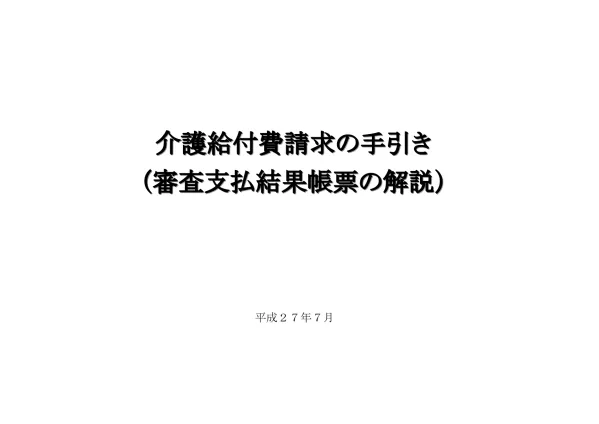
国保連合会 処理日程とエラーコード対応
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 9.10 MB |
| 専攻 | 介護保険 |
| 文書タイプ | マニュアル |
概要
I.介護給付費請求におけるエラーと対応
本資料は、国民健康保険団体連合会への介護給付費請求明細書提出における様々なエラー(ANN4エラー、ANNMエラー、AEF0エラー、ASS5エラー、ASS6エラーなど)とその原因、対応策を解説しています。 主なエラー原因は、給付管理票と請求明細書の情報不一致、被保険者情報の誤り、保険者への情報登録漏れ・誤り、支給限度基準額超過などです。返戻された場合は、エラー内容を精査し、修正または再請求が必要です。 給付管理票の修正は「修正」で、新規作成は「新規」で提出します。 保険者(市町村)への照会が必要なケースが多く、要介護状態区分、保険者番号、被保険者番号の正確性が重要です。 特定のエラー(例:ANN4)は、過去の請求と重複していることを示し、再請求前に過誤手続きが必要となる場合があります。
1. 介護給付費請求における主要なエラーと対応
このセクションでは、介護給付費請求における代表的なエラーとその対応策について詳述しています。具体的には、ANN4エラー(既に該当する介護給付費給付実績が存在しています)、ANNMエラー(前月以前に同じ介護給付費を請求し、給付管理票と突合審査を行った結果全額マイナス(0決定)しているのに再請求した場合)といったエラーコードを中心に解説しています。ANN4エラーは、過去に同一内容の請求が既に支払済であることを示し、再請求を行うには、まず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で取下げ(過誤)が完了していることを確認する必要があります。過誤が決定されないうちに再請求すると、ANN4エラーが発生し、請求は返戻となります。一方、ANNMエラーは、給付管理票と照合した結果、既に全額マイナス(0決定)となっているにも関わらず再請求した場合に発生します。この場合も、再請求の前に、エラー原因を特定し、適切な対応を行う必要があります。 その他、AEF0エラー、ASS5エラー、ASS6エラーなど、様々なエラーコードとその原因、対応策についても触れられています。これらのエラーは、給付管理票と請求明細書の情報不一致、被保険者情報の誤り、保険者への情報登録漏れ・誤り、支給限度基準額超過などが主な原因として挙げられています。 各エラーへの対応策としては、請求明細書や給付管理票の確認、保険者(市町村)への照会、修正、再請求などが含まれます。 請求明細書に誤りがなければ、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに連絡し、給付管理票の修正を依頼する必要があります。 減単位(0単位)となった請求明細書は、0円決定されているため再請求は不要です。 保険者番号や被保険者番号の誤入力についても言及されており、正しい情報に修正して再請求する必要があるとされています。
2. 給付管理票と請求明細書の不一致に関するエラーと対応
この部分では、給付管理票と請求明細書の内容が一致しないことによって発生するエラーとその解決策について説明しています。 具体的には、給付管理票にサービス事業所の実績(計画単位数)が記載されていない場合(事由記号=A)、または、給付管理票の実績を請求明細書が上回っている場合(事由記号=B)にエラーが発生します。事由記号Aの場合は、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票に実績を追加してもらう必要があります。この際、給付管理票は「修正」として提出します。事由記号Bの場合は、請求単位数は給付管理票の計画単位数に修正されます。 また、請求明細書と給付管理票の不一致によって発生する他のエラーについても言及されており、これらのエラーは、特定入所者介護サービス費の請求がある場合に顕著に現れると指摘されています。具体的には、請求明細書のサービス種類が給付管理票に記載されていない場合、または、請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合にエラーが発生する可能性があります。これらのケースにおいても、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票の修正を依頼することが重要となります。請求明細書の内容に誤りがなければ、給付管理票に実績を追加してもらい、「修正」で再提出する必要があります。 返戻となった請求明細書は再請求が必要になります。 書類の不備によるエラーを未然に防ぐためには、請求前に請求明細書と給付管理票の内容を徹底的に照合することが重要です。
3. 被保険者情報に関するエラーと対応 認定変更 資格問題など
このセクションでは、被保険者情報の不備や変更申請に関するエラーとその対応策について説明しています。 具体的には、利用者の受給者証の情報と、請求書に記載された保険者番号や被保険者番号が異なる場合、または、市町村の認定情報と不一致がある場合にエラーが発生します。市町村の認定情報との不一致は、支援事業所番号、計画作成区分などで発生し、保険者(市町村)が国保連合会に登録している情報と請求明細書の情報に差異がある場合に起こります。 対応策としては、利用者の受給者証などで認定日、喪失日を確認し、保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)へ照会することが挙げられています。特に、保険者番号、被保険者番号の誤入力は、他の利用者の情報と混同する可能性があり、注意が必要です。 また、要介護認定の変更申請中であるにもかかわらず請求した場合、または、特定入所者にかかる申請中である場合もエラーが発生します。この場合は、保険者(市町村)に照会し、変更申請が確定した後に再請求する必要があります。保険者の国保連合会への受給者情報の登録期限と事業者の請求書提出期限のずれもエラーの原因となるため、事業者は当月の請求までに変更申請が確定していることを確認する必要があります。 旧措置入所者特例対象者かどうかなども確認が必要です。 要介護度の把握ミスによるサービスコードの誤入力、市町村認定の要介護度との不一致などもエラーの原因となり、この場合は保険者への照会が必要になります。 これらのエラーを回避するには、被保険者情報の正確性と、変更申請状況の把握が不可欠です。
4. 請求金額 負担限度額に関するエラーと対応
このセクションでは、請求金額や負担限度額に関するエラー、具体的にはASS5エラー(請求金額等計算値超過)とASS6エラー(市町村認定の負担限度額と相違)について説明しています。ASS5エラーは、特定入所者介護サービス費の保険及び公費請求額と利用者負担額が審査により検算した値を超えている場合に発生します。ASS6エラーは、保険者(市町村)が国保連合会に登録している利用者の特定入所者負担限度額と事業所が請求明細書に入力している負担限度額が異なる場合に発生します。これらのエラーは、請求明細書と給付管理票の内容が不一致で、かつ、特定入所者介護サービス費の請求がある場合に起こりやすいとされています。 主な原因として、請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力されていない場合や、請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合が挙げられます。 対応策としては、まず請求明細書のサービス内容に誤りがないかを確認し、誤りがなければ居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡して給付管理票の修正を依頼する必要があります。 請求明細書が返戻になっている場合は、再請求が必要です。 支給限度基準額超過についても言及されており、給付管理票のサービス計画合計単位数と償還払いのサービス利用単位数の合計が、保険者が国保連合会に登録している利用者の要介護度に対する支給限度基準額を超えている場合にエラーとなります。この場合も、合計単位数と支給限度額をまず確認する必要があります。
II.給付管理票と請求明細書の不一致によるエラー
給付管理票と請求明細書の内容不一致は、多くのエラー(返戻)の原因となります。 主な原因は、サービス事業所番号の相違、請求明細書に記載されたサービスが給付管理票に反映されていないことなどです。対応としては、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票の修正を依頼する必要があります。請求明細書のサービス年月やサービスコードに誤りがないか確認する必要があります。 減単位された請求明細書は、0円決定の場合、再請求は不要です。
1. 給付管理票に実績が記載されていない場合のエラー
請求明細書に係る被保険者の給付管理票が、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターから提出されているにも関わらず、該当するサービス事業所のサービス実績(計画単位数)が給付管理票に入力されていない場合、エラーが発生します。これは、給付管理票作成時の入力ミス、または、事業所番号の変更などに起因する可能性があります。このエラーが発生すると、確定単位数は0単位となり、一覧表の内容欄に0と表示されます。このエラーを解消するには、サービス事業所が給付管理票に実績を追加する必要があります。具体的には、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票の修正(「修正」として提出)を依頼する必要があります。 請求明細書に記載されているサービス年月やサービスコードに誤りがないか確認する必要があります。修正された給付管理票が提出されると、減単位されていた金額がサービス事業所に支払われます。 このエラーは、請求明細書と給付管理票の情報の一貫性を確保する上で非常に重要であり、関係各所との連携が不可欠であることを示しています。事前に、請求明細書の情報と給付管理票の情報が一致しているかを確認することで、このようなエラーを予防できます。
2. 給付管理票の実績を超える請求の場合のエラー
請求明細書の請求単位数が、提出済みの給付管理票に記載されている計画単位数を超える場合、エラーが発生します。この場合、給付管理票に記載されている計画単位数が確定単位数となります。つまり、請求明細書に記載された単位数よりも少ない単位数で決定されることを意味します。 このエラーは、請求前に給付管理票の計画単位数を必ず確認することで防ぐことができます。請求単位数を給付管理票の計画単位数と照合し、超過分を修正する必要があります。 このエラーは、請求明細書の作成段階で、給付管理票の情報と請求内容の整合性を確認する重要性を示しています。 請求前に、給付管理票に記載された計画単位数を確認し、請求単位数と比較することで、このようなエラーを回避することが可能です。 請求明細書と給付管理票の情報の一致は、正確な介護給付費請求において非常に重要であり、関係者間の綿密な連携が必要となります。
3. 特定入所者介護サービス費請求時の不一致エラーと対応
特定入所者介護サービス費の請求がある場合、請求明細書と給付管理票の内容が不一致だとエラーが発生します。このエラーは、請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力されていない場合、または、請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合に起こります。 国保連合会では、通常2ヶ月間請求情報を保留しますが、この保留期間内に給付管理票が提出されれば支払が行われます。しかし、保留期間内に給付管理票が提出されないと請求明細書は返戻となります。 対応策としては、まず請求明細書のサービス年月やサービスコード等に誤りがないかを確認します。誤りがなければ、該当利用者の居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票に実績を追加してもらう必要があります。この際、給付管理票は「修正」で提出します。 請求明細書が返戻となっている場合は再請求が必要となります。 このエラーは、特定入所者介護サービス費の請求において、請求明細書と給付管理票の情報の正確性と一貫性が特に重要であることを示しています。 関係各所との情報共有と連携を強化することで、このエラーの発生を抑制することができます。
III.被保険者情報に関するエラーと対応
被保険者情報の誤りや変更申請中の状態もエラー(特にAEF0エラー、12PAエラー)の原因となります。 保険者が国保連合会に登録している情報と、請求明細書の情報に不一致がある場合に発生します。 被保険者証の情報と照合し、必要に応じて保険者に照会し、情報の修正を依頼する必要があります。要介護状態区分、認定有効期間、保険者番号、被保険者番号の確認が重要です。 変更申請中の場合は、申請が確定するまで再請求できません。
1. 保険者番号 被保険者番号の誤りによるエラー
請求明細書または給付管理票に、保険者番号や被保険者番号を誤って入力した場合、エラーが発生します。これは、単純な入力ミスや、他の利用者の情報と混同したことが原因と考えられます。このエラーが発生した場合、正しい保険者番号と被保険者番号に修正して再請求する必要があります。 既に正しい請求明細書が返戻されている場合は、誤って入力した請求明細書を取り下げ(過誤)処理した後、介護給付費過誤決定通知書で取下げが完了したことを確認してから、正しい保険者番号と被保険者番号で再請求する必要があります。 取下げ依頼は該当の保険者に対して行う必要があります。通常、取下げ依頼から介護給付費過誤決定通知書に記載されるまで2~3ヶ月かかります。 このエラーを避けるためには、請求前に保険者番号と被保険者番号を必ず確認し、正確に入力することが非常に重要です。 特に、複数の利用者の情報を扱う際には、細心の注意を払う必要があります。 入力ミスによるエラーを減らすためには、入力支援システムの活用や、入力内容の二重チェックといった対策が有効です。
2. 市町村の認定情報との不一致によるエラー
保険者(市町村)が国保連合会に登録している情報と、請求明細書または給付管理票の情報が一致しない場合、エラーが発生します。具体的には、支援事業所番号、被保険者番号、計画作成区分などが市町村の認定情報と異なる場合にエラーとなります。 このエラーの原因としては、保険者(市町村)が国保連合会に登録している情報に登録漏れや誤りがある場合、または、市町村の認定情報自体に誤りがある場合があります。 対応としては、まず請求した事業所が利用者の居宅支援事業所として該当月以前に保険者(市町村)に届出をしているかを確認する必要があります。届出がされていない場合は、請求できません。 計画作成区分に関しても、保険者(市町村)が国保連合会に登録している受給者台帳の情報と一致しているか確認する必要があります。「自己作成」となっている場合もエラーになります。 このエラーを回避するためには、請求前に保険者(市町村)に確認し、最新の情報と照合することが不可欠です。 市町村と国保連合会との情報連携の重要性を改めて認識させるエラーと言えます。
3. 要介護認定変更申請中などのエラーと対応
要介護認定の変更申請中、または特定入所者の申請・変更申請中であるにも関わらず請求した場合、エラーが発生します。平成17年10月サービス分以降は、「要介護認定」と「特定入所者」の両方の申請状況を確認する必要があります。どちらか一方でも申請中であればエラーとなります。 このエラーは、保険者の国保連合会への受給者情報の登録期限(通常は前月末までの異動情報を当月の4日までに提出)と、事業者の請求書提出期限(通常は10日)のずれによって発生することがあります。 対応策としては、該当の保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)に照会し、変更申請(または更新申請)が確定(却下を含む)し、受給者情報に登録されたことを確認の上、再請求する必要があります。 このエラーは、保険者と事業者間の情報共有の遅れや不備が原因となるため、両者の連携強化が重要となります。 申請状況の確認を徹底し、申請が確定してから請求を行うことで、このエラーを未然に防ぐことができます。
4. 市町村認定の要介護度とサービス内容の不一致によるエラー
請求明細書に記載されたサービス内容のサービスコードが、保険者(市町村)が国保連合会の受給者台帳に登録している該当被保険者の要介護度では算定できない場合、エラーが発生します。 このエラーの原因としては、変更申請などにより該当被保険者の要介護度の把握を誤っていたために、入力したサービスコードが受給者台帳登録の要介護度と異なっていることが考えられます。 対応としては、まず請求に誤りがないかを確認し、誤りがなければ該当の保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)に受給者台帳に登録されている要介護度を照会する必要があります。 請求に誤りがあった場合、または保険者への照会結果に基づき請求した要介護度に誤りがあった場合は、正しいサービスコードを入力して再請求します。保険者に受給者台帳の修正を依頼する必要がある場合もあります。その場合は、請求明細書は訂正せず再請求します。 このエラーは、サービスコードと要介護度の整合性を常に確認する必要性を示しており、保険者との綿密な連携が重要となります。
IV.支給限度基準額超過と償還払いに関するエラー
給付管理票のサービス計画合計単位数と償還払いの単位数の合計が、支給限度基準額を超えるとエラーが発生します。これは要介護状態区分の誤りや、保険者が国保連合会に登録している情報と相違がある場合に起こります。 支給限度額と合計単位数をチェックし、利用者の要介護度を確認する必要があります。償還払いの単位数は、利用者または保険者に確認する必要があります。
1. 支給限度基準額超過によるエラー
給付管理票のサービス計画合計単位数と償還払いのサービス利用単位数の合計が、保険者が国保連合会に登録している利用者の要介護度に対する「支給限度基準額」を超えている場合、エラーが発生します。このエラーは、証記載保険者番号、給付管理票種別区分、被保険者番号、給付合計単位数・日数といった情報がエラーメッセージに含まれる場合があります。 エラーの原因は、給付管理票に記載されている要介護度と、保険者が国保連合会に登録している要介護度が異なる場合に発生する可能性があります。給付管理票上では誤りがないように見えても、保険者の登録情報が異なればエラーとなるため、利用者の要介護度についても確認が必要です。 対応策としては、まず合計単位数と「支給限度額」をチェックし、利用者の要介護度を確認します。「支給限度額」は、給付管理票に入力されている要介護度ではなく、保険者が国保連合会に登録している要介護度によって決定されます。 償還払いの単位数については、利用者または該当の保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)に確認する必要があります。 このエラーは、保険者と事業者間の情報共有の重要性、特に要介護度の情報の一致を強調しています。
2. 特定入所者介護サービス費における請求金額 負担限度額エラー
特定入所者介護サービス費に関するエラーとして、ASS5エラー(利用者負担額、保険分請求額:請求金額等計算値超過)とASS6エラー(負担限度額、保険分請求額:市町村認定の負担限度額と相違)が挙げられます。ASS5エラーは、保険及び公費請求額と利用者負担額の合計が審査により検算された値を超えている場合に発生します。 ASS6エラーは、保険者(市町村)が国保連合会に登録している利用者の特定入所者負担限度額(食費・居住費/第1段階~第3段階)と、事業所が請求明細書に入力している負担限度額が異なる場合に発生します。 これらのエラーは、請求明細書と給付管理票の内容が不一致で、かつ、特定入所者介護サービス費の請求がある場合に起こりやすく、請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力されていない場合や、請求事業所と給付管理票の記載事業所番号が異なる場合などが主な原因です。 対応としては、請求明細書と給付管理票の情報の一致を確認し、不一致があれば給付管理票を修正してもらう必要があります。 このエラーは、特定入所者介護サービス費の請求における、請求金額と負担限度額の正確な計算と、請求明細書と給付管理票の一貫性の重要性を示しています。
V.その他エラーと対応
その他、事業所台帳、サービス台帳の情報不一致、市町村の認定情報との不一致、算定できないサービスの請求、重複請求などもエラー原因となります。 これらのエラーに対処するには、関係書類の情報を確認し、必要に応じて保険者、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどに連絡し、情報の修正を依頼する必要があります。 再請求の前に、エラー内容を正確に理解し、適切な対応を行うことが重要です。
1. 事業所情報に関するエラーと対応
このセクションでは、事業所に関する情報(事業所番号、サービス種類など)の不備によって発生するエラーについて説明しています。 事業所基本台帳、サービス台帳、事業所台帳といった登録情報との不一致が原因でエラーが発生することがあります。具体的には、事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効または存在しない場合、指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効または存在しない場合、事業所基本台帳の指定・基準該当サービス区分コードと一致しない場合などが挙げられます。 また、サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表に該当する情報が存在しない場合もエラーとなる可能性があります。 さらに、請求先の公費負担者番号が事業所からの請求に使用できない場合、指定・基準該当等サービス台帳の施設等の区分コードや人員配置区分コードと一致しない場合もエラーとなります。 サービス提供体制に関するエラーもあります。例えば、認知症専門棟、送迎体制、特定事業所加算(訪問介護)、ユニットケア体制、在宅・入所相互利用体制、ターミナルケア(看取り看護)体制、小規模拠点集合体制、準ユニットケア体制、障害者生活支援体制といった体制が不足している、または、体制の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がない場合などにエラーが発生します。これらのエラーへの対応は、事業所情報の確認、関係台帳への登録状況の確認、都道府県への照会などが含まれます。
2. その他の請求関連エラーと対応
このセクションでは、事業所情報以外で発生する様々なエラーと対応について述べられています。 例えば、居宅サービス計画費の値が統一されていない場合、公費負担者番号は設定されているのに公費受給者番号または公費給付率が設定されていない場合、基本情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しない場合、様式番号とサービス種類の不整合がある場合など、請求明細書自体に不備がある場合にエラーが発生します。 また、既に同内容の請求書が存在する場合(介護給付費請求書、別紙、総合事業費請求書など)、介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書の情報が重複している場合、同月に同じ請求書が提出済みの場合などもエラーになります。 さらに、要介護状態区分コードが有効な値ではない場合、口座名義人に使用できない文字がある場合、審査済みの申請に要介護区分に事業対象者が設定されている場合、保険及び公費請求額と利用者負担額の合計が審査により再計算した総額と異なる場合、再審査の申立点数が当初請求時のサービス点数を超えている場合などもエラーとして挙げられます。 これらのエラーへの対応は、エラー内容の確認、関係書類の修正、再請求、保険者への照会など、エラーの内容によって異なります。 複数の市町村独自加算の請求、算定期間外のサービス提供、ターミナルケア加算に必要な情報の不足、初期加算算定に必要な情報の不足、介護予防サービスに関するエラーなど、様々なケースが想定されます。
3. 国保連合会における保留と返戻
国保連合会では、通常2ヶ月間請求情報を保留します(保留期間は各県によって異なります)。この保留期間中に該当の給付管理票が提出されれば支払いが行われますが、提出されなければ請求明細書は返戻となり、備考欄に「返戻」と表示されます。 返戻の原因としては、給付管理票と請求明細書の内容不一致(サービス種類、事業所番号の不一致など)が挙げられます。 対応としては、該当利用者の居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票の国保連合会への提出を依頼します。給付管理票が提出されれば、請求明細書の再請求は不要です。しかし、給付管理票が提出されなければ、請求明細書を再請求する必要があります。 このセクションは、国保連合会の審査プロセスにおける保留と返戻の仕組みを説明し、事業者側がとるべき対応策を明確に示しています。特に、保留期間内の給付管理票の提出状況が、請求の成否を大きく左右することを示唆しています。
