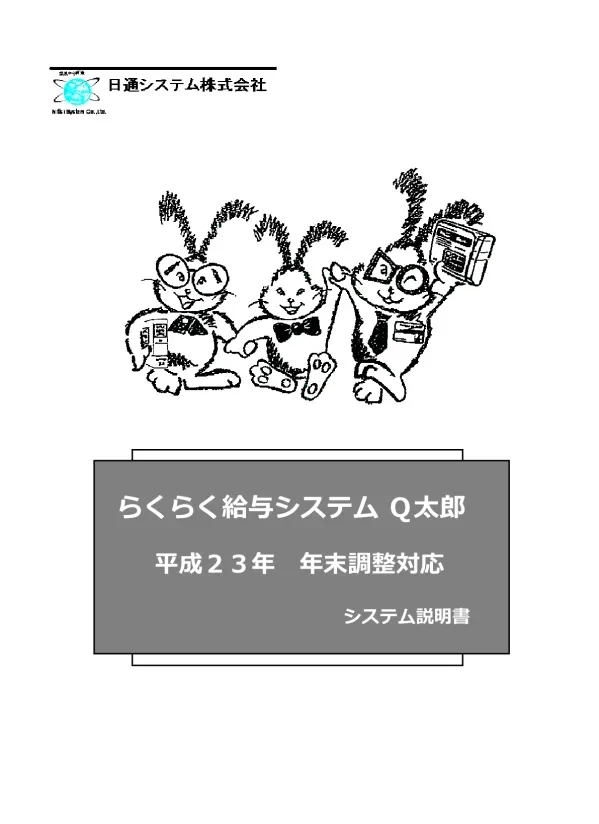
年末調整ガイド|Q太郎操作手順
文書情報
| 会社 | らくらく給与システム Q太郎 |
| 文書タイプ | マニュアル |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.63 MB |
概要
I.平成23年度 年末調整処理手順と重要事項
この資料は、らくらく給不システムQ太郎を用いた平成23年度の年末調整処理に関する手順書です。源泉徴収税額計算、扶養親族情報入力、配偶者特別控除、住宅借入金等特別控除などの重要な控除項目の設定方法、そして源泉徴収票の出力方法を解説しています。特に、源泉徴収税額は年齢16歳未満の扶養親族が障害者である場合の計算方法が変更されている点に注意が必要です。システム導入前のデータ処理方法についても説明があり、導入前データの入力方法として3つの方法が提示されています。給与計算と賞与計算の両方に対応しており、年末調整エラーリストによるデータチェック機能も備えています。
1. 平成23年度 年末調整における源泉徴収税額の計算
このセクションでは、平成23年度の年末調整における源泉徴収税額の計算方法について説明しています。特に、16歳未満の扶養親族が障害者(特別障害者を含む)または同居特別障害者に該当する場合の計算方法に焦点を当てています。従来の計算方法では、扶養親族の数に1人を加えて計算していましたが、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の額が変更されています。具体的には、1人につき75万円(特別障害者である場合は40万円に35万円を加算した額)が控除されることになりました。この変更点は、年末調整計算において重要な要素であり、正確な税額計算のために、システムがこれらの新しいルールを正しく反映していることを確認することが重要です。また、給与と賞与の処理方法についても言及されており、給与年調と賞与年調の場合の明細書印刷に関する注意事項が記載されています。給与・賞与処理は通常通り行われますが、給与明細書や賞与明細書の印刷は行わないように指示されています。システムの「給不(賞不)」-「支給入力フルスクリーン/マトリクス(賞不入力フルスクリーン/マトリクス)」画面では、通常の所得税額が表示されることが明記されています。このセクションは、年末調整における税額計算の正確性を確保するための重要なガイダンスを提供しています。
2. システム導入前のデータ処理方法
このセクションでは、平成23年度の途中で給与計算システムを導入した場合の、導入前のデータ処理方法について解説しています。システム導入前にさかのぼる給与データはシステム上に存在しないため、これらのデータを新たに作成し、システムに反映させる必要があります。文書では、導入前データの作成方法として3つの方法が提示されています。1つ目は、1月から導入前月までの給与合計を導入前の1ヶ月の給与として明細データを作成する方法です。2つ目は、1月から導入前月までの明細データを各月ごとに作成する方法です。3つ目は、「賞与入力」機能を用いて、導入前月までの給与金額を合計し、新たな賞与として入力する方法です。それぞれの方法について詳細な設定手順が別途記載されていると明記されています。また、賞与は年4回まで登録可能であり、4回分の賞与をすでに支給済みの場合は、1つ目または2つ目の方法で設定する必要があると記載されています。このセクションは、システム導入後のスムーズな年末調整処理を実現するために、導入前のデータ処理を適切に行うための重要な手順を示しています。特に、システム導入時期が途中である場合、正確なデータ反映は年末調整の正確性に直結するため、注意深く対応する必要があります。
3. 年末調整エラーの処理と過不足額の反映
このセクションは、年末調整処理におけるエラー処理と過不足額の反映方法について説明しています。「年末調整エラーリスト」を用いて、エラーデータの抽出と出力を実行し、寡婦控除等の限度額超過チェックを行い、必要に応じて修正を行う必要があることを示しています。「反映元データ」として「本年度過不足額」を選択し、明細一覧表で反映結果を確認します。給与または賞与の所得税欄には過不足額を加味した金額が反映されますが、「給与(賞与)」-「支給入力フルスクリーン/マトリクス(賞与入力フルスクリーン/マトリクス)」画面では、所得税の金額は過不足額を加味していない金額が表示されるという重要な注意点が記載されています。過不足額に関するより詳細な情報は、別冊のQ&A集を参照するように指示されています。このセクションは、年末調整処理において発生する可能性のあるエラーや過不足額を適切に処理するための手順を明確に示しており、年末調整の正確性を維持するために重要な役割を果たしています。エラーチェックと修正、そして過不足額の反映は、正確な税額計算と源泉徴収票の作成に不可欠なプロセスです。
II.個人情報マスタメンテナンスと年末調整計算
正確な年末調整計算を行うには、正確な個人情報の設定が不可欠です。「メンテナンス」メニューの「個人情報マスタメンテナンス」画面で、社員の基本設定(氏名、カナ、年末調整計算区分、源泉徴収票提出区分など)、配偶者情報(氏名、生年月日、配偶者障害区分、老人控除対象など)、そして扶養親族情報(氏名、続柄、生年月日、扶養区分、障害者区分)を正確に入力する必要があります。扶養親族が多い場合は、氏名のみ入力することも可能です。個人情報の更新後は必ず再計算を行う必要があります。
1. 個人情報マスタメンテナンス 基本情報の設定
このセクションでは、正確な年末調整計算を行うために必要な個人情報の設定方法について説明しています。システムの「メンテナンス」→「個人情報マスタメンテナンス」→「基本設定1」画面において、社員の基本情報を設定する必要があります。具体的には、社員の氏名、カナ(半角カナ入力)、そして年末調整計算区分を設定します。年末調整計算を行う場合は、『計算する』を選択します。さらに、源泉徴収票を税務署に提出する場合は、『提出する』を選択し、この選択によって「源泉徴収票合計表」内の提出者数にカウントされます。 生年月日を入力することで、老人控除対象配偶者かどうかが自動的に判定されます。控除対象配偶者が障害者の場合は、配偶者障害区分にチェックを入れ、『一般』または『特別』を選択します。これらの設定項目は、年末調整計算の精度に直接影響を与えるため、正確な情報を入力することが重要です。入力ミスによる計算誤りを防ぐため、入力を終えるたびに内容を確認することが推奨されます。特に、源泉徴収票提出区分の設定は税務処理上重要であり、誤った設定は税務上の問題につながる可能性があるため注意が必要です。この基本情報の正確な設定は、年末調整プロセスの基礎となります。
2. 個人情報マスタメンテナンス 配偶者と扶養親族の情報入力
このセクションでは、配偶者と扶養親族に関する情報の入力方法について説明しています。配偶者情報としては、氏名、生年月日、そして70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」にチェックを入れます。配偶者が障害者の場合は、障害区分(『一般』または『特別』)を選択する必要があります。扶養親族については、「扶養者詳細入力画面」で、氏名、続柄、生年月日、扶養区分、障害者区分を入力します。扶養親族が多い場合は、氏名のみを入力することも可能です。詳細な設定方法は、別冊資料の「3.補足事項」の「①扶養親族の追加について」と「②扶養親族の削除について」を参照するよう指示されています。扶養親族の情報の正確性は、年末調整における控除額の計算に直接影響を与えるため、正確な情報を入力する必要があります。特に、生年月日や扶養区分、障害者区分などは、控除対象の判定に重要な要素となるため、注意深く入力する必要があります。入力する情報は、関連する申告書の内容と一致していることを確認することが重要です。 また、扶養親族の追加や削除に関する手順も別途資料を参照することで、システムを効率的に利用できるようになっています。
3. 年末調整計算と再計算の必要性
このセクションでは、年末調整計算の実行と、個人情報更新後の再計算の必要性について説明しています。年末調整計算を行う前に、入力した個人情報が正確であることを確認することが重要です。個人情報の更新を行った場合は、必ず「年末調整」→「年末調整計算」で再計算を行う必要があります。再計算を行わないと、源泉徴収票には変更前の情報が出力されてしまい、税務処理上の不備につながる可能性があります。再計算が必要となるのは、個人情報、特に配偶者や扶養親族に関する情報の変更、または控除に関する情報の変更を行った場合です。これらの変更は、年末調整計算結果に影響を与えるため、正確な源泉徴収票を作成するために再計算を行うことが不可欠です。再計算の手順はシンプルで、「年末調整」→「年末調整計算」を選択するだけで実行できますが、この手順を踏むことで、正確な年末調整結果と税務処理が保証されます。このセクションは、正確な年末調整処理を確保するために、再計算の重要性を強調しています。
III.給与所得者の保険料控除申告書と住宅借入金等特別控除申告書
年末調整に必要な社会保険料控除額、配偶者特別控除額、住宅借入金等特別控除額の入力には、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』と『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』の情報を使用します。特に住宅借入金等特別控除については、控除可能額や複数の適用がある場合の摘要欄への出力方法が詳細に説明されています。国民年金保険料等の金額も重要な入力項目です。
1. 保険料控除額と配偶者特別控除額の入力
このセクションでは、年末調整に必要な保険料控除額と配偶者特別控除額の入力方法について説明しています。入力の根拠となるのは、『給不所得者の保険料控除申告書 兼 給不所得者の配偶者特別控除申告書』です。この申告書に基づき、年末調整に必要な社会保険料控除額、保険料控除額、そして配偶者特別控除額を入力します。特に、「うち国民年金保険料等の金額」については、申告書に記載されている社会保険料のうち、国民年金保険料に該当するものの合計額を入力する必要があります。国民年金保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金がある場合は、その金額を正確に入力することが重要です。配偶者特別控除額については、配偶者の合計所得金額を入力すると自動計算されます。この合計所得金額の計算方法は、申告書表面の早見表、または裏面の計算方法を参照することで確認できます。これらの控除額の正確な入力は、年末調整計算の正確性に直結するため、申告書の内容を十分に確認し、正確な数値を入力する必要があります。入力ミスは、税額計算の誤りにつながるため、細心の注意を払って作業を進めることが求められます。
2. 住宅借入金等特別控除額の入力
このセクションは、住宅借入金等特別控除額の入力方法について解説しています。入力の根拠となるのは、『給不所得者の住宅借入金等特別控除申告書』です。この申告書に基づき、年末調整に必要な住宅借入金等特別控除額を入力します。具体的には、「給不所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「(新築又は購入)居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」欄にある合計金額を入力します。さらに、新築または購入した家屋の居住開始年月日も入力する必要があります。住宅借入金等特別控除額が算出税額ですべて控除できる場合は、金額は表示されません。満額控除されている場合は、源泉徴収票の摘要欄に記載する必要はありません。しかし、控除可能額があり、複数の住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合、摘要欄には「居住開始年月日」の後に、住宅借入金に関する情報(控除の種類、年末残高)が出力されます。このセクションは、住宅ローン控除に関する情報を正確に入力し、年末調整を正確に行うための重要な手順を示しています。特に、複数の控除の適用や控除額の算出方法について理解しておくことが重要です。
3. 配偶者合計所得金額と配偶者特別控除額の自動計算
このセクションは、配偶者合計所得金額と配偶者特別控除額の入力と自動計算について説明しています。「給不所得者の配偶者特別控除申告書」の「配偶者の合計所得金額(①~⑦の合計額)」を入力すると、配偶者特別控除額が自動的に計算されます。配偶者の合計所得金額の計算方法は、申告書表面の早見表、または裏面の「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算について」を参照することで確認できます。この自動計算機能は、入力の手間を軽減し、計算ミスを防ぐのに役立ちます。しかし、入力するデータの正確性は依然として重要であり、申告書の内容と入力内容の一致を確認することが不可欠です。 配偶者に関する情報の正確な入力と、システムによる自動計算機能の活用によって、年末調整における配偶者特別控除の計算を効率的かつ正確に行うことができます。この自動計算機能は、システムの大きな利点の一つであり、ユーザーの負担を軽減し、年末調整業務の効率化に貢献します。
IV.源泉徴収票出力設定と摘要欄出力内容
源泉徴収票の出力設定では、「対象者」「対象年度」「出力順」「出力条件」を設定します。摘要欄には、中途入社者の前職分情報や、住宅借入金等特別控除に関する情報(控除の種類、年末残高、居住開始年月日)が出力されます。住宅借入金等特別控除が満額控除されている場合は、摘要欄への記載は不要です。また、使用する帳票に「居住開始年月日」の表記がある場合とない場合で出力内容が異なります。16歳未満の扶養親族を出力するかどうかを選択することもできます。出力前にプレビューを確認できます。
1. 源泉徴収票出力設定
このセクションでは、源泉徴収票(給与支払報告書)の出力設定方法について説明しています。システムの「年末調整」→「源泉徴収票(単票)/源泉徴収票(連続用紙)」画面で、「対象者」、「対象年度」、「出力順」、「出力条件」を設定し、「印刷」ボタンをクリックすることで、源泉徴収票を出力できます。出力形式として単票と連続用紙が選択可能です。出力前に、印刷イメージを確認したい場合は「問合せ」ボタンをクリックし、「源泉徴収票問合せ」画面で内容を確認できます。また、印刷位置を調整したい場合は、「オプション」ボタンをクリックして「単票印刷設定」または「連続用紙印刷設定」画面で調整できます。 出力設定においては、対象者や対象年度の正確な指定が重要であり、誤った設定は誤った源泉徴収票の出力につながるため注意が必要です。出力順や出力条件の設定によって、出力される源泉徴収票の並び順や内容が変化するため、目的に合った設定を行う必要があります。このセクションでは、源泉徴収票の出力に関する基本的な操作方法を説明しており、正確な源泉徴収票を出力するための重要な手順を示しています。
2. 源泉徴収票摘要欄の出力内容
このセクションでは、源泉徴収票の摘要欄に出力される内容について、いくつかのケースを挙げて説明しています。例えば、中途入社者で入社前に他の支払者から給与等を受け取っている場合、前職分情報(支払金額、徴収税額、社会保険料合計額)が摘要欄に出力されます。また、住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合、摘要欄には「居住開始年月日」の後に、住宅借入金に関する情報(控除の種類、年末残高)が出力されます。複数の住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合や、住宅借入金等特別控除可能額がない場合、または控除の種類が「特定増改築等」の場合など、様々なケースで摘要欄への出力内容が変化します。使用する源泉徴収票によって摘要欄の出力内容が異なるため、注意が必要です。さらに、摘要欄に記載できない情報がある場合、源泉徴収票の出力後に「記載不足者一覧」画面が表示され、不足している情報を確認できます。16歳未満の扶養親族を出力するかどうかについても設定できます。住宅借入金等特別控除額が算出税額ですべて控除できる場合は、金額は表示されません。このセクションでは、摘要欄に出力される情報の多様性と、その出力条件を明確にすることで、ユーザーが源泉徴収票の内容を正確に理解することを支援しています。
3. 源泉徴収票の 社会保険料等の金額 欄について
このセクションは、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄への記載内容について説明しています。年末調整入力で「小規模企業共済等掛金控除」の項目に金額を入力した場合、その金額が源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に内書きされます。この情報は、社会保険料に加えて、小規模企業共済等掛金控除の金額も記載されることを意味しており、年末調整における控除項目の反映状況を正確に把握するのに役立ちます。 このセクションは、源泉徴収票における社会保険料等の金額欄への記載内容について、簡潔に重要な情報を提示しています。小規模企業共済等掛金控除の金額が反映されるという情報は、年末調整処理における重要な補足事項であり、正確な源泉徴収票作成のために必要な情報です。この欄への記載は、税務署への提出書類としての源泉徴収票の正確性を担保する上で重要です。
V.システム情報
このシステムは日通システムが提供するらくらく給不システムQ太郎です。住所は名古屋市中区栄三丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル9階です。MS-Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。無断複製・改変は禁止されています。
1. システム名と提供会社
このセクションは、利用されているシステムと提供会社に関する情報を簡潔に示しています。利用されているシステムは「らくらく給不システム Q太郎」であり、これは給与計算と年末調整処理を支援するソフトウェアであることが文書全体から推測できます。提供会社に関する情報は、文書の末尾に記載されており、システムの無断複製や改変を禁止する記述と共に、住所(名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパーク ビジネスセンタービル9階)が明示されています。 システムの名前と提供元の住所を明確に提示することで、システムに関する問い合わせを行う際の連絡先を容易に特定することができます。また、無断複製・改変禁止の明記は、知的財産権保護の観点から重要な情報であり、ユーザーはこれらの条件を遵守する必要があります。この簡潔なシステム情報は、文書全体の信頼性を高める役割も担っています。
2. 使用ソフトウェアに関する補足情報
このセクションでは、システムの動作環境に関するわずかな情報が示されています。具体的には、「MS-Windowsは、米国マイクロソフト社の登録商標です。」という記述があります。これは、システムがMicrosoft Windows上で動作することを示唆しており、ユーザーは適切な動作環境を確保する必要があることを示しています。この情報は、システムを利用する上で必要となる基本的な環境条件を示すものであり、ユーザーがシステムを正しく利用するために不可欠な情報です。 ただし、記載されている情報はMicrosoft Windows環境に関するもののみで、他の動作環境に関する情報は提供されていません。このため、他のOS環境での動作可否については、別途確認が必要となります。この簡潔な補足情報は、システムの動作環境を理解する上で、重要な役割を果たしています。
