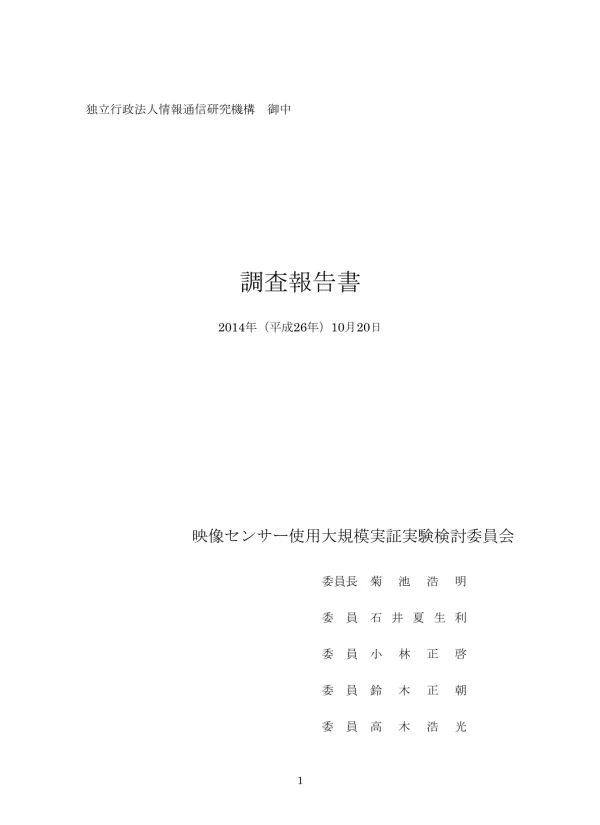
映像センサー実証実験の法的・倫理的検討
文書情報
| 著者 | 石井 夏生利 |
| 学校 | 情報通信研究機構 (NICT) |
| 専攻 | 情報科学、法学、社会科学 |
| 会社 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 840.31 KB |
概要
I.大阪駅における大規模映像センサー実験 プライバシー問題と法的検討
独立行政法人情報通信研究機構(NICT)は、JR西日本と協力し、大阪ステーションシティ(OSC)において、災害対策に向けた人流統計情報作成のための大規模映像センサー実験を実施予定でした。しかし、顔認証を含むこの実験は、プライバシー保護の問題から強い反発を受け、延期されました。本実験では、92台のデジタルビデオカメラを用いて、通行者の映像を収集し、特徴量情報(歩容、服装など)を解析して人流統計情報を作成する計画でした。個人情報保護法の観点から、肖像権やプライバシー権の侵害、個人識別のリスクが大きく懸念されました。特に、特徴量情報の保存期間や、他の情報との照合による個人特定の可能性が問題視されました。
1. 実験の概要と目的
NICTとJR西日本は、大阪ステーションシティにおける大規模映像センサー実験を計画しました。この実験の主たる目的は、災害発生時等の安全対策への実用に資する人流統計情報の作成可能性を検証することです。平成25年11月25日にはプレスリリースとNICTのウェブサイトで実験予告がなされました。実験には92台のデジタルビデオカメラ(映像センサー)が用いられ、通行する一般利用者を撮影し、そのデータから人流統計情報を作成する計画でした。具体的な手法としては、画像から個人を特定できない特徴量情報(歩容、服装など)を抽出し、属性ごとの人数をカウントするカウンティングや、特徴量情報から同一人物の移動経路を記録するマッチングが想定されていました。しかし、この実験計画は、個人情報保護に関する懸念から大きな反発を招き、延期されることになりました。南海トラフ地震を想定し、JR大阪駅周辺の帰宅困難者数が18万人と推定されていることから、この実験がもたらす人流データの災害対策への有効性が期待されていました。 NICTとJR西日本は、平成25年11月19日付の建物使用貸借契約を締結しており、その契約に基づき、NICTは特定の個人を識別できない情報をJR西日本に無償提供する義務を負っていました。
2. 公表後の反発と延期
実験計画の公表後、毎日新聞や朝日新聞など各紙が画像の取り扱いに関する懸念を報じました。「監視社会を拒否する会」はNICTに対し実験の中止を求める要請書を提出しました。これらの批判を受け、平成26年3月11日、NICTは実験の延期を発表しました。翌12日には、大阪市議会が個人情報やプライバシー保護を慎重に検討するよう求める意見書を可決しました。市民からの反発は、個人を特定されたり、年齢・性別などの属性情報が取得されたりする可能性、あるいは、たとえ特定されなくても行動が追跡されることに対する嫌悪感や、監視社会への恐怖感に基づくものでした。特に、顔画像や顔識別情報は生体情報であり、一度取得されると将来にわたる追跡やネット上への流出のリスクが高いという認識が、批判の背景にありました。 実験の延期は、データ活用と利用者保護の両立の難しさを改めて浮き彫りにしました。
3. 法的 倫理的な問題点
実験計画は、民法上の肖像権・プライバシー権侵害、独立行政法人等個人情報保護法違反の可能性を含んでいました。検討委員会は、肖像権侵害に関する裁判例(京都府学連事件など)を参考に、承諾なき撮影が原則禁止であるものの、公共の福祉に資する目的であれば例外的に許容される可能性があることを確認しました。プライバシー権については、『宴のあと』事件などの判例を踏まえ、私生活の不当な公開が問題となります。本実験においては、大阪ステーションシティという公共空間での撮影であること、そして特徴量情報は短時間での消去が予定されていたことから、プライバシー権の侵害は違法とは必ずしも言えないとされました。しかしながら、実験が利用者に萎縮効果を与える可能性や、特徴量情報の漏洩リスク、そして、情報管理体制の不備などが懸念事項として挙げられました。 これらの点を踏まえ、実験の法的・倫理的な妥当性について詳細な検討がなされました。
II.民法上の適法性 肖像権とプライバシー権の保護
実験の民法上の適法性を検討するため、肖像権とプライバシー権に関する裁判例が参照されました。肖像権については、承諾のない撮影が原則禁止ですが、公共の福祉のために必要な場合は許容される場合があるとされました。プライバシー権については、『宴のあと』事件などの判例を踏まえ、私生活の不当な公開が問題となります。本実験においては、大阪ステーションシティという公共空間での撮影であること、そして、特徴量情報は短時間での消去が予定されていたことから、プライバシー権の侵害は違法とは認められないと結論づけられました。しかし、利用者の萎縮効果への懸念も指摘されました。
1. 肖像権に関する裁判例と検討
本節では、肖像権に関する裁判例を分析し、本実証実験への適用可能性を検討しています。日本の裁判例においては、京都府学連事件が重要な先例となっています。この事件では、警察官によるデモ隊の写真撮影の合法性が争われ、最高裁判所は個人の承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めました。ただし、犯罪行為の証拠保全など、公共の福祉に資する目的であれば、撮影を許容する例外が認められると判示しています。 その他、写真週刊誌による被疑者や一般人の撮影・公開に関する下級審判例も紹介され、肖像権の保護範囲と、撮影の目的・方法・必要性などが総合的に考慮されるべきことが示されています。これらの判例を踏まえ、本実証実験における大阪ステーションシティ内での撮影行為が肖像権を侵害するかどうかが検討されています。 実験では、デジタルビデオカメラによる撮影が行われ、個人の容貌・姿態が捉えられる可能性があるため、肖像権との関係が重要な論点となっています。
2. プライバシー権に関する裁判例と検討
プライバシー権に関しては、『宴のあと』事件が重要な先例として挙げられています。この事件では、私生活の不当な公開がプライバシー権侵害として認められました。東京地方裁判所は、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義し、公開された内容が私生活上の事実またはそれに類するもの、かつ、当該個人が不快・不安を感じたことを要件としています。近年の裁判例では、プライバシーの対象となる情報は拡大傾向にあり、住民基本台帳データの漏洩や、週刊誌記事への情報提供などもプライバシー権侵害として扱われる事例があります。 本実証実験においては、特徴量情報や移動経路情報といった、個人を直接特定しない情報であっても、他の情報と組み合わせることで個人を特定できる可能性があるため、プライバシー権の保護範囲が議論の焦点となります。 特に、「とらわれの聞き手」事件における伊藤正己裁判官の補足意見が引用されており、公共交通機関利用時のような、撮影回避が困難な状況でのプライバシー権制限には慎重な考慮が必要であると指摘されています。大阪地裁の「あいりん地区」テレビカメラ設置事件の判例も参考に、プライバシー保護と公共の利益のバランスが検討されています。
3. 実証実験の適法性に関する結論
上記の裁判例や論点を総合的に勘案し、検討委員会は本実証実験の適法性を判断しています。一時的な画像撮影、特徴量情報、移動経路情報、そして人流統計情報の生成は、利用者のプライバシー権を違法に侵害するとは認められないという結論に至っています。この結論は、大阪ステーションシティという公共空間における撮影であること、特徴量情報は短時間で消去されること、そして、実験の目的が災害対策に資する公共性の高いものであることなどを考慮した結果です。ただし、この結論は、適切な情報管理体制が確立され、個人識別リスクが最小限に抑えられることを前提としています。 また、利用者の承諾を得るための周知方法の適切さも重要な要素として考慮されています。 利用者への事前の十分な説明と、撮影を回避するための手段の提供なども、実験の適法性確保に不可欠であると指摘されています。
III.個人情報保護法の観点からの検討
本実験は独立行政法人等個人情報保護法にも抵触する可能性がありました。映像情報の処理、人流統計情報のJR西日本への提供が問題となりました。特徴量情報は、個人を直接特定できない「識別非特定情報」と位置づけられましたが、時間経過後であっても、再入場時の特徴量情報と照合することで個人を特定できる可能性が残ります。そのため、個人情報の適切な加工と提供目的の明確化、そして、情報漏洩対策の徹底が求められました。NICTは、個人識別のリスクを市民に丁寧に説明する必要性も指摘されました。
1. 個人情報保護法上の問題点 データの取得 利用 提供
本節では、NICTが計画していた大阪ステーションシティ内での一般利用者の撮影、映像情報の電子処理、人流統計情報の作成、そしてJR西日本への提供といった一連の行為が、独立行政法人等個人情報保護法に抵触しないかどうかを検討しています。 特に、映像情報が消去された後であっても、同一人物が再度撮影され、過去の「特徴量情報」と照合されることで、個人を特定できる可能性が指摘されています。この場合、特定の個人を識別できる情報となり、個人情報保護法の対象となる可能性があります。しかしながら、NICTの説明によると、特徴量情報は移動経路情報生成後、遅くとも営業終了時に消去され、翌営業日以降は個人を特定することは困難であるとされています。 このため、NICTが保有する特徴量情報は「識別非特定情報」と解釈できる可能性も示唆されています。しかし、検討委員会は、時間経過を伴う場合でも、顔識別を含む情報システム全体を一体的に判断する必要があると指摘しています。 また、IT総合戦略本部が策定した「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」も参照され、個人特定性低減データの扱いについても議論されています。
2. 個人情報の定義と識別可能性の解釈
本実験における「映像情報」や「特徴量情報」などが個人情報に該当するかどうかは、個人を識別できるかどうかという点に依存します。 しかし、特徴量情報から元の画像を復元することは不可能であっても、特徴量情報に基づいて個人を識別することは技術的に可能であると指摘されています。さらに、特徴量情報が消去された後であっても、同一人物が再度撮影された場合、過去の記録と照合することで個人を特定できる可能性があります。 検討委員会は、このような時間的経過を伴う場合も含め、顔識別を含む情報システム全体の中で「個人情報」の該当性を一体的に判断すべきだと主張しています。 また、カメラに一度しか撮影されなかった利用者の特徴量情報についても、他の情報と照合することで個人を特定できる可能性があるため、個人情報として扱う必要があるとされています。このため、個人情報該当性の判断には、時間軸も含めた包括的な検討が必要であることが強調されています。
3. 実験の評価と今後の対策
本実証実験では、撮影用カメラが一般利用者から防犯カメラと区別できないように設置されていた点が問題視されています。そのため、実験の趣旨を明確に表示する必要性が指摘されています。表示を怠った場合は、情報取得の意思を秘した隠し撮りとなり、違法性の問題が生じる可能性があるとされています。 マスコミや市民団体からの批判、そして大阪市議会による慎重な検討を求める意見書採択などを踏まえ、NICTはプライバシー影響評価を誤り、公的団体としての説明責任を果たしていないとの批判を免れないと指摘されています。 検討委員会は、特徴量情報や移動経路情報などの取得はプライバシー権を侵害するものではないと結論づけていますが、その前提として、NICTは実験計画、目的、手段を市民に丁寧に説明し、個人識別リスクが低いことを明確にする必要性を強調しています。同時に、情報漏洩防止のための安全管理措置の徹底、撮影回避手段の提供、そして個人識別リスクの事前説明など、具体的な対策の実施と公表を求めています。JR西日本に対しても、独立行政法人等個人情報保護法に基づき、人流統計情報の利用目的を限定し、再識別を禁止するなどの措置が求められています。
IV.実験への提言と今後の課題
検討委員会は、実験の目的を明確化し(大規模災害発生時の避難誘導等の安全対策に活用すること、及び、その有効性の検証)、人流統計情報の提供に関する契約を明確にすることを提言しました。さらに、映像センサーの存在と稼働状況を分かりやすく表示すること、撮影を回避する手段の提供、情報漏洩防止のための安全管理措置の徹底、そして、個人識別のリスクに関する市民への事前説明の徹底などを求める結論となりました。 本実験は、顔認証技術を含む生体認証技術のデータ利活用とプライバシー保護のバランスを問う重要な事例となりました。
1. 個人情報保護法遵守のための課題 データの加工と提供目的の明確化
NICTによる映像データの取得、利用、およびJR西日本への提供は、独立行政法人等個人情報保護法の観点から厳格に検討される必要があります。特に、人流統計情報の作成過程で用いられる特徴量情報が、個人情報保護法の対象となるかどうかが重要な問題です。 NICTは、取得した映像を不可逆処理を行い、特定の個人が識別できない情報に変換すると説明していますが、特徴量情報から個人を識別できる可能性が否定できないため、その扱いに関する明確な基準が必要です。 検討委員会は、個人情報保護法第10条「保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求」に基づき、JR西日本への人流統計情報の提供に際し、利用目的を本実証実験の目的に限定し、再識別を禁止するなどの制限を付すことを提言しています。 また、IT総合戦略本部における「パーソナルデータに関する検討会」の結論も踏まえ、人流統計情報の加工方法と提供方法を検証し、適法な提供が行われるよう、厳格な基準の策定と運用が求められています。 データの加工方法によっては、適法な提供とは認められない可能性もあるため、その点についても慎重な検討が必要です。
2. 情報セキュリティと安全管理対策の徹底
たとえ個人を特定できないようにデータが加工されたとしても、情報漏洩のリスクは常に存在します。本実証実験では、特徴量情報などの個人情報がNICTの施設内で電子的に処理された後、速やかに消去される予定でしたが、情報セキュリティには絶対はなく、安全管理対策の徹底が不可欠です。 検討委員会は、情報漏洩の危険性を小さくするため、通信路の暗号化、サーバーへのアクセス制御など、システムとネットワークの安全管理措置を徹底するよう求めています。 サーバー機器の運用者に人が介在しない計画であること、大阪ステーションシティ内およびNICTデータセンター内のサーバー室に侵入防止措置が施されることなどを考慮すると、不正行為の確率は小さいと判断されていますが、それでも情報セキュリティ上のリスクは完全に排除できないため、万全の対策が求められます。 生体識別情報である映像情報や特徴量情報の取り扱いには、特に厳格な安全管理が求められるとされています。
3. 市民への情報提供と透明性の確保 実験方法の改善
本実証実験は、一般市民が撮影対象となる場所で実施されるにも関わらず、その目的や趣旨、プライバシーに関する影響が十分に説明されないまま計画が進められたため、市民に不安感を与えました。 検討委員会は、NICTが実験計画、目的、手段を市民に丁寧に説明し、個人識別リスクが僅少であることを明確にして不安の軽減に努める必要があると指摘しています。具体的には、映像センサーの存在と稼働状況を明確に表示し、撮影を回避できる手段を提供するなどの改善策が求められています。 また、実験実施のための手順やチェックリストを定めること、そして、得られた結果を市民に公表することも重要です。 NICTとJR西日本間の契約において、人流統計情報の利用目的が曖昧であった点も指摘されており、その目的を「大規模災害発生時の避難誘導等の安全対策に活用すること、及び、その有効性の検証」と明確化し、委託契約あるいは共同研究契約を締結するよう提言しています。 これにより、実験成果の目的外利用を防ぐとともに、実験の透明性を高めることが期待されます。
