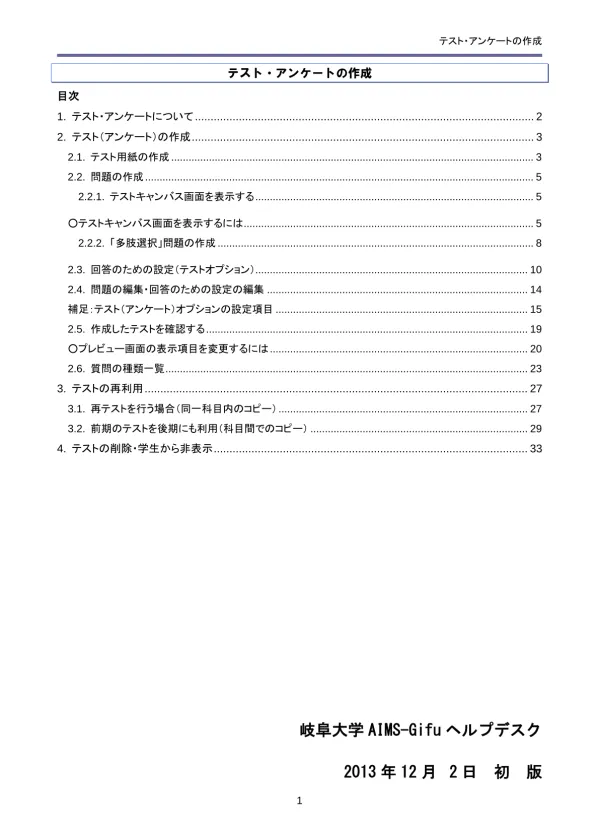
AIMS-Gifuテスト作成ガイド
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.39 MB |
概要
I.テスト作成と設定 オンラインテスト アンケート作成
このマニュアルは、AIMS-Gifu を使用したテスト作成とアンケート作成の手順を説明します。多肢選択問題を含む17種類の質問形式に対応しており、自動採点と手動採点の両方が可能です。テストオプションとして、試験時間制限、受験回数制限、フィードバックの設定、成績集計への反映などが可能です。Excelを用いた質問作成方法についても触れています。 表示期間やパスワードの設定も可能です。テストを学生に公開する際には「リンクを利用可能にする」オプションを使用します。
1. テスト用紙の作成
このセクションでは、AIMS-Gifu を用いたテスト作成の最初のステップであるテスト用紙の作成について説明されています。空の用紙を作成した後、問題を作成する手順が示されています。特に、多用される多肢選択問題の作成方法が詳細に解説されており、他の質問形式については、後述の質問形式一覧を参照するよう指示されています。 作業途中でブラウザを閉じても、テストキャンバス画面を表示させる方法も説明されています。この段階では、まだテストオプションの設定は行わず、問題の作成に焦点を当てています。 多肢選択問題以外にも、様々な種類の質問形式に対応しており、柔軟なテスト作成を可能にしていることが示唆されています。 Excel を利用した問題作成方法についても言及されており、効率的なテスト作成のためのツールとしての活用を促しています。
2. 回答のための設定 テストオプション
テスト作成後、学生がテストを受験できるようにするための設定、いわゆるテストオプションの設定について解説しています。 具体的には、テストの公開、連絡事項への表示、受験回数、公開日時の設定などが含まれます。 また、テストフィードバックの設定についても言及されており、正解・不正解時のフィードバックを表示させるかどうかを選択できます。 さらに、テストの表示期間を制限する機能や、パスワードによるアクセス制限機能、強制完了機能(テストの中断を許さない設定)についても説明があります。 複数試行の設定により、テストの受験回数を制限したり、回数無制限に設定することも可能であることがわかります。 時間制限を設定し、時間切れになった際に自動送信する機能も備えていることが記載されています。 これらのオプションを適切に設定することで、テストの実施方法を柔軟に調整できることが強調されています。
3. テスト アンケート アクセス設定とプレゼンテーション
このセクションでは、テストへのアクセス制御と、テストのプレゼンテーション方法に関する設定について説明しています。 テスト(アンケート)アクセス設定では、「リンクを利用可能にする」オプションを通して、学生がテストを受験できる状態にする方法が記述されています。カレンダーと時計のアイコンを利用した表示開始日と終了日の設定方法も説明され、日付と時刻の指定が容易に行えるようになっています。 パスワードの設定も可能で、セキュリティを強化することができます。 また、期限の設定と期限切れの警告機能も備えていることがわかります。 さらに、「このテストの結果をインストラクタおよび成績管理に対して完全に非表示にする」オプションにより、完全に自己評価のためのテストとして利用できることも示されています。 テスト(アンケート)プレゼンテーションでは、プレゼンテーションモードの設定について解説されており、一度に全ての質問を表示するか、1問ずつ表示するかの選択が可能です。1問ずつ表示する場合は、前の質問に戻れるかどうかも設定できます。 フィードバックの表示設定も可能で、学生へのフィードバックの可否を制御できます。 成績表への得点反映についても、オプションで制御できることが記述されています。
II.質問形式一覧と採点方法
AIMS-Gifu では、ファイル提出、画像の座標指定、正誤問題、数値計算、数式計算など17種類の質問形式が利用できます。各形式には、自動採点可能なものと手動採点が必要なものがあります。自動採点の場合、事前に設定した正解に基づいて採点が行われます。手動採点が必要な形式では、成績センタで手動で採点する必要があります。一部の形式では、ルーブリック(評価観点表)を使用した採点も可能です。
1. 質問形式一覧
このセクションでは、AIMS-Gifu システムで利用可能な17種類の質問形式が一覧で示されています。それぞれの質問形式について、詳細な設定方法は別マニュアル「テスト・アンケートの質問形式」を参照するよう指示されています。 一覧には、各質問形式の名称とともに、自動採点可能かどうか(自動採点、手動採点)が明記されています。 例として、ファイル提出(手動採点)、画像の座標指定(自動採点)、正誤問題(自動採点)、数値計算(自動採点)、数式計算(自動採点)、記述式問題(手動採点)などが挙げられています。 また、「質問文作成」(クイズボウル形式)のような、回答者が設問を作成するユニークな形式も含まれています。 さらに、Excel を使用して質問を作成する際の記号(FIL、MAなど)についても触れられており、Excel 活用による効率的な質問作成をサポートする仕組みが示されています。 ルーブリック(評価観点表)を用いた採点に対応している質問形式についてもマークで示されており、より詳細な評価を可能にする機能が備わっていることがわかります。
2. 自動採点と手動採点
このセクションでは、テストの採点方法として、自動採点と手動採点の2種類が説明されています。 自動採点は、予め設定した正解に基づいてシステムが自動的に採点を行う方法です。 すべての質問形式が自動採点に対応しているわけではない点に注意が必要です。 手動採点は、成績センタにアクセスして教員が手動で採点を行う方法です。 記述式問題など、自動採点できない質問形式では手動採点が必要になります。 自動採点と手動採点の使い分けによって、テストの効率性と採点の精度を両立させることが可能になります。 このセクションでは、それぞれの採点方法の特徴と、適切な適用場面について理解を深めることが目的となっています。 成績センタは、テストの採点結果や集計結果を確認するための重要なインターフェースとして機能します。 また、部分点の設定や、複数の正解パターンを設定できる機能についても言及されており、柔軟な採点に対応していることがわかります。
III.テストの再利用と削除
作成したテストやアンケートは、科目内でのコピーによる再利用や、科目間のエクスポート/インポートによる再利用が可能です。テストを削除する場合は、学生の答案も全て削除されることに注意が必要です。成績センタに空の列を残すかどうかのオプションを選択できます。テストを学生から非表示にすることで、答案を削除せずにテストを無効化できます。
1. テストの再利用 同一科目内
このセクションでは、同一科目内で作成済みのテストを再利用する方法について説明しています。テストやアンケートを一度実施すると、編集に制限がかかるため、再テストを行う場合などは、テストまたはアンケートのコピーを作成して編集する必要があると記載されています。 この方法は、既存のテストをベースに修正を加え、新たなテストを作成する場合に非常に有効です。 コピーを作成することで、元のテストデータは保持されたまま、修正を加えた新しいテストを作成できます。 この手順により、テスト作成にかかる時間を短縮し、効率的なテスト管理を実現できます。 ただし、コピー元のテストの内容によっては、修正可能な範囲に制限がある可能性がある点には注意が必要です。
2. テストの再利用 科目間
このセクションは、作成したテストやアンケートを異なる科目間で再利用する方法を説明しています。 同一科目内での再利用とは異なり、科目間での再利用には、まず該当のテストをエクスポートする必要があります。 エクスポートされたテストデータは、自分のマイドキュメントなどに保存されます。 その後、再利用したい科目を選択し、インポート機能を使ってテストを導入します。 この手順は、一度作成した質の高いテストを複数の授業で活用したい場合に非常に便利です。 時間と労力の節約に繋がり、教員の負担軽減にも貢献する有効な方法です。 ただし、科目の特性によっては、テスト内容の修正が必要となる場合もある点に注意が必要です。 エクスポートとインポートのプロセスは、ファイルのダウンロードとアップロードを伴うため、ネットワーク環境に注意する必要があります。
3. テストの削除と学生からの非表示
このセクションでは、テストの削除方法と、学生からテストを非表示にする方法について説明されています。 テストを削除する場合、学生の答案データも全て削除されるため、慎重な操作が求められます。 削除前に、データのバックアップを取っておくことを推奨します。 削除する際には、成績センタに空の列を残すかどうかを選択できます。 どちらを選択しても、テストの答案は削除されますが、「結果を保持」して削除する場合は、成績の詳細画面に点数のみが残るため、成績管理の記録として残したい場合に有効です。 一方、テストの答案を削除せずに学生からテストを非表示にしたい場合は、「リンクを利用可能にする」オプションを「いいえ」に設定することで実現できます。 この方法は、テストを一時的に非公開にしたい場合や、テストを修正後に改めて公開する場合などに便利です。 テストの削除と非表示化は、それぞれ異なる目的と結果をもたらすため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
