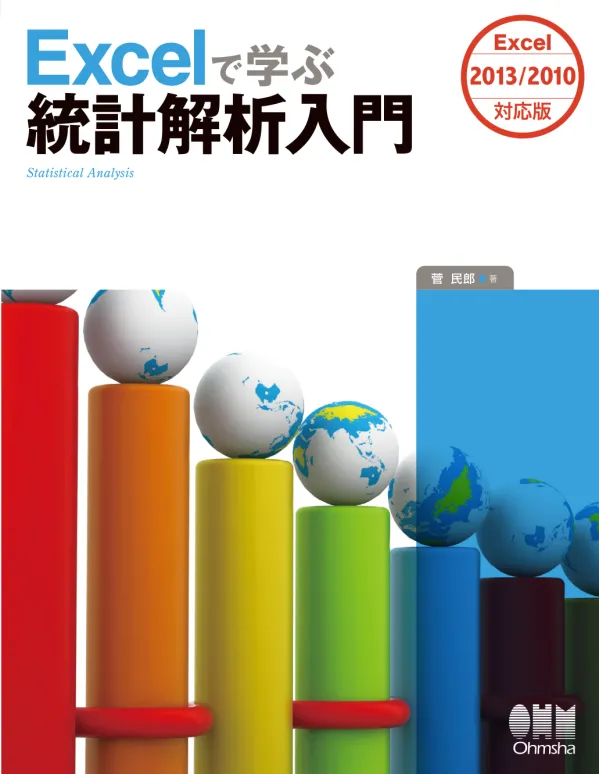
Excel統計解析入門
文書情報
| 専攻 | 統計学 |
| 会社 | 株式会社オーム社 |
| 文書タイプ | 入門書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.50 MB |
概要
I.本書の概要 Excelを使った統計解析入門
本書は、Microsoft Excelを用いた統計解析入門として、統計学の基礎から応用までを網羅的に解説しています。Excelデータ分析に必要な関数やツールに加え、より高度な解析を可能にするExcelアドインソフトウェアについても説明しています。特に、相関分析、回帰分析、そして統計学学習者にとって重要な到達点である統計的推定・検定を分かりやすく解説することで、推測統計学への理解を深めます。文科系・理科系を問わず、データ処理を行う社会人にとって必須の統計学入門書として最適です。 本書で学ぶことで、Excel統計解析スキルを向上させ、現実の仕事や研究に役立つデータ分析能力を習得できます。 アイスタット社のホームページから無料でダウンロードできるExcelアドインソフトウェアも活用することで、より効率的な解析が可能です。
1. 本書の目的と特徴
本書『Excelで学ぶ統計解析入門』は、Microsoft Excel を用いた統計解析の入門書として、1999年10月の初版発行以来、Excelのバージョンアップに合わせて改訂を重ねてきました。特に今回の改訂では、2013年版Excelに対応するとともに、書籍構成の見直し、特に推測統計学の解説を分かりやすく改善しました。 統計学は数式が多く難しいと捉えられがちですが、本書では数式にとらわれず、現実の仕事や研究に役立つ統計解析の方法に焦点を当てています。パソコンの普及によりデータ解析の機会が増加した現代において、大量のデータの処理に悩む多くのユーザーに対し、Excelを用いた効率的なデータ分析手法を提供することを目的としています。 そのため、統計解析の基礎から、相関分析、回帰分析、統計的推定・検定といった統計学における重要な概念までを網羅的に解説しています。Excel関数の活用方法やデータ分析ツールの使用方法に加え、Excel単体では難しい解析についても、著者が開発したExcelアドインソフトウェアを用いることで対応できるよう工夫されています。このアドインソフトウェアは、アイスタット社のホームページから無料でダウンロード可能です。文科系、理科系を問わず、データ処理を行う社会人にとって、本書は統計学の基礎を学ぶための貴重な一冊となるでしょう。
2. Excelアドインソフトウェアの活用
本書では、Excel標準機能に加え、著者が開発したExcelアドインソフトウェアも活用することで、より効率的で高度な統計解析を可能にしています。特に、統計学において難しいとされる「標本統計量の分布」についても、このアドインソフトウェアを用いたシミュレーションにより、視覚的に理解しやすく解説しています。 このソフトウェアの利用により、Excel標準機能では複雑で時間のかかる計算やグラフ作成を容易に行うことができ、データ処理の負担を軽減します。 アドインソフトウェアは、著者の会社である(株)アイスタットとオーム社のWebページから無料でダウンロードできるため、本書を購入した読者は誰でもすぐに利用を開始できます。 本書では、このアドインソフトウェアを用いた解析例も多数掲載されており、実践的な統計解析スキルを習得するために役立つでしょう。 これにより、Excelを用いた統計解析の敷居を低くし、より多くのユーザーが統計学を身近に感じ、活用できる環境を提供することを目指しています。
3. 本書の構成と学習方法
本書は、統計解析の基礎から、実践的な応用までを段階的に学ぶことができるように構成されています。初学者でも理解しやすいように、可能な限り平易な言葉で説明し、図表を豊富に用いることで、視覚的な理解を促進しています。 さらに、目次および本文には難易度を示す指標を付記することで、読者が自身のレベルや目的に合わせて学習を進めることができます。 データ処理において必ず理解すべき重要な事項と、目的に応じて学習する事項を明確に区別することで、効率的な学習を支援します。 本書で解説されている統計解析手法は、仕事や研究で頻繁に使用されるものばかりです。 Excelを用いた具体的な計算方法や、結果の解釈方法を丁寧に説明することにより、読者がすぐに実践で活用できるスキルを習得できるよう配慮しています。 統計学は、データから意味のある情報を引き出すための重要なツールです。本書を通じて、読者が統計学の楽しさ、有用性を理解し、データ分析のスキルを向上させることを期待しています。
4. 統計解析の有用性と現代社会
現代社会では、情報が溢れており、その情報を正しく理解し、活用することが非常に重要になっています。本書で学ぶ統計学は、情報を正確に読み取り、間違いなく伝え、有効に活用するための理論と手法を提供します。 統計解析は、単なるデータの処理にとどまらず、意思決定の根拠となる客観的な情報を提供し、より効果的な戦略立案を支援します。 本書は、統計解析の一般的な活用手順として、まず解決したい問題を明確化し、データ収集、統計解析手法の選定、Excelや統計解析ソフトウェアを用いた計算、そして結果の解釈という流れを提示しています。 この手順に沿って学習を進めることで、読者は体系的に統計解析スキルを習得することができます。 また、本書は、どの統計解析手法を選べばよいか、Excelや統計解析ソフトを用いた計算方法は何か、という2点を習得することを目標としています。これらのスキルを習得することで、読者は様々な場面でデータ分析を効果的に行うことができるようになります。
II.統計学の基礎とデータの種類
統計学は、現実の現象を解析し法則性を見出す学問です。本書では、記述統計学と推測統計学の両方を扱います。記述統計学では、集団の特徴(平均値、中央値、最頻値など基本統計量)を明らかにします。推測統計学では、部分的なデータから全体の傾向を推測します。扱うデータは、数量データ(量的データ)とカテゴリーデータ(質的データ)の2種類があり、それぞれ適切なデータ分析手法を用いる必要があります。
1. 記述統計学と推測統計学
統計学は、データの集まりから集団の特徴や傾向を明らかにする学問です。本書では、大きく分けて記述統計学と推測統計学の2つのアプローチを扱います。記述統計学は、得られたデータ全体を分析し、その集団の代表値(平均値、中央値、最頻値など)や散布度(データのばらつき)を計算することで、集団の特徴を要約します。 例えば、100人の身長と性別に関するデータがあれば、記述統計学を用いて平均身長や男性の割合などを求めることができます。 一方、推測統計学は、集団の一部(標本)から全体の性質を推測する手法です。 例えば、1000人の児童がいる小学校でお年玉の金額を調べるとき、全員を調査する代わりに200人だけを抽出して調査し、その結果から1000人の平均お年玉金額を推定するのが推測統計学の応用例です。記述統計学と推測統計学はどちらも集団全体の特性を把握するという共通の目的を持ちますが、利用するデータの範囲と分析アプローチが異なります。
2. 数量データとカテゴリーデータ
統計学では、扱うデータの種類を理解することが重要です。データは大きく分けて、数量データ(量的データ)とカテゴリーデータ(質的データ)の2種類があります。数量データは、数値で表され、大小関係や演算が意味を持つデータです。例えば、身長、体重、年収などは数量データです。これらのデータに対しては、平均値、中央値、標準偏差といった統計量を用いて分析することができます。 一方、カテゴリーデータは、数値で表される場合もありますが、大小関係や演算に意味がなく、分類を表すデータです。例えば、血液型、性別、居住地などはカテゴリーデータです。カテゴリーデータの分析では、度数分布や割合(比率)などを用いて、各カテゴリーの出現頻度を調べます。 本書では、これらのデータの種類を理解し、適切な分析手法を選択することが重要であると強調しています。例えば、血液型を数値でコード化しても、平均血液型を計算することに意味はありません。 数量データとカテゴリーデータそれぞれの特性を理解した上で、適切な統計手法を選択することで、より正確で有効なデータ分析を行うことができます。
3. 基本統計量とデータの分布
集団の特徴を把握するために用いられる基本統計量は、代表値と散布度の2つの側面から分析されます。代表値は、集団の中心的な傾向を示す値で、平均値、中央値、最頻値などが挙げられます。平均値はデータの合計をデータ数で割った値ですが、極端に大きい値や小さい値(外れ値)の影響を受けやすいという欠点があります。中央値はデータを大きさ順に並べたときの真ん中の値で、外れ値の影響を受けにくいというメリットがあります。最頻値は最も多く出現する値です。 散布度は、データのばらつき具合を表す指標で、範囲、分散、標準偏差などが用いられます。 これらの基本統計量に加えて、データの分布を視覚的に確認することも重要です。ヒストグラムや箱ひげ図などのグラフを用いることで、データの分布形状や中心傾向、ばらつきを直感的に理解することができます。 本書では、これらの基本統計量とデータの分布を理解することで、データの特徴を正確に把握し、適切な統計解析手法を選択するための基礎を築くことを目指しています。
III.相関分析と多変量解析
相関分析は、2つの変数の関係性を分析する手法です。例えば、飲酒量と血圧の関係などを調べることができます。多変量解析は、複数の変数の関係性を分析する手法で、例えば、様々な要因から血圧を予測するモデルを作成できます。本書では、これらのExcelを用いた実践的な解析方法を丁寧に解説します。
1. 相関分析 因果関係の解明
相関分析は、2つの変数間の関係性を分析する統計手法です。 例えば、血圧と飲酒量の関係、塩分摂取量と血圧の関係などを調べることができます。 相関分析では、変数間の関連の強さと方向性を示す相関係数を算出します。相関係数は-1から+1の範囲を取り、+1に近いほど正の相関(一方の変数が増加すると他方も増加する)、-1に近いほど負の相関(一方の変数が減少すると他方は増加する)、0に近いほど相関がないことを示します。 しかし、相関関係があるからといって、因果関係があるとは限りません。 相関分析の結果は、変数間の関連性の有無を示すものであり、一方の変数が他方の変数の原因であるとは断定できません。 血圧と飲酒量に相関関係が見られたとしても、飲酒が血圧上昇の直接的な原因であるとは必ずしも言えないということです。 本書では、相関分析の結果を解釈する際には、この点を十分に考慮する必要があることを強調しています。
2. 多変量解析 複数の要因の影響分析
多変量解析は、複数の変数間の関係性を同時に分析する高度な統計手法です。 相関分析が2つの変数に限定されるのに対し、多変量解析は3つ以上の変数を扱うことができます。 例えば、血圧に影響を与える要因として、塩分摂取量、喫煙の有無、飲酒量、年齢などを考え、これらの変数を用いて血圧を予測するモデルを作成することができます。 これは、複数の要因が複雑に絡み合った状況において、各要因が目的変数(ここでは血圧)にどのような影響を与えているかを明らかにするのに有効な手法です。 本書では、多変量解析によって、個々の要因が目的変数に及ぼす影響の度合いを定量的に評価し、予測モデルを作成することで、将来の状況を予測したり、より効果的な対策を立てるための情報を提供できると説明されています。 多変量解析は相関分析よりも高度な手法であり、適切な解釈には専門的な知識が必要となる場合があることを理解しておくことが重要です。
3. 目的変数と説明変数
相関分析や多変量解析においては、目的変数と説明変数の概念を理解することが重要です。目的変数とは、分析の対象となる変数、つまり結果を表す変数です。 説明変数とは、目的変数に影響を与える可能性のある変数、つまり原因となる変数です。 例えば、血圧を予測するモデルにおいては、血圧が目的変数、塩分摂取量、喫煙の有無、飲酒量、年齢などが説明変数となります。 相関分析では、目的変数と説明変数の間の関係性を分析し、相関係数を算出します。多変量解析では、複数の説明変数を用いて、目的変数を予測するモデルを作成します。 本書では、目的変数と説明変数の関係を明確に理解した上で、適切な統計解析手法を選択し、結果を正しく解釈することが、データ分析の成功に繋がることを強調しています。 この理解は、統計解析を正しく行い、得られた結果を現実の問題解決に役立てるために不可欠です。
IV.Excelによる実践的な統計解析
本書では、豊富な例題を用いて、Excelによる統計解析の実践的な方法を解説しています。Excel関数や「データ分析」ツール、そしてアイスタット社が提供するExcelアドインソフトウェアを駆使することで、複雑な計算やグラフ作成を効率的に行うことができます。 これにより、データ処理初心者でも、分析の仕方と解析ソフトの使い方を習得できます。
1. Excelを用いた統計解析手法
本書は、統計解析の基礎から応用までを、Microsoft Excel を使用して実践的に学ぶことができるよう構成されています。 Excel の標準機能である関数や「データ分析」ツールを用いた具体的な計算方法、グラフ作成方法を丁寧に解説することで、読者が容易に統計解析を実行できるよう支援しています。 特に、Excel の標準機能では処理が困難な複雑な計算や高度な解析については、著者が開発した Excel アドインソフトウェアを活用することで解決策を提供しています。このアドインソフトウェアは、(株)アイスタットとオーム社のウェブサイトから無料でダウンロード可能です。 本書では、例題を用いた実践的な解説を通して、Excel を使った統計解析の手順を段階的に学ぶことができます。 これにより、データ処理に不慣れな読者でも、分析手法の理解とソフトウェアの操作方法を同時に習得することが可能です。 そのため、統計解析の初心者にとって、実践的なスキルを身につけるための最適な教材となっています。
2. Excelアドインソフトウェアによる高度な解析
Excel の標準機能では対応できない高度な統計解析についても、本書では著者が開発した Excel アドインソフトウェアの活用を推奨しています。 このソフトウェアは、特に「標本統計量の分布」といった、統計学において理解が難しいとされる概念についても、シミュレーションを通して視覚的に理解できるよう設計されています。 ソフトウェアを使用することで、複雑な計算を簡素化し、結果を分かりやすく表示することで、データ分析の効率化と理解度向上を図ることができます。 また、本書では、このアドインソフトウェアを用いた具体的な解析事例が多数提示されており、実践的なスキル習得に役立ちます。 無料提供されているため、本書の読者は追加費用を負担することなく、高度な統計解析を体験し、習得することが可能です。 このアドインソフトウェアは、本書の内容をより深く理解し、実践的に活用するための重要なツールと言えます。
3. 分析手法の選択と結果の解釈
本書では、統計解析を行う上で重要な2点、すなわち「解決したいテーマに対してどの統計解析手法を使用すべきか」と「Excel や統計解析ソフトを用いた計算方法は何か」を習得できるよう構成されています。 そのため、本書は単なる計算方法の説明にとどまらず、適切な統計手法を選択するための知識と、得られた結果を正しく解釈するための能力を養うことを目的としています。 数式を多用した複雑な説明を避け、図表や例題を豊富に用いることで、初学者でも理解しやすいように工夫されています。 特に、文系出身者であっても、本書の内容を理解し、実践的に活用できるよう、分かりやすい解説を心がけています。 データの質に関わらず、分析者の技量と解析ソフトの使いこなしが、データ分析の成果を大きく左右することを本書は強調しています。 本書で習得した知識とスキルは、読者の業務や研究において、データに基づいたより正確な意思決定を可能にするでしょう。
